
重度障害者や通勤が困難な障害者を雇用する事業主にとって、従業員の通勤支援は重要な課題です。国は、こうした事業主を支援するため、「重度障害者等通勤対策助成金」を設けています。中でも、住宅手当の支払いを助成する制度は、通勤困難な障害者の居住地選択を広げ、雇用機会の拡大に繋がる重要な施策です。この記事では、「重度障害者等通勤対策助成金」の中でも、住宅手当の支払助成金に焦点を当て、対象者、受給条件、申請方法などをわかりやすく解説します。この助成金を活用することで、企業は障害者雇用を促進し、従業員は安心して働くことができる環境づくりに貢献できます。
住宅手当の支払助成金:制度の全体像を理解する

重度障害者や通勤困難な障害者を雇用する事業主に対し、通勤を容易にするための措置費用を助成する制度があります。今回は、その中でも住宅手当の支払助成金に焦点を当て、制度の全体像を解説します。障害者雇用は進んでいるものの、通勤の困難さが雇用を阻むケースは少なくありません。特に重度障害者の場合、公共交通機関の利用が難しかったり、介助が必要だったりと、通勤の負担は非常に大きくなります。住宅手当助成金は、職場に近い場所に居住することを可能にし、通勤の負担を軽減することで、障害者の就労意欲を高め、雇用継続を支援します。
助成金の種類とそれぞれの目的:通勤をサポートする様々な助成金
重度障害者等用住宅の賃借助成金、指導員の配置助成金、通勤用バスの購入助成金など、様々な種類があります。これらは障害者の通勤を多角的にサポートすることを目的としています。
住宅手当の支払助成金とは:支給対象となる住宅手当の定義
重度障害者等が住宅を賃借している場合に、住宅手当を支給する事業主に対して助成が行われます。他の従業員に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支給する場合が対象です。
令和7年度の変更点:最新情報をチェック!
令和7年度の変更点については、高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課からの情報公開をお待ちください。申請の際は必ず最新情報を確認してください。不明な点は、各都道府県支部の窓口に問い合わせるのが確実です。
他の助成金との違い:併用は可能か?
住宅手当の支払助成金と他の助成金との併用については、個別の要件を確認する必要があります。詳細はお問い合わせください。
支給要件:事業主と障害者の両方をチェック

通勤支援の助成金を受け取るには、事業主と障害者の双方が一定の要件を満たす必要があります。
支給対象となる事業主の要件:雇用状況、支払い状況など
重度障害者等を労働者として雇用していることが大前提です。次に、その障害者の通勤が困難であり、住宅手当の支給など、通勤を容易にするための措置を講じなければ雇用継続が難しいと認められる必要があります。また、住宅手当を支給する場合は、就業規則等に定め、他の労働者との公平性を保つ必要があります。
支給対象となる障害者の要件:障害の種類、通勤困難の理由など
助成金の対象となる障害者は、重度障害者、知的障害者、精神障害者などが該当します。重要なのは、障害の種類だけでなく、その障害によって通勤が著しく困難であることです。例えば、公共交通機関の利用が難しい、長距離の移動が困難といった具体的な理由が必要です。
“通勤が容易でない”とは?:具体的な事例で解説
「通勤が容易でない」とは、単に通勤時間が長いというだけでなく、障害特性によって公共交通機関の利用が困難、または著しい負担を伴う場合を指します。例えば、肢体不自由のある方が、階段の多い駅を利用しなければならない、精神障害のある方が、人混みの中で強いストレスを感じてしまうなどが該当します。
6ヶ月ルール:雇用期間に関する注意点
助成金の申請時点で、対象となる障害者の雇用期間が6ヶ月を超えている場合、原則として対象外となります。ただし、中途障害者となった場合や、障害の重度化が認められる場合は例外となります。また、人事異動や事業所の移転など、やむを得ない理由がある場合も考慮されます。
助成金額と支給期間:いくら、いつまでもらえる?

重度障害者等の通勤を容易にするための住宅手当支給に対する助成金は、事業主の負担を軽減し、障害者の雇用を促進する制度です。
- 支給限度額:対象者1人につき月額6万円が上限です。これは、他の従業員に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う場合に適用されます。
- 支給期間:最長10年間、助成を受けることができます。
- 支給対象費用の算定方法:支給対象となるのは、障害者に支払われる住宅手当から、他の従業員に通常支払われる住宅手当の限度額を差し引いた額です。例えば、住宅手当として8万円を支給し、通常限度額が2万円の場合、対象となるのは6万円となります。
- 75%の経費補助率:事業主の負担を大幅に軽減します。上記の例では、6万円の75%にあたる4.5万円が助成されます。
この助成金を活用することで、事業主は重度障害者の雇用を積極的に進め、従業員の定着を促進することができます。
支給対象となる措置の要件:住宅に関する条件を詳しく解説

重度障害者等の通勤を容易にするための住宅手当支給に対する助成金には、支給対象となるための住宅に関する要件がいくつか存在します。
- 通勤困難性の証明:障害がなければ公共交通機関で通勤できるにもかかわらず、障害特性により通勤が困難であると認められる必要があります。
- 新規賃借の重要性:通勤を容易にするために新規に住宅を賃借し、賃料を支払っていることが条件です。採用前から居住していた住宅や、事業主が賃貸していた住宅の契約を切り替えたものは対象外となります。
- “10分程度の距離”とは?:申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であり、徒歩または車いす等で通勤できることが求められます。公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等は対象外です。
- 障害特性への配慮:申請住宅が、支給対象障害者の障害特性に配慮したものである必要があります。バリアフリー化などが考慮されます。
- 就業規則への明記:支給対象障害者以外の労働者が住宅を賃借した場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えた住宅手当の支払いを、就業規則等に定めた上で行っている必要があります。
申請手続きの流れ:ステップごとの詳細解説

重度障害者等を雇用する事業主向けの通勤対策助成金。申請は2段階です。まず、受給資格認定申請では、申請期間内に必要書類(申請書、事業計画書等)を事業所管轄の都道府県支部に提出します。電子申請も可能です。次に、支給請求では、請求期間内に支給請求書等を提出します。
申請書類は、記入例を参考にミスなく作成しましょう。添付書類のチェックリストを活用し、漏れがないように準備してください。オンライン申請は時間や場所を選ばず便利です。詳細や最新情報は、各都道府県支部の高齢・障害者業務課等にお問い合わせください。
申請書類と様式:どこで入手できる?

重度障害者等の通勤をサポートする助成金申請には、適切な書類準備が不可欠です。
- 主要な申請書類は、受給資格認定申請書や支給請求書などです。これらの様式は、高齢・障害者雇用支援機構のウェブサイトからダウンロードできます。
- 記入にあたっては、よくある間違い(例えば、最新様式でない、必要事項の未記入など)に注意し、記入例を参考に丁寧に作成しましょう。
審査のポイントと注意点:不備なくスムーズな申請のために

重度障害者等の通勤を支援する助成金制度は、障害者雇用を促進する上で重要な役割を果たします。申請をスムーズに進めるためには、審査のポイントと注意点を理解しておくことが不可欠です。
審査で重視される点
審査では、まず通勤困難性の証明が重要視されます。障害の種類や程度、公共交通機関の利用状況などを具体的に説明する必要があります。次に、住宅の適合性です。通勤時間や距離、住宅のバリアフリー状況などが審査されます。
よくある不備とその対策
申請書類の不備はよく見られます。申請前にチェックリストを活用し、必要書類が全て揃っているか確認しましょう。情報不足も不備の原因となります。通勤困難性や住宅の適合性について、詳細な情報を記載するように心がけてください。
認定後の変更手続き
認定後に住所変更や雇用状況の変化があった場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、助成金が打ち切られる可能性があるので注意が必要です。
助成金の取り下げ
やむを得ない事情で助成金を取り下げる場合は、所定の手続きが必要です。取り下げ理由を明確に説明し、必要な書類を提出しましょう。
助成金活用事例:成功事例から学ぶ

企業が助成金を活用し、障害者雇用を促進した事例を紹介します。中小企業では、重度障害者等通勤対策助成金を活用し、通勤困難な従業員のために住宅手当を支給、定着率向上に成功しました。大企業では、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用し、職場環境改善や研修制度を充実させ、多様な人材が活躍できる環境を実現しています。業種別では、IT企業が在宅勤務制度を導入する際に助成金を利用し、通勤困難な障害者の雇用を拡大しました。これらの事例から、助成金が障害者雇用促進と企業の成長に貢献することがわかります。
Q&A:よくある質問と回答
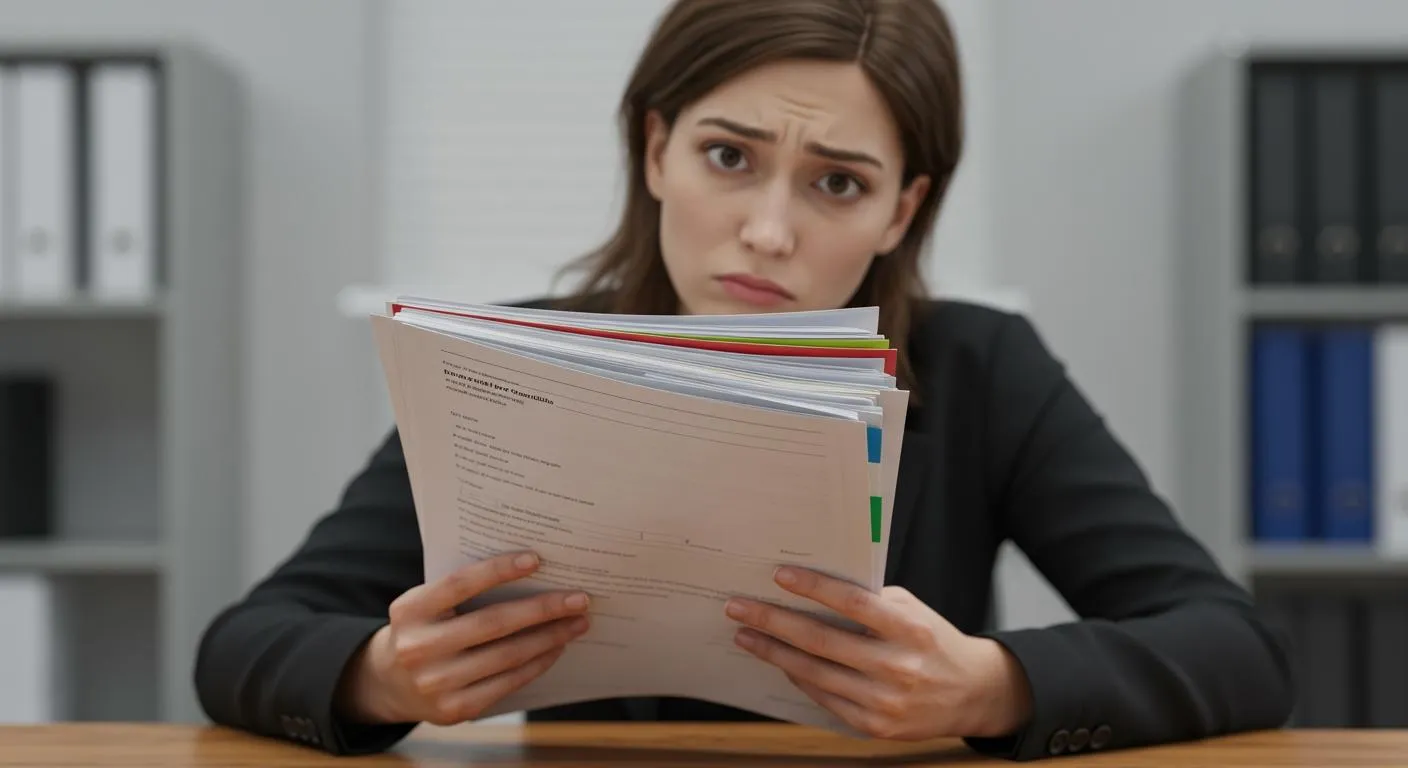
Q1:他の助成金との併用は可能ですか?
他の助成金との併用については、個別の助成金ごとに条件が異なります。重度障害者等通勤対策助成金と他の助成金の併用を検討される場合は、高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課へご確認ください。
Q2:申請期間を過ぎてしまった場合は?
原則として、申請期間を過ぎた場合は助成金を受け取ることはできません。各助成金には申請期間が定められているため、事前に確認し、期間内に申請を行うようにしてください。
Q3:住宅手当の金額を変更したい場合は?
住宅手当の金額を変更する場合は、変更後の金額で改めて認定申請が必要となる場合があります。詳細については、高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課へお問い合わせください。
Q4:退職した場合、助成金はどうなりますか?
助成金の支給は、対象となる重度障害者等の雇用を継続することを前提としています。退職された場合、助成金の支給が停止される可能性があります。
Q5:審査に落ちてしまった場合は?
審査に落ちた場合、理由を確認し、改善できる点があれば再申請を検討することができます。審査結果に関する問い合わせも、高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課で受け付けています。
問い合わせ先と関連情報:困ったときの相談窓口

重度障害者、知的障害者、精神障害者の方の雇用に関して、通勤を容易にするための助成金制度があります。もし制度について疑問点があれば、お住まいの都道府県支部、高齢・障害者業務課までお気軽にお問い合わせください。
相談窓口一覧
各都道府県支部の高齢・障害者業務課では、助成金に関する相談を受け付けています。
高齢・障害者雇用支援機構のウェブサイト
最新情報やFAQが掲載されていますので、ぜひご確認ください。
地域障害者職業センター
職業相談や職業訓練に関する情報が得られます。
障害者雇用に関する情報提供
関連機関のリンク集も参考に、必要な情報を見つけてください。
まとめ:住宅手当助成金を活用して、障害者雇用を促進しよう!

障害者雇用を積極的に進める企業にとって、重度障害者等通勤対策助成金は非常に有効な制度です。特に住宅手当の助成は、通勤困難な障害者の居住地を職場近くに確保し、安定した雇用に繋げられます。
助成金活用のメリットを再確認
助成金を利用することで、企業の経済的負担を軽減しつつ、障害者が働きやすい環境を整備できます。通勤の負担軽減は、障害者の定着率向上にも繋がり、結果として企業の社会的責任を果たすことにも貢献します。
令和7年度の助成金申請に向けて
令和7年度も同様の助成金制度が継続される予定です。最新情報を確認し、早めの準備を心がけましょう。各都道府県支部の高齢・障害者業務課への問い合わせも有効です。
障害者雇用に関する企業の社会的責任
障害者雇用は、企業が社会の一員として果たすべき重要な責任です。助成金制度を積極的に活用し、障害者が能力を発揮できる社会の実現を目指しましょう。
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




