
障害のある方の社会参加を促進し、企業の雇用を支援する「重度障害者等通勤対策助成金」。中でも、通勤用自動車購入助成金は、移動に困難を抱える方にとって、就労への扉を開く重要な制度です。本記事では、令和7年度の最新情報に基づき、助成金の目的、対象者、申請方法、活用事例などをわかりやすく解説します。障害者雇用を検討中の企業担当者の方、またはご自身が対象となる可能性のある方は、ぜひ本記事を参考に、制度の理解を深め、積極的な活用をご検討ください。
助成金制度の目的と概要:就労機会の拡大を目指して

重度障害者等通勤対策助成金は、障害者雇用促進法に基づき、通勤が困難な障害者の雇用を支援し、就労機会の拡大を目指す制度です。通勤用自動車購入の助成金は、その一環として、通勤を容易にするための措置費用の一部を補助します。住宅、指導員、通勤バスなど、様々な種類の助成金があり、企業の状況や障害者のニーズに合わせて活用できます。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用自動車購入)の基本

対象となる事業者と障害者の条件:誰が助成を受けられるのか?
この助成金の対象となるのは、重度障害者、知的障害者、精神障害者、または通勤が困難な障害者を雇用する事業主です。ただし、運転免許の有無や障害の程度など、具体的な条件があります。詳細については、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にお問い合わせください。
通勤用自動車の定義と要件:どのような車が対象となるのか?
助成対象となる自動車は、自家用車や障害に合わせて改造された自動車です。乗車定員、構造、設備に関する規定があり、通勤用途に限定されます。業務での使用は認められません。
令和7年度 助成金の詳細情報:金額、期間、手続き

令和7年度も、障害者雇用を促進する企業向けに、重度障害者等通勤対策助成金が提供されます。特に、通勤用自動車の購入に対する助成は、障害者の通勤を支援する上で重要な役割を果たします。
助成金額と対象経費:いくら助成されるのか?
自動車1台あたり上限150万円、または条件によっては250万円まで助成されます。車両本体価格に加え、障害に合わせた改造費用や寒冷地仕様なども対象となる場合があります。経費補助率は75%です。
申請期間とスケジュール:いつまでに申請すれば良いのか?
令和7年度の申請期間は2024年4月1日から2025年3月31日までです。事前認定申請が必須であり、期限を過ぎると申請できなくなるため注意が必要です。支給請求書の提出期限も忘れずに確認しましょう。
申請に必要な書類と手続き:どのように申請するのか?
認定申請書や支給請求書など、必要な書類は高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトから入手できます。申請方法は、持参、郵送、e-Gov電子申請サービスのいずれかを選択できます。手続きの詳細は事前に確認しましょう。
申請を成功させるためのポイント:スムーズな申請のために
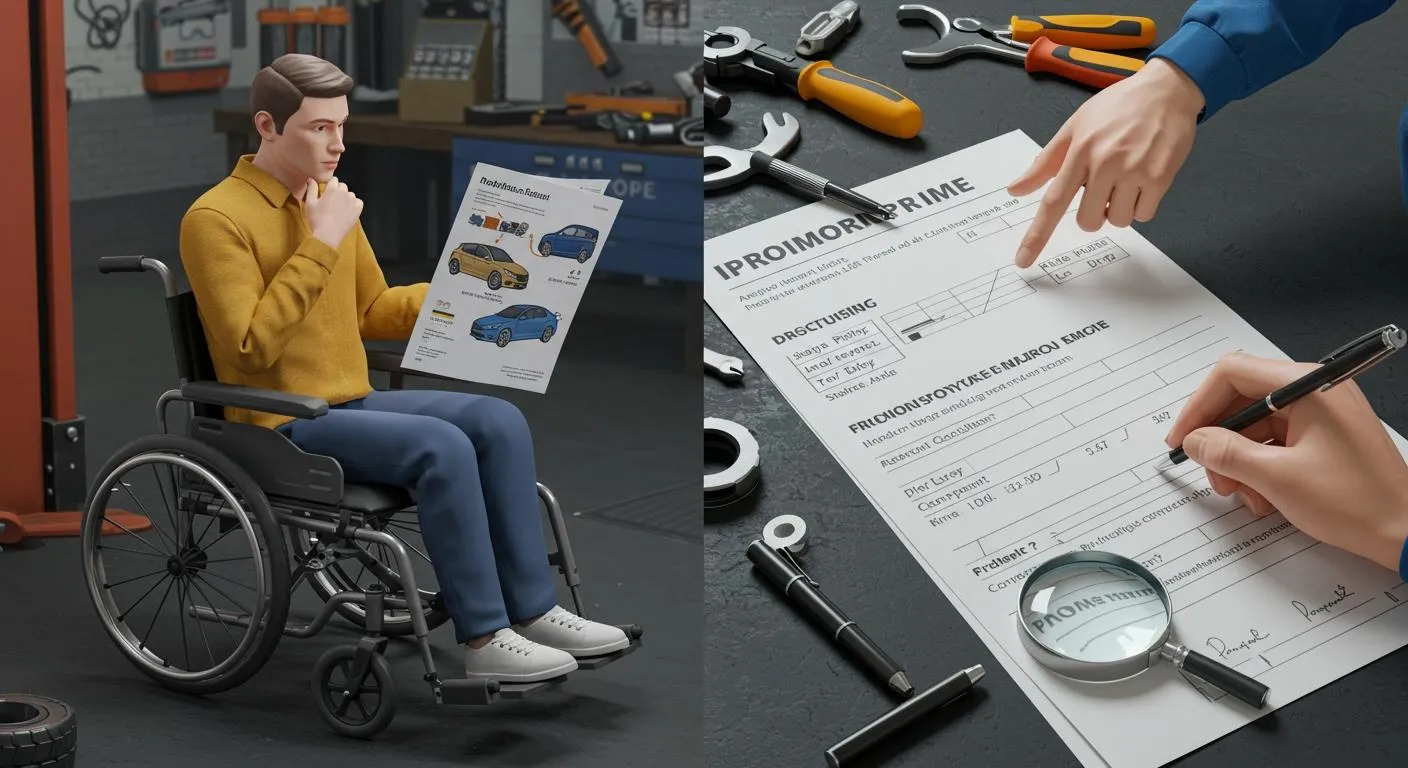
申請書類作成の注意点:何に気をつければ良いのか?
申請書類の記入例や注意点を必ず確認しましょう。障害者の通勤困難さを具体的に示すことが重要です。例えば、公共交通機関の利用が難しい理由や、通勤時間の長さなどを詳細に記述します。虚偽の記載は絶対に避けましょう。
助成対象となる自動車の選定:どのような車を選べば良いのか?
障害の種類や程度に合わせた適切な車種を選定しましょう。改造が必要な場合は、信頼できる改造業者を選び、見積もりを取得します。中古車の購入が助成対象となるか事前に確認が必要です。
よくある質問と回答(Q&A):疑問を解消してスムーズに申請
申請が却下される事例として、書類の不備や対象外の自動車を選定した場合などが挙げられます。申請前に要件をしっかり確認しましょう。助成金に関する疑問点は、管轄の都道府県支部へ問い合わせて解消しましょう。
助成金活用事例と企業の声:導入企業の成功事例

障害者雇用を積極的に進める企業にとって、助成金は大きな支えとなります。特に重度障害者の通勤を支援する「重度障害者等通勤対策助成金」は、通勤用自動車の購入費用を補助するなど、手厚いサポートが魅力です。
助成金を活用したA社では、重度障害のある社員が自動車通勤できるようになり、通勤の負担が軽減されたことで、より業務に集中できるようになったという声が上がっています。また、B社では、知的障害者の雇用にあたり、指導員配置助成金を活用。手厚いサポート体制を構築することで、知的障害者の職場定着率向上に成功しました。
助成金申請には、書類作成や手続きなど、一定の苦労も伴います。しかし、C社の担当者は「助成金のおかげで、これまで雇用をためらっていた障害のある方の採用に踏み切ることができた。社会貢献にもつながり、社員全体の意識も向上した」と語ります。助成金は、企業と障害のある方、双方にとって大きなメリットをもたらす制度と言えるでしょう。
関連情報と問い合わせ先:さらに詳しく知りたい方へ

重度障害者等の通勤を支援する各種助成金に関するお問い合わせは、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口となります。
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構: 制度全般に関する質問や、申請手続きの概要について確認できます。
詳細な申請方法や個別の状況に関する相談は、事業所が所在する都道府県支部の高齢・障害者業務課までお問い合わせください。
- 各都道府県支部の高齢・障害者業務課: 申請書類の書き方、必要書類、具体的な事例に関する相談など、より詳細な情報が得られます。
また、障害者雇用に関する一般的な情報や、他の支援制度については、以下の情報サイトも参考になります。
- 障害者雇用に関する情報サイト: JEEDのウェブサイトなどで、障害者雇用のノウハウや企業の取り組み事例などを知ることができます。
これらの窓口を活用し、貴社の障害者雇用を促進してください。
まとめ:助成金を活用して、誰もが働きやすい社会へ

重度障害者等通勤対策助成金の重要性の再確認:改めて制度の意義を理解する
重度障害者等通勤対策助成金は、通勤が困難な障害者の雇用を促進する重要な制度です。企業が障害者の通勤をサポートする費用を助成することで、障害者の就労機会を拡大し、社会参加を支援します。
助成金活用による企業と障害者の双方のメリット:双方にとってwin-winな関係
助成金の活用は、企業と障害者の双方にメリットをもたらします。企業は経済的な負担を軽減しながら、障害者の雇用を促進できます。障害者は通勤の負担を軽減し、安心して働くことができます。例えば、通勤用自動車の購入助成金を利用することで、公共交通機関の利用が難しい障害者の通勤を支援できます。
今後の展望:障害者雇用のさらなる促進:より良い未来のために
助成金制度の周知と活用促進により、障害者雇用はさらに進むことが期待されます。企業は助成金を活用し、障害者が働きやすい環境を整備することで、多様な人材が活躍できる社会の実現に貢献できます。重度障害者等通勤対策助成金を活用し、誰もが働きやすい社会を実現しましょう。
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




