
金融業界の皆様へ、企業の社会的責任を果たす上で重要なテーマである障害者雇用。本記事では、その課題解決を支援する「障害者介助等助成金」について解説します。特に、重度障害者の雇用継続を後押しする「職場介助者の配置または委嘱助成金」に焦点を当て、制度概要から申請方法、成功事例までを網羅的にご紹介します。助成金活用は、合理的配慮の提供を促進し、新たな人材の活用による企業価値向上にも繋がります。ぜひ、本記事を参考に、助成金制度の活用をご検討ください。
障害者雇用における企業の課題と助成金の重要性

障害者雇用は、企業の社会的責任を果たす上で重要なテーマですが、合理的配慮の提供や職場環境の整備など、多くの課題が存在します。そこで注目したいのが、国や自治体が提供する助成金制度です。特に「障害者介助等助成金」は、企業の負担を軽減し、障害のある方が活躍できる環境づくりを後押しします。
職場介助者の配置または委嘱助成金とは?助成内容をわかりやすく解説

障害者の雇用促進と職場定着を目的としたこの助成金は、特に重度視覚障害者や重度四肢機能障害者の雇用に際し、職場介助者を「配置」または「委嘱」する場合に、その費用の一部が助成されます。「配置」は、企業が従業員として介助者を雇用すること。「委嘱」は、外部の専門家や事業者に介助を依頼することを指します。中小企業だけでなく、大企業も対象となる場合があります。障害のある方が安心して働ける環境づくりを支援する制度です。
助成率と助成額:いくらもらえるのか?
障害者介助等助成金は、新規・継続、配置・委嘱で助成率が異なります。新規配置の場合、助成率は3/4で月額15万円が上限です。継続配置では2/3、月額13万円が上限となります。委嘱の場合、新規は3/4で年間150万円または24万円(業務内容による)、継続は2/3で年間135万円または22万円です。例えば、重度視覚障害者のAさんの業務をサポートするため、新たに職場介助者を配置した場合、月額最大15万円の助成が受けられます。自社がどの程度助成されるか、事前にシミュレーションすることをおすすめします。
支給期間:最長10年!長期的な支援を受けられる
障害者介助等助成金は、新規配置・委嘱の場合、最長10年間支援が受けられる点が魅力です。継続配置・委嘱の場合は最長5年となります。
10年間の支給期間を最大限に活用するには、雇用計画を綿密に立て、定期的な面談や評価を通じて、介助者のスキルアップや業務内容の見直しを行うことが重要です。
支給期間終了後は、助成金に頼らずとも雇用を継続できるよう、職場環境の改善や、障害者本人のスキルアップ支援などを計画的に進める必要があります。雇用継続のための具体的な計画を立て、実行に移しましょう。
助成対象となる経費:人件費だけじゃない!

障害者介助等助成金は、職場環境改善に役立つ制度です。助成金の対象となる経費は、人件費だけではありません。
- 職場介助者の人件費:給与、賞与、社会保険料などが対象です。新規配置だけでなく、継続的な雇用も支援されます。
- 委嘱費用:外部の専門家への謝金や交通費も対象となります。手話通訳者や職場支援員への依頼も可能です。
- その他、助成対象となる経費の例:相談窓口の設置費用、職場復帰支援プログラムの費用なども対象となる場合があります。
助成金を活用して、より働きやすい環境を整備しましょう。
申請方法と必要書類:スムーズな申請のために
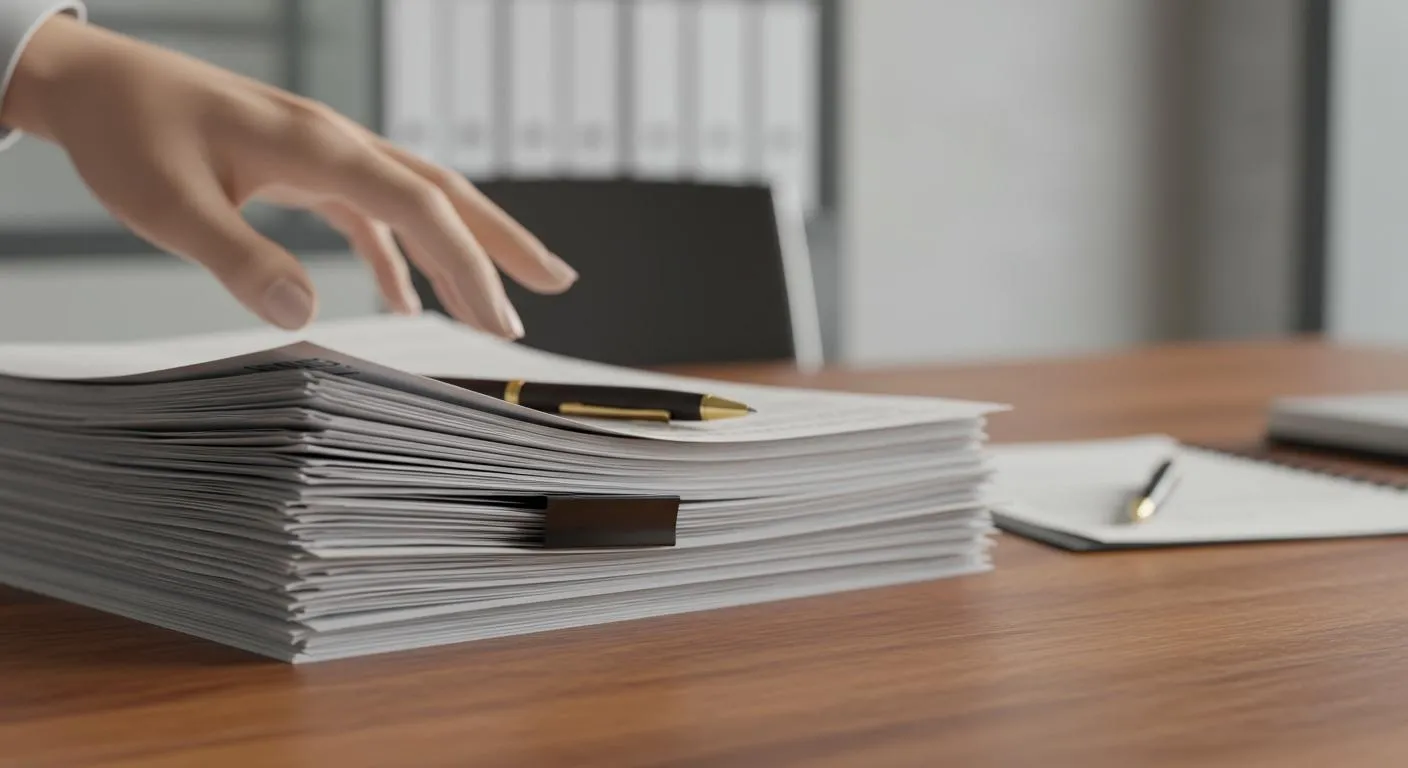
障害者介助等助成金を受け取るには、原則として、事前に受給資格認定申請を行い、認定後に支給申請を行う2段階のプロセスが必要です。
申請期限
配置・委嘱に関する助成金の場合、認定申請は配置・委嘱の前日までに行う必要があります。支給申請は、配置・委嘱日から6カ月ごとに区切った期間の末日の翌月末日が期限です。
必要書類
申請には、申請書、雇用契約書、委嘱契約書などが必要です。助成金の種類によって必要な書類が異なるため、事前に確認しましょう。
申請時の注意点
書類に不備があると申請が遅れる可能性があります。また、申請期限を過ぎると助成金を受け取ることができなくなるため、注意が必要です。
申請の流れをステップごとに解説

障害者介助等助成金を得るには、定められた手順を踏む必要があります。スムーズな申請のために、各ステップを理解しておきましょう。
ステップ1:事前準備(情報収集、計画策定)
まずは、自社がどの助成金の対象となるか、詳細な情報を収集します。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式サイトで最新情報を確認し、具体的な計画を立てましょう。
ステップ2:受給資格認定申請
計画に基づき、必要な書類を準備し、JEEDへ受給資格の認定を申請します。申請期限は助成金の種類によって異なるため、注意が必要です。
ステップ3:配置・委嘱の実施
受給資格認定後、計画通りに職場介助者の配置や手話通訳者の委嘱などを実施します。
ステップ4:支給申請
配置・委嘱後、実際に支払った費用に基づいて、助成金の支給申請を行います。
ステップ5:助成金の受給
審査を通過すれば、助成金が支給されます。支給された助成金は、障害のある従業員の支援のために有効活用しましょう。
助成金活用の成功事例:企業事例から学ぶ

障害者雇用を積極的に進める企業にとって、助成金は強力なサポートとなります。「障害者介助等助成金」は、障害のある方が働きやすい環境を整備する上で役立ちます。ここでは、助成金を活用した企業の成功事例をご紹介します。
事例1:重度視覚障害者の雇用と職場介助者の配置
ある企業では、重度視覚障害のある方を雇用するにあたり、職場介助者を配置しました。助成金を活用することで、介助者の人件費を抑えつつ、視覚障害のある方が安心して業務に取り組める環境を整備。結果、その方は専門知識を活かし、チームに貢献しています。
事例2:重度四肢機能障害者の雇用と職場介助者の委嘱
別の企業では、重度四肢機能障害のある方を雇用する際に、外部の専門機関に職場介助を委嘱しました。助成金により、委嘱費用を軽減。その方は、在宅勤務を中心に、高度なデータ分析業務を担当し、企業の業績向上に貢献しています。
事例から学ぶ:助成金活用のポイント
これらの事例から、助成金を活用する上でのポイントが見えてきます。まず、自社の状況に合った助成金を選ぶことが重要です。次に、申請書類を正確に準備し、期限内に提出することが求められます。そして、障害のある方のニーズを的確に把握し、適切なサポート体制を構築することが成功の鍵となります。助成金を有効活用し、誰もが活躍できる職場環境を実現しましょう。
注意点とよくある質問:申請前に確認しておきたいこと

障害者介助等助成金の申請を検討する際、注意すべき点やよくある質問をまとめました。
助成金の返還事由
不正受給はもちろんのこと、雇用状況の悪化も返還事由となる場合があります。助成金受給後も、雇用状況を維持することが重要です。
他の助成金との併用
障害者雇用に関する他の助成金との併用は、可能な場合と不可能な場合があります。事前に事務局に確認しましょう。
Q&A:よくある質問とその回答
- Q: 申請期間は?
- A: 助成金の種類によって異なります。必ず事前に確認しましょう。
- Q: 助成金の対象となる合理的配慮の範囲は?
- A: 個別の状況によって判断が異なります。事務局に相談することをおすすめします。
- Q: 申請に必要な書類は?
- A: 申請する助成金の種類によって異なります。事務局のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせましょう。
関連助成金:他の助成金も活用しよう

障害者雇用を促進するため、手話通訳や職場介助など、様々な助成金が用意されています。
- 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金:聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳者を委嘱する費用を助成します。
- 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金:重度訪問介護サービス利用者への業務支援を委託する費用を助成します(自治体連携必須)。
- 障害者相談窓口担当者の配置助成金:障害者への合理的配慮を提供する相談窓口の人員配置を支援します。
- 職場支援員の配置又は委嘱助成金:障害者の職場定着を支援する職場支援員の配置・委嘱費用を助成します。
- 職場復帰支援助成金:休職者の職場復帰を支援する措置に対して助成金が支給されます。
これらの助成金を活用し、より働きやすい環境づくりを目指しましょう。詳細な条件や申請方法については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式ホームページをご確認ください。
まとめ:助成金を活用して、誰もが活躍できる職場へ

職場介助者の配置・委嘱助成金は、障害者雇用において重要な役割を果たします。助成金によって、企業は経済的な負担を軽減しつつ、障害者が働きやすい環境を整備できます。
助成金を活用することで、障害者の雇用機会の拡大、職場定着率の向上、企業の社会的責任の遂行など、多くのメリットが得られます。障害者雇用促進は、多様性を尊重する社会の実現に不可欠であり、今後のさらなる発展が期待されます。
助成金に関する相談は、ハローワークや高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)などで受け付けています。詳細な情報は、各機関の公式ウェブサイトで確認できます。
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




