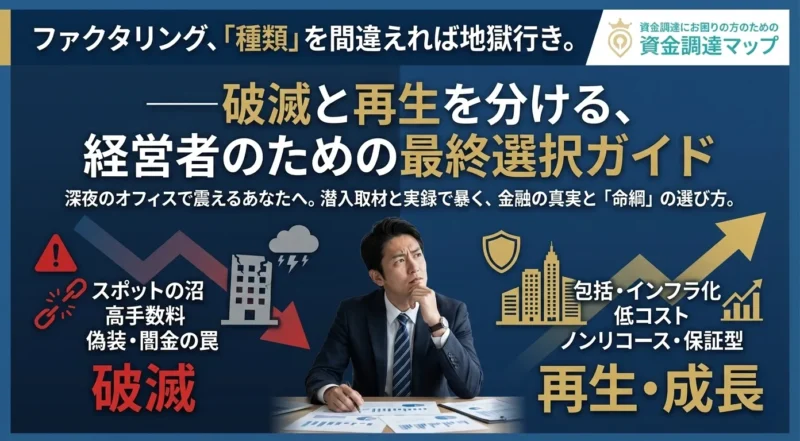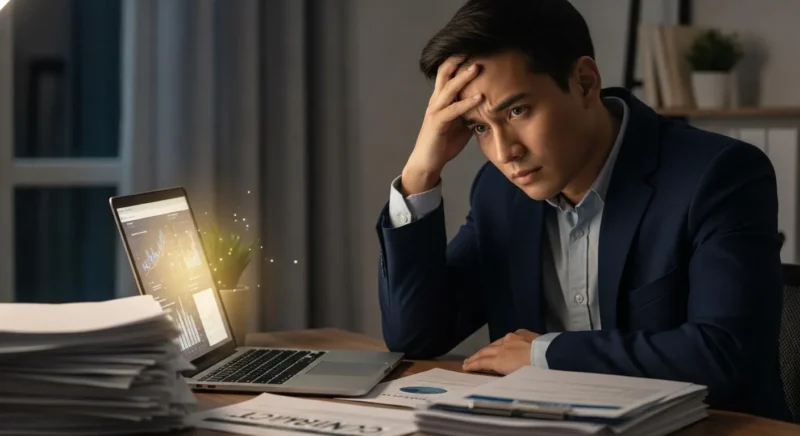電子記録債権(でんさい)とファクタリングは、いずれも企業の資金管理や資金調達において注目度が高まっている手法です。しかし、両者は目的・仕組み・導入効果が大きく異なり、「どちらを選べばよいのか分からない」という声も少なくありません。本記事では、金融・会計実務に精通した筆者が、最新の法制度・市場動向・事例をもとに、両者の定義や仕組みからメリット・デメリット、選び方、将来性までを徹底解説します。資金繰り改善や事務効率化を検討中の経営者・財務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事
電子記録債権(でんさい)の定義と仕組み

電子記録債権とは何か
電子記録債権(通称:でんさい)とは、電子的な記録によって発生・譲渡が管理される新しい形態の金銭債権です。従来の債権は紙の契約書や手形を前提としており、発行・郵送・保管といった物理的な作業や印紙税の負担が伴いました。一方、電子記録債権は電子債権記録機関の原簿に記録され、債権者・債務者・償還期日・金額・承諾などが電子的に一元管理されます。
この制度は2008年に成立した電子記録債権法を基盤に運用されており、日本では全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が代表的な記録機関です。債権譲渡の際には承諾や依頼に基づき、記録変更が即座に反映されるため、取引の透明性が高まります。
利用シーンとしては、企業間取引での売掛金の受け渡し、長期的な大口取引の決済、資金管理の効率化などが挙げられます。例えば、安定した取引先を持つ企業が紙の手形を廃止し、でんさいに移行することで、郵送や紛失リスクを回避し、印紙税を削減できます。
電子記録債権の仕組み
電子記録債権は次のような流れで生成・流通します。
- 売買契約や請負契約に基づき、債権者が債務者に請求書を発行。
- 債務者が支払期日・金額・債権者名を確認し、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)の原簿に発生記録を依頼。
- 記録機関が契約内容に基づき、原簿に電子債権を登録。発生日や償還期日なども自動的に反映。
- 必要に応じて、債権譲渡や分割譲渡を記録。承諾を得たうえで第三者に譲渡可能。
- 償還期日に債務者が指定口座に入金し、記録機関が償還を確定。
このプロセスにより、契約から償還までの全てのステップが電子化され、紙の契約書や手形の保管は不要です。2008年の制度施行以降、ITを活用した電子化が加速し、2026年現在では大企業だけでなく中小企業・個人事業主にも普及が進んでいます。
安全性については、でんさいネットが暗号化通信・認証システムを採用し、二重譲渡防止や契約書との照合を行っています。結果として、債権者・債務者双方が安心して利用できる仕組みが整備されています。
ファクタリングの定義と仕組み

ファクタリングとは
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、期日前に現金化する資金調達方法です。売掛先の支払期日を待たずに現金を得られるため、資金繰りの改善や急な支払いへの対応が可能になります。
ファクタリングは融資ではなく売買契約に基づくため、バランスシート上で負債として計上されません(条件による)。また、売掛先の信用力が重視されるため、取引先の信用が高ければ、自社の財務状況が厳しくても利用できる可能性があります。
他の資金調達方法(銀行融資や手形割引)と比べ、審査期間が短く、最短即日での資金化が可能です。たとえば、建設業者が公共工事の入金まで数か月かかる場合でも、ファクタリングを活用すれば資材費や人件費の支払いを迅速に行えます。
ファクタリングの仕組み
ファクタリングの基本的な流れは以下の通りです。
- 売掛債権を保有する企業(売り手)が、ファクタリング会社に利用申込。
- 必要書類(請求書、契約書、取引先情報など)を提出。
- ファクタリング会社が取引先(買い手)の信用調査を実施。
- 契約締結後、売掛債権を譲渡。ファクタリング会社が売掛金額から手数料を差し引いた額を支払。
- 期日に取引先がファクタリング会社へ支払いを行い、取引が完了。
ファクタリングには、2社間取引(売り手とファクタリング会社のみ)と3社間取引(売り手・買い手・ファクタリング会社)があります。2社間は即日対応が可能ですが手数料は高め、3社間は手数料が低めで信用力向上につながる場合があります。
電子記録債権とファクタリングの違い

基本的な違い
電子記録債権はインターネット上でやり取りされるデジタル形式の金銭債権です。従来の紙の手形や契約書の代わりに、専用の記録機関(例:でんさいネット)の原簿に債権を記録する仕組みで、取引の効率化やコスト削減を目的としています。
一方、ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に売却し、すぐに現金化できる資金調達手段です。売掛金の入金を待たずに現金を得られるため、資金繰りの改善に直結します。
譲渡方法も異なります。電子記録債権は「記録機関への登録」によって権利が移転し、公式の記録に残ります。一方、ファクタリングは「契約書の締結と譲渡通知」で権利が移る仕組みです。つまり、電子記録債権は一連の取引をシステム上で一元管理できるのに対し、ファクタリングは必要なときに資金を確保するためのスポット的な取引が中心です。
イメージとしては、「でんさい=電子的に整理された決済の仕組み」「ファクタリング=現金化のための即席の売買契約」と言えます。
利用目的の違い
ファクタリングの主な目的は、企業が短期間で資金を確保することです。特に、支払いが先行する業種や、売掛先の信用リスクが高く回収が不安な場合に有効です。
一方、電子記録債権の目的は取引の効率化と事務負担の軽減です。紙の契約書や手形管理をなくすことで、経理部門や管理部門の作業を大幅に削減し、コストも抑えられます。
例えば、短納期で大量の資材を仕入れるために資金がすぐ必要な場合はファクタリングが適しています。逆に、長期的に多くの取引先と売掛金の管理を効率化したい場合は電子記録債権が有効です。両者の用途は明確に異なるため、自社の「今の課題」が資金調達なのか、業務効率化なのかによって選択が変わります。
電子記録債権のメリットとデメリット

電子記録債権のメリット
電子記録債権(でんさい)の最大のメリットは、資金回収のスピードと事務手続きの簡素化です。従来の紙ベースの手形では「作成→印紙を貼る→郵送→受領→保管」という一連の作業が必要でしたが、でんさいでは全てが電子的に完結します。
- 迅速な回収:郵送期間が不要となり、入金確認までが早い。
- コスト削減:印紙税が不要。さらに郵送費・紙の保管費用も削減。
- 情報管理の効率化:償還期日や残高が電子的に整理され、売掛金管理が容易。
- 安全性:紙と違い盗難や紛失リスクがなく、真正性を記録機関が保証。
実際に、優良な取引先を持つA社は、でんさいを導入したことで年間約600万円のコスト削減に成功しました。印紙税と郵送費がゼロになっただけでなく、営業担当者が「相手に手形を届ける」時間も減り、営業活動に集中できるようになったのです。
電子記録債権のデメリット
一方で、電子記録債権には以下のデメリットもあります。
- 導入コスト:システム設定費用や利用手数料がかかる。
- ITリテラシーが必要:社員が仕組みを理解していないと運用に支障。
- 利用範囲が限定的:相手先がでんさいに対応していなければ使えない。
例えば、地方のB社は取引先の半数以上がまだでんさいに対応しておらず、紙の手形と並行運用せざるを得ませんでした。結果、業務フローが一時的に複雑化し、経理部門の負担が逆に増えてしまったのです。このように、取引先の状況に左右される点は無視できない課題です。
また、中小企業では「ITシステムに不慣れ」という理由から現場に抵抗感が出ることもあります。そのため、導入時には研修やマニュアル整備が不可欠です。
どちらを選ぶべきか?選択基準

ファクタリングが向いているケース
ファクタリングは以下のような場面で特に効果的です。
- 短期間で資金が必要(例:納期前の大量仕入)
- 取引先の信用リスクが高く、回収が不安
- 売掛金の回収に時間がかかる業種(建設、製造、卸売など)
経験談①: 開業間もないE社は、銀行融資の審査に時間がかかる間、ファクタリングを利用して急場をしのぎました。結果、仕入れを止めずに済み、開業直後の受注を逃さずに済みました。
経験談②: 建設業G社は、大型工事案件を受注した際、資材費や人件費が先行して発生しました。入金は半年先だったため、2社間ファクタリングを活用。短期資金を確保し、工期を守ることができたことで元請けからの信頼が高まり、次の案件にもつながりました。
電子記録債権(でんさい)が向いているケース
でんさいは次の条件に当てはまる場合に適しています。
- 安定した取引先がいる
- 大口取引を行う(高額債権のやり取り)
- 手数料を抑えつつ事務作業を効率化したい
経験談①: 製造業F社は、全取引先の90%以上がでんさい対応だったため、紙手形から全面移行。年間で印紙税をゼロにし、郵送や管理コストを約400万円削減しました。
経験談②: 卸売業H社は、長年紙手形での取引を行っていましたが、印紙税・郵送費・保管コストの負担が大きくなっていました。でんさいを導入した結果、経理担当者の作業時間を月40時間削減。さらに、透明性の高い記録管理が評価され、銀行からの融資条件も改善されました。
ファクタリングとでんさいの利用方法
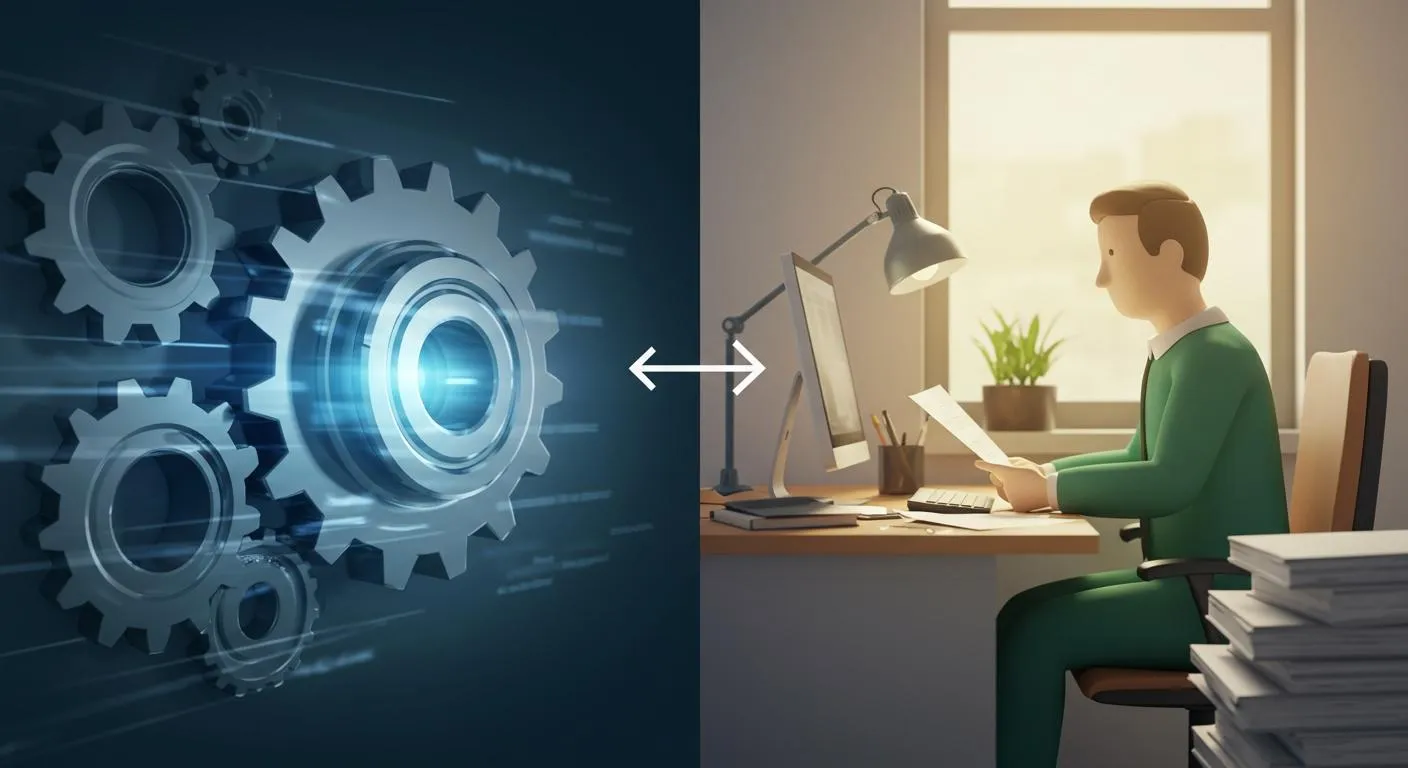
ファクタリングの利用手順
ファクタリングを安全かつ効果的に利用するためには、以下の手順を踏むことが重要です。
- 申し込み:オンラインまたは対面で申請フォームに必要事項を入力し送信。
- 必要書類の提出:請求書、契約書、取引先情報、支払い履歴など。オンライン送信も可能。
- 審査通過:ファクタリング会社が取引先の信用状況や債権内容を審査。
- 契約締結:契約内容(手数料率、支払期日、譲渡条件など)を確認し、署名または電子署名。
- 資金受け取り:最短で即日、銀行口座に振込。支払い完了後、取引先から代金がファクタリング会社へ支払われる。
信頼できる業者を選ぶ際は、設立年、実績、利用者の評判、手数料の明確さをチェックしましょう。中でも、急な資金ニーズではオンライン完結型サービスの利便性が高く評価されています。
でんさいの利用手順
でんさいを利用するには、以下のステップを踏みます。
- 利用登録:取引銀行を通じて、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)に利用者登録。
- 発生記録:契約内容に基づき、債権の発生日・金額・償還期日などを記録機関に登録。
- 譲渡・分割:必要に応じて、債権を他社へ譲渡。承諾と同時に原簿に反映。
- 償還:期日に債務者が指定口座へ入金。入金確認後、償還記録を確定。
注意点として、取引先がでんさい非対応の場合は併用が必要となることや、発生記録や譲渡の都度、記録機関への手数料が発生する点を事前に把握しておきましょう。
ファクタリングとでんさいの共通点

資金調達の迅速性
両者の共通点として、従来の融資よりも迅速に資金が確保できる点が挙げられます。ファクタリングは最短即日で現金化可能であり、でんさいは決済サイトの短縮や入金管理の効率化によって実質的な資金化スピードを向上させます。
例えば、製造業G社は、でんさいで支払サイトを従来の120日から60日に短縮し、さらに一部債権をファクタリングで現金化する「併用型」を採用。結果、運転資金の回転率を大幅に改善しました。
事務負担の軽減
もう一つの共通点は事務作業の効率化です。でんさいでは発生・譲渡・償還が電子記録で完結し、ファクタリングでは契約・審査・資金化の多くがオンライン化されています。
これにより、紙書類の管理や郵送作業が減り、事務担当者の負担が軽減。例えば、小売業H社はでんさい導入後、請求書発行から入金消込までの作業時間を40%削減しました。
ファクタリングとでんさいを利用する際の注意点

悪徳業者の見極め
特にファクタリング利用時には、悪徳業者を避けることが最重要です。以下をチェックしましょう。
- 手数料や契約条件を事前に明示しているか
- 登録番号や所在地、連絡先が明確か
- 利用者の口コミや第三者評価が良好か
過去には「手数料0%」を謳いながら実質的に高額な事務手数料を請求するケースもありました。必ず複数業者を比較し、契約書の細部まで確認することが重要です。
取引先の状況確認
でんさい・ファクタリングいずれの場合も、取引先の信用状況を把握することが不可欠です。過去の支払履歴や財務状況を確認し、支払能力に問題がないかを調べましょう。
例えば、建設業I社は、取引先の信用情報を事前に調査し、回収不能リスクを持つ案件を早期に回避。結果として、年間の貸倒損失をゼロに抑えることができました。
ファクタリングとでんさいの将来性

市場の動向
日本のファクタリング市場は、2020年代に入り年平均成長率(CAGR)で6〜8%程度の拡大を続けています。背景には、企業の資金繰り多様化ニーズの高まり、銀行融資枠の逼迫、そしてデジタル化による取引スピードの向上があります。一方、電子記録債権(でんさい)は、2026年の約束手形全面廃止に向けて普及が加速。全銀電子債権ネットワークの統計によると、発生記録件数は年々増加傾向にあります。
競合他社の動向として、クラウド会計や請求書発行サービスと連携したファクタリングや、ERPシステムとAPI連携するでんさいサービスが台頭。これにより、中小企業でも導入障壁が下がり、市場全体が拡大フェーズに入っています。
顧客ニーズは、単なる資金調達から「資金繰り・与信・請求・回収の一体管理」へとシフトしており、今後はワンストップ型プラットフォームが主流になる可能性が高いです。
テクノロジーの進化と影響
ファクタリングとでんさいの双方において、テクノロジーが大きな役割を果たし始めています。
- ブロックチェーン:債権譲渡や償還の記録を改ざん不可能な形で保管し、二重譲渡や不正取引を防止。
- AI審査:従来は数日かかっていた与信審査を、AIスコアリングによって数分〜数時間に短縮。
- デジタルプラットフォーム統合:会計・請求・入金消込・与信管理を一元化し、資金繰り可視化を実現。
2026年現在、一部の大手ファクタリング会社では、売掛先の過去3年分の支払傾向や財務データをAIが自動分析し、最適な手数料率を即時提示するシステムが稼働しています。また、でんさいにおいても、スマホアプリから発生記録や譲渡が可能なモバイル対応が進んでおり、外出先や現場からでも債権管理が可能となっています。
まとめと今後の展望

ファクタリングとでんさいの選択肢
ここまで解説してきた通り、ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は、目的・仕組み・導入効果が大きく異なります。
- ファクタリング:短期資金調達に強く、与信リスクを軽減できるが、手数料負担がある。
- 電子記録債権(でんさい):取引効率化やコスト削減に有効だが、取引先の対応状況が普及のカギ。
両者のメリット・デメリットを比較し、自社のニーズに合った方法を選ぶことが重要です。また、場合によっては併用が最適解になることもあります。
自社に合った資金調達方法の検討
資金調達手段を選定する際は、以下の観点を考慮しましょう。
- 目的:運転資金の補填か、取引効率化か。
- 費用:手数料、導入コスト、隠れコストの有無。
- スピード:必要な資金がいつまでに必要か。
- リスク:取引先の信用リスク、制度改正の影響。
例えば、資金繰りが逼迫している中小企業は、短期的にはファクタリングで即時資金を確保し、中長期的にはでんさいを導入して事務効率化とコスト削減を図る戦略が有効です。
また、銀行融資・クラウドファンディング・リース契約など、他の調達手段と比較することで、よりバランスの取れた資金戦略を構築できます。
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する