
中小企業の経営者の皆様、IT投資は業務効率化や経営革新に不可欠ですが、資金調達でお悩みではありませんか?日本政策金融公庫の「IT活用促進資金」は、中小企業のIT化を強力に後押しする融資制度です。本記事では、制度の概要から融資条件、申込方法、活用事例までを網羅的に解説します。
IT活用促進資金とは?制度の概要を理解する

IT活用促進資金は、中小企業がITを活用して業務効率化や経営革新を図るための資金を融資する制度です。変化の激しい事業環境に対応するため、IT導入を検討している企業にとって、有効な選択肢となるでしょう。中小企業の競争力強化を目的としており、業務効率化や高度化、経営革新を促進します。
どんな企業が対象?利用対象者をチェック
この制度を利用できるのは、ITを活用した業務効率化を目指す事業者や、ネットワーク上での取引を行う事業者などです。具体的には、以下の事業者が対象となります。
- ITを活用した業務効率化や高度化を目指す事業者
- ネットワーク上での取引や情報発信を行う事業者
- 企業内外のITレベルを標準化しようとする事業者
- IT活用による経営革新を図る事業者
- 中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた情報処理支援機関
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給または導入計画の認定を受けた事業者
- テレワークの導入等を行う事業者
資金の使い道は?対象となる設備と用途
IT活用促進資金は、設備資金と長期運転資金として利用可能です。
- 設備資金:電子計算機(ソフトウェアを含む)、周辺装置、端末装置、被制御設備、関連設備、関連建物・構築物などに利用できます。コンピュータ本体だけでなく、周辺機器やソフトウェア、関連設備など、IT投資に必要な幅広い費用に利用できます。テレワーク導入のための設備投資にも活用可能です。
- 長期運転資金:ソフトウェアの取得、制作、運用に必要な資金や、建物更新に伴う一時的な施設賃借費用などに利用できます。
融資条件の詳細:金融業界向け徹底解説

IT活用促進資金の融資条件について、金融業界の読者に向けて詳細を解説します。中小企業のIT投資を支援する本制度を例に、融資条件のポイントを絞ってご紹介します。
融資限度額:最大いくらまで借りられる?
IT活用促進資金では、直接貸付と代理貸付で融資限度額が異なります。直接貸付の場合、最大7億2千万円まで、代理貸付の場合は1億2千万円まで融資可能です。運転資金としての利用も可能ですが、限度額が設定されている場合があります。事業計画に合わせて必要な金額を確認しましょう。
利率:金利はどれくらい?特別利率の適用条件
金利は基準利率と特別利率の2種類があります。特別利率は、一定の要件を満たす場合に適用されます。要件は、事業内容や地域によって異なるため、詳細はお問い合わせください。金利タイプを確認し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
返済期間:無理のない返済計画を立てるために
設備資金と運転資金で返済期間が異なります。設備資金は最長20年以内(据置期間2年以内)、運転資金は最長7年以内(据置期間2年以内)です。据置期間を活用することで、事業開始直後の負担を軽減できます。返済計画を綿密に立て、資金繰りを安定させましょう。
担保・保証人:必要となるケースとは?
担保や保証人の必要性は、融資の種類や金額、事業の状況によって異なります。直接貸付の場合、経営責任者の個人保証が必要となるケースもあります。担保の有無や種類は、金融機関との相談の上で決定されます。
IT活用促進資金 申込方法と必要書類

直接貸付と代理貸付:どちらを選ぶ?
IT活用促進資金は、中小企業のIT投資を支援する制度です。融資の申込窓口は、直接貸付と代理貸付の2種類があります。直接貸付は各支店の中小企業事業窓口で、融資限度額は7億2千万円です。一方、代理貸付は中小企業事業の代理店窓口で、融資限度額は1億2千万円です。事業規模や必要金額に合わせて選択しましょう。
必要書類:事前に準備しておきたいもの
申込には、確定申告書、決算書、試算表、見積書などの書類が必要です。これらは事業の現状とIT投資計画を審査するために用いられます。事前に準備しておくことで、スムーズな手続きが可能です。会員登録をすると、創業計画の作成機能も利用できます。
IT活用促進資金 活用事例:成功へのヒント

中小企業の皆様、IT活用による事業成長を支援する「IT活用促進資金」をご存知でしょうか? この制度は、業務効率化、顧客管理強化、テレワーク導入など、ITを活用した経営革新を目指す中小企業を対象に、低金利で資金調達を可能にするものです。
業務効率化:RPA導入によるコスト削減
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入により、定型業務を自動化し、大幅なコスト削減を実現した企業があります。従業員はより創造的な業務に集中できるようになり、生産性向上に繋がっています。
顧客管理の強化:CRM導入による売上向上
CRM(顧客関係管理)システム導入で顧客データを一元管理し、顧客ニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供することで、売上向上に成功した企業もあります。顧客満足度向上にも貢献しています。
テレワーク導入:働き方改革と生産性向上
テレワーク導入を支援し、従業員の柔軟な働き方を実現した企業では、従業員満足度が向上し、優秀な人材の確保にも繋がっています。通勤時間の削減による生産性向上も期待できます。
IT活用促進資金を活用し、御社のビジネスをさらに加速させませんか? 詳しくは、お近くの金融機関または中小企業支援機関にお問い合わせください。
他の融資制度との比較:自社に最適な資金調達方法を見つける
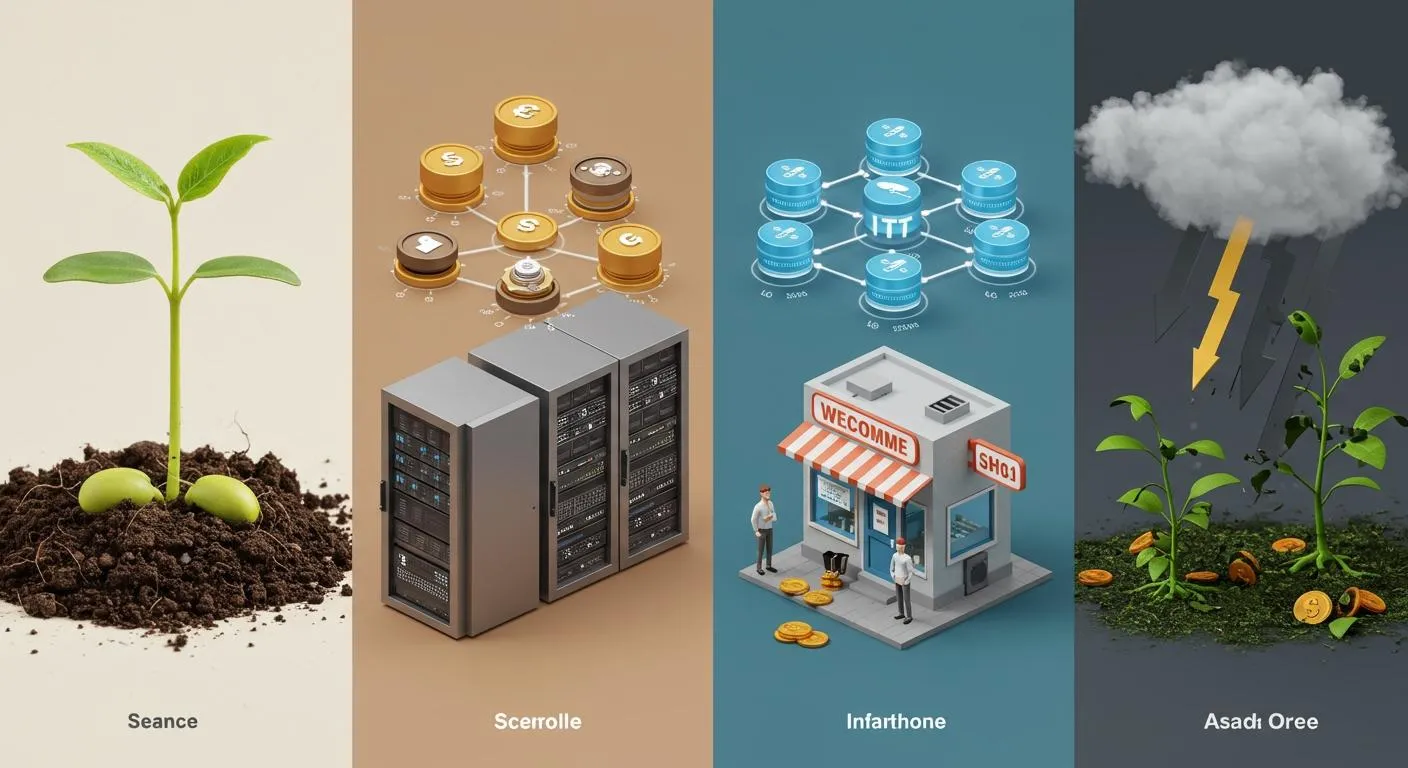
IT活用促進資金は、中小企業のIT投資を支援する制度ですが、他にも様々な融資制度が存在します。自社にとって最適な資金調達方法を見つけるためには、これらの違いを理解することが重要です。
新規開業資金:創業時の資金調達
新規開業資金は、新たに事業を始める際に利用できる融資制度です。IT活用促進資金は、既に事業を行っている企業がIT投資を行う際に利用できる点が異なります。創業時の資金調達であれば新規開業資金、事業拡大のためのIT投資であればIT活用促進資金が適しています。
マル経融資:小規模事業者向けの融資
マル経融資は、小規模事業者向けの経営改善資金です。IT活用促進資金も小規模事業者が利用できますが、IT投資に限定されている点が異なります。マル経融資は、運転資金など幅広い用途に利用できます。事業内容や資金用途に合わせて選択しましょう。
新型コロナウイルス感染症特別貸付:緊急時の資金調達
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、コロナ禍で経営が悪化した企業向けの緊急融資でした。既に受付は終了していますが、IT活用促進資金は、コロナ禍に関わらず、IT投資による事業成長を目指す企業を支援する制度です。
まとめ:IT活用促進資金で未来を拓く

中小企業の情報化投資を支援する「IT活用促進資金」。この制度は、業務効率化や高度化、ネットワーク取引の拡大、テレワーク導入など、IT活用を目指す中小企業を力強くサポートします。
金利や融資限度額、返済期間などの条件は、事業規模や資金用途によって異なります。まずは日本政策金融公庫に相談し、自社の状況に合った活用方法を検討しましょう。IT活用促進資金を積極的に活用し、事業の成長と発展を目指しましょう。この制度を有効活用し、競争力強化と持続的な成長を実現してください。
外部リンク
- 日本政策金融公庫「IT活用促進資金」公式ページ
- 創業融資支援センター|IT活用促進資金の制度解説
- 創業手帳|IT活用促進資金の最新情報(2025年7月)
- 弥生 資金調達ナビ|IT活用促進資金の概要・条件まとめ
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




