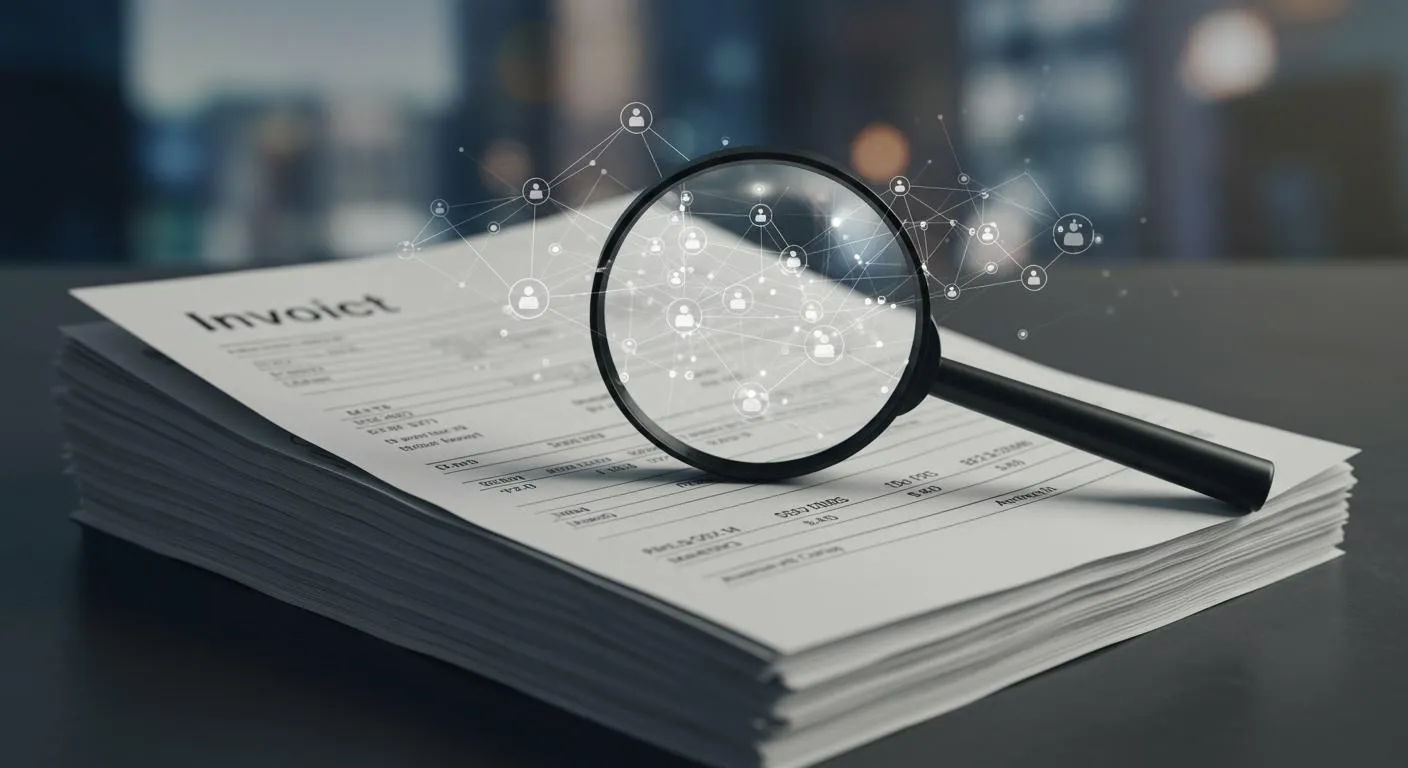ファクタリングは、中小企業から上場企業まで幅広く利用される資金調達手段の一つです。売掛金を早期に現金化することで資金繰りを改善できるメリットがありますが、同時に「ファクタリング取引に消費税はかかるのか?」という疑問を持つ経営者や経理担当者は少なくありません。実際、ファクタリング手数料は消費税法上「非課税」とされており、売掛債権の譲渡そのものも課税対象外です。しかし、契約内容や付随費用の扱いによっては課税仕入れが発生するケースもあるため、正確な理解が不可欠です。
本記事では、ファクタリングの基本から種類ごとの特徴、消費税の仕組み、非課税となる理由、課税が発生する場面、契約書における注意点まで体系的に解説します。さらに、筆者が現場で接してきた実務トラブル事例や成功ケースを交え、初心者でも理解しやすい形でまとめました。2026年の最新制度や市場動向も反映しているため、今後ファクタリングを導入・利用する企業にとって実践的な指針となるでしょう。
関連記事
ファクタリングの基本を理解しよう

ファクタリングとは何か
ファクタリングとは、企業が持つ売掛金をファクタリング会社に譲渡し、手数料を差し引いた金額を早期に現金化する資金調達の方法です。銀行融資のように審査に長期間を要することなく、比較的短期間で資金を確保できる点が特徴です。特に中小企業や個人事業主にとっては、急な資金ニーズに対応できる有効な手段といえます。
この仕組みの目的は大きく二つあります。第一に、企業のキャッシュフロー改善です。取引先からの入金を待たずに現金化できることで、仕入れや人件費などの支払いに余裕を持たせられます。第二に、信用リスクの軽減です。売掛金をファクタリング会社に譲渡することで、万が一取引先が倒産しても、売掛金未回収のリスクを回避できるケースがあります。
例えば、ある製造業の株式会社では、主要取引先の支払サイトが長く、資金繰りに困窮していました。そこでファクタリングを導入し、売掛金を早期に現金化した結果、仕入代金の支払いを滞りなく行えるようになり、取引関係の安定につながりました。このように、ファクタリングは「資金調達の補助線」として機能するのです。
ファクタリングの種類と特徴
ファクタリングには複数の種類が存在し、それぞれに特徴と利用シーンがあります。代表的なのは以下の通りです。
- リコースファクタリング:売掛先が倒産した場合、利用企業が債務を負担する方式。手数料は安い傾向がありますが、リスクは利用企業側に残ります。
- ノンリコースファクタリング:売掛先が倒産しても利用企業に遡及請求されない方式。リスクはファクタリング会社が引き受けるため、手数料は高めです。
- 国内ファクタリング:日本国内の取引に用いられる一般的な形式。中小企業や個人事業主の利用が多いです。
- 国際ファクタリング:海外企業との取引で利用される形態。異なる法制度や通貨リスクに対応するため、輸出入ビジネスに適しています。
- 2社間ファクタリング:利用企業とファクタリング会社の2者のみで行う方式。取引先に通知せず秘密裏に資金調達できる一方、ファクタリング会社のリスクが大きいため手数料は高めです。
- 3社間ファクタリング:利用企業・ファクタリング会社・売掛先の3者間で行う方式。売掛先からファクタリング会社へ直接入金される仕組みで、透明性が高く手数料も低めですが、取引先に知られるデメリットがあります。
利用目的や状況に応じて選び方は異なります。例えば、国内取引で短期的に資金を調達したい場合は「国内リコースファクタリング」や「2社間ファクタリング」が効率的です。一方で、海外取引で回収リスクを徹底的に避けたい場合は「国際ノンリコースファクタリング」や「3社間ファクタリング」が適しています。
このように、ファクタリングは事業規模・業種・取引環境によって最適な方法が変わるため、自社に合った種類を選ぶことが成功の鍵となります。
消費税の基礎知識

消費税の概要と目的
消費税とは、日本国内における消費活動全般に発生する税金であり、最終的には消費者が負担する仕組みです。企業は取引ごとに消費税を発生させ、これを一時的に預かり、国や地方に納付する役割を担っています。
日本で消費税が導入された背景には、安定的な税収の確保と社会保障費用の増加があります。少子高齢化が進む国内では、国民の生活や医療、福祉を支えるために安定した財源が必要とされ、その一環として消費税が採用されました。
また、消費税は特定の企業や個人に偏らず、広く公平に負担が行き渡る税制である点も特徴です。事務処理にかかるコストや手続きの負担はありますが、国内の経済活動全体を下支えする目的で設計されており、企業の経理担当者にとっても理解しておくべき重要な制度といえます。
課税対象となる取引の条件
消費税の対象となる取引は、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 国内取引であること(国外で行われる取引は対象外)
- 事業者が行う取引であること(個人的な売買は対象外)
- 対価を得て行う取引であること(無償提供は対象外)
- 資産の譲渡や役務の提供に該当すること(有価証券の売買などは対象外)
例えば、商品の販売やサービスの提供は消費税の課税対象となりますが、有価証券や土地の売買など一部は非課税取引に該当します。この区別を誤ると、取引先との請求や経理処理で混乱が生じる可能性があります。
また、課税の仕組みは「売上にかかる消費税額 − 仕入や経費にかかる消費税額」という計算方式を採用しています。つまり、企業は単に税金を支払う存在ではなく、消費税を一時的に預かり、税務署へ納付する役割を果たすのです。
採用情報や会社案内にも登場するほど、消費税は国内の企業活動に密接に関係しています。そのため、経営者や経理担当者は課税対象と非課税の違いを正確に把握し、契約や会計処理で混乱しないよう準備することが大切です。
ファクタリング取引における消費税の扱い

ファクタリング手数料は非課税
結論からいうと、ファクタリングの「手数料」や「割引」は原則として非課税です。理由は、これらが金銭債権(売掛金)の譲受対価の一部として位置づけられるためで、一般の課税取引(商品販売や役務の提供)とは性質が異なるからです。したがって、法人・個人事業主のいずれが利用しても、通常は手数料に消費税を「上乗せして支払い」する必要はありません(免税というより非課税の区分である点に注意)。
イメージしやすいように、現金化の流れと金額でかみ砕いてみます。
例:売掛金1,000万円を2社間で買取、割引率3%、送金手数料は実費
- 売掛金(譲渡対象)… 10,000,000円
- 割引(手数料、譲受対価の控除)… 300,000円 ←原則非課税
- 振込実費(銀行手数料など)… 880円程度 ←金融機関の手数料は課税/非課税が混在、明細で要確認
- 入金額(現金) … 9,699,120円(=10,000,000 − 300,000 − 880)
この取引で、割引300,000円に消費税は通常かかりません。明細書に消費税が上乗せ記載されていないかを確認しましょう。
なお、「非課税」≠「すべての周辺費用が非課税」という点は重要です。ファクタリングに付随して発生する、報酬や役務が独立して提供される場合(例:債権のデューディリジェンス、回収代行などのサービス)は、一般の役務提供として課税されることがあります。ケースごとに取引の中身が異なりますから、明細の書き方・契約の書き方次第で区分が変わる点に注意が必要です。
- 原則非課税になりやすい明細:割引、ファクタリング手数料(譲受対価として一体)、遅延控除等
- 課税になりやすい明細:調査料・与信審査レポート費・回収代行料など独立の役務、システム利用料、コンサル報酬 など
この整理は、個人事業主でも法人でも基本は同じです。「保険」のように見える文言が付いていても、実質が譲受対価か独立役務かで区分は変わります。原則は非課税だが、明細次第で課税が混じることは十分ありえる—と覚えておくと実務で迷いにくくなります。
- 請求書の「手数料」に消費税が上乗せされていないか(原則は非課税)。
- 「調査料」「回収料」など独立役務があれば課税計上でよいか。
- 契約では、「手数料=譲受対価(非課税)」か「役務(課税)」かを文言で明瞭に。
売掛債権譲渡の非課税理由
売掛債権の譲渡(売却)自体が非課税とされるのは、金銭債権という「お金に関する権利」の取引であり、通常の「商品販売」や「役務の提供」とは課税の性質が違うためです。消費税は原則として「資産の譲渡」や「役務の提供」に課税されますが、金銭債権の譲渡は非課税の代表例にあたります(「土地」の売買が非課税なのと同じく、消費に馴染まない取引という整理)。
実務では、次の3点を押さえると安全です。
- 契約書・明細の一貫性:明細の「譲渡対価(割引)」と「独立役務(課税)」の線引きを、契約書・請求書・入金明細で同じ表現にする。
- 二重譲渡の回避:売掛金の二重譲渡を防ぐため、債権譲渡登記や債務者(取引先)への通知・承諾の運用をあらかじめ設計(3社間では通知が基本)。
- 登録免許税・印紙などの周辺コスト:登録免許税は税目が異なり、消費税計算とは別の扱い。契約書の印紙税は記載金額・区分記載の有無で変わるため、消費税の課否とは切り離してチェック。
Q&A(現場でよく出る質問)
- Q:売掛金を譲渡したら「売上」はどうなりますか?
- Q:譲渡の対価(割引)に消費税は?
- Q:債権譲渡登記って必須?費用は?
A:売上(販売)自体は従来どおり商品・役務の提供時点で計上。ファクタリングは売上債権の資金化手段であり、売上そのものの増減ではありません。
A:非課税です(譲受対価として一体)。ただし、債権調査など独立の役務は課税になることがあるため、明細の分け方に注意。
A:二重譲渡リスク回避や優先関係の明確化に有効。費用には登録免許税のほか、司法書士への報酬(課税)が発生し得ます(登記の必要性はスキーム・金額によります)。
用語の整理としては、譲渡の対象は売掛(売掛金)という金銭債権であり、土地のような非課税資産と同様、消費税の「課税対象」からは外れる、という理由付けです。会計処理では、売掛金の減少と入金(現金)の増加、差額の割引(ファクタリング費用)で整合を取ります。
消費税がかかる場合とは?

特定の手数料に対する消費税
ファクタリングの取引は原則「非課税」とされますが、すべての費用が非課税になるわけではありません。特定の手数料については消費税の課税対象となるケースがあるため注意が必要です。
代表的に課税となる可能性があるのは、以下のような費用です。
- 契約書作成費や事務手続き料:事務代行や役務提供としての性質を持つため課税。
- 与信調査料や審査報酬:売掛先の信用調査を独立したサービスとして実施する場合は課税。
- 回収代行料:債権譲渡とは別に、債権回収サービスを提供している場合は課税。
つまり、「売掛債権の譲渡対価」=非課税ですが、「独立したサービス提供」=課税という整理です。
例:手数料に消費税が発生するケース
- 調査報酬:50,000円 → 課税対象(消費税10%=5,000円)
- 契約書事務手数料:10,000円 → 課税対象(消費税10%=1,000円)
- 割引料(譲受対価):200,000円 → 非課税
この場合、請求書には「課税対象の手数料」と「非課税の割引料」を明確に区分して記載する必要があります。
消費税の計算方法は「課税対象となる手数料 × 消費税率」というシンプルなものです。ただし、1万円未満の少額領収書の場合、2029年9月まではインボイス保存の特例が認められているため、実務ではこの特例を活用できるかどうかもチェックしましょう。
債権譲渡登記に関する費用
ファクタリングで大口の取引を行う場合、債権譲渡登記を行うケースがあります。これは、二重譲渡を防ぐために不可欠であり、取引の安全性を高める重要な手続きです。
債権譲渡登記に関連する主な費用は以下の通りです。
- 登録免許税:国に納める税金で、債権金額に応じて算定されます(例:金銭債権1件につき7,500円など)。これは消費税の対象外です。
- 司法書士報酬:登記を代行する司法書士に支払う報酬は課税対象(消費税10%)となります。
- 契約書印紙代:印紙税法に基づくもので、こちらも消費税の対象外です。
例:債権譲渡登記費用の内訳(1件あたり)
- 登録免許税:7,500円(非課税)
- 司法書士報酬:30,000円+消費税3,000円(課税)
- 契約書印紙:4,000円(非課税)
合計:44,500円(うち課税対象は司法書士報酬部分のみ)
このように、登記関連費用の中には課税されるものと非課税のものが混在しています。そのため、契約書・請求書に「区分記載」を行い、課税・非課税を明確に整理することが大切です。
特に、契約書や契約金額に「消費税を含む」と記載してしまうと印紙税の計算額が増える可能性があるため注意が必要です。ここは契約実務と税務の接点であり、経理担当者にとっては見逃せないポイントです。
ファクタリング業者との取引における注意点

悪徳業者に騙されないために
ファクタリングは便利な資金調達手段ですが、すべての業者が健全とは限りません。残念ながら、一部には高額な手数料を要求したり、不当な契約条件を押し付ける悪徳業者も存在します。そのため、取引を始める前に信頼できる事業者を選ぶことが非常に重要です。
まず確認すべきは業者の実績と信頼性です。金融庁や各種業界団体の情報を参考に、過去の運営実績や顧客の声を調べましょう。また、契約書の内容を丁寧に確認し、特に手数料の算定方法・契約期間・解約条件について不明点があれば必ず質問してください。
さらに、実際に利用した企業の口コミや評判を確認することも有効です。ネット上のレビューや同業者からの紹介は、信頼性を判断する重要な材料となります。短期間で資金が必要だからと焦らず、複数の業者を比較・検討してから契約することをおすすめします。
- 手数料が「相場」に比べて極端に高くないか
- 契約書に不利な条項(途中解約不可など)が含まれていないか
- 会社の所在地や連絡先が明確に示されているか
- 口コミ・評判にトラブル事例が多くないか
消費税請求時の対処法
ファクタリングの取引では、原則として手数料や割引料は非課税ですが、まれに課税対象外のはずの費用に消費税が上乗せされて請求されるケースがあります。このような場合、請求書の正確性を必ず確認することが必要です。
請求内容に疑問があれば、まず業者へ確認し、適切に修正を求めましょう。それでも解決しない場合は、国税庁や税務署へ相談することで、公的なアドバイスや是正指導を受けることができます。
また、請求書の記載内容と実際の契約内容に齟齬がないかをチェックすることも大切です。請求書には「課税」「非課税」の区分を明確に記載し、万一税務調査が入った場合でも説明できる状態を整えておきましょう。
トラブル事例:ある小規模事業者は、ファクタリング業者から「手数料+消費税10%」という請求を受けました。しかし実際には手数料は非課税取引であるため、誤って多くの金額を支払ってしまったのです。税務署に相談した結果、業者側の請求ミスが判明し、後日返金対応を受けることになりました。
このように、請求書の消費税計算は誤りやすいポイントです。疑問があれば遠慮せず確認する姿勢が、後のトラブル回避につながります。
ファクタリングの消費税に関するメリットとデメリット

ファクタリング利用における消費税のメリット
ファクタリングの最大の特徴は、手数料や割引料が非課税として扱われる点です。これにより、企業は以下のようなメリットを享受できます。
- 資金調達コストを抑えられる:通常の金融取引であれば手数料に消費税が加算されますが、ファクタリングの割引料は非課税のため、余計な税負担が発生しません。
- キャッシュフローのシンプル化:消費税額の計算や仕訳処理で複雑な調整が不要となり、経理実務が効率化されます。
- 免税事業者にも有利:インボイス制度の導入後、免税事業者が課税事業者となるケースが増えていますが、ファクタリング手数料は非課税なので、新規課税事業者にとっても大きな負担増にはつながりにくい点が魅力です。
- 業界共通のルール:非課税という扱いは消費税法に基づくものであり、どのファクタリング会社を利用しても基本的に一貫した処理が可能です。
経験談:小売業を営むA社は、資金繰りの改善のためにファクタリングを利用しました。割引料が非課税だったことで、想定よりも資金流出が少なく済み、「税負担を考えると融資より有利だった」と経理担当者は語っています。
ファクタリング利用における消費税のデメリット
一方で、ファクタリングの取引には消費税の課税対象となる費用も存在するため、次のようなデメリットや注意点があります。
- 付随費用は課税される:債権譲渡登記の司法書士報酬や、独立した与信調査費用、回収代行料などは課税取引となるため、消費税が上乗せされます。
- 仕入税額控除の影響:ファクタリングの対価は非課税売上となるため、課税売上割合が下がり、仕入税額控除の計算に影響する場合があります。
- 契約書の記載ミスによるトラブル:非課税のはずの手数料に「消費税別途」と記載され、不要な消費税を支払ってしまうトラブルが発生するケースがあります。
- 税務署対応の手間:万が一、課税/非課税の区分で解釈が分かれる明細があると、税務調査時に説明や修正が必要になるリスクがあります。
実例:建設業のB社は、ファクタリング契約に「事務手数料+消費税」と記載があり、本来非課税であるべき金額に税を支払ってしまいました。税務署に相談したところ、契約書の表現が不適切だったことが判明し、業者側に修正を依頼することで解決しました。
まとめ
ファクタリングにおける最大のメリットは「手数料が非課税」である点ですが、デメリットとしては「付随費用は課税」「仕入税額控除に影響」という二つが大きなポイントです。消費税の観点を理解したうえでファクタリングを利用すれば、資金調達のコストを最小化しつつ、税務リスクを回避することができます。
ファクタリングを利用する際の会計処理

仕訳の基本
ファクタリングを利用した場合の会計処理は、基本的には「売掛金の減少」と「現金または預金の増加」を記録するシンプルな流れです。融資と異なり、借入金の計上は行いません。なぜなら、ファクタリングは融資ではなく「売掛債権の売却」にあたるからです。
たとえば、売掛金1,000,000円をファクタリングにより950,000円で現金化した場合の仕訳は次のようになります。
(借方)現金 950,000円 /(貸方)売掛金 1,000,000円 (借方)ファクタリング費用 50,000円
このように、売掛金を減少させ、受け取った現金を計上し、差額を「ファクタリング費用」として処理します。
「ファクタリング費用」という勘定科目を使わず、「支払手数料」や「雑費」に含める企業もありますが、財務の透明性を高めるために独立した勘定科目を設定するのが望ましいでしょう。
消費税に関する仕訳の注意点
ここで重要になるのが消費税の扱いです。原則として、ファクタリングの割引料や手数料は非課税取引に該当します。そのため、仕訳を行う際に消費税区分は「対象外」として処理する必要があります。
ただし、以下のような課税対象となる費用が含まれている場合には注意が必要です。
- 司法書士報酬:債権譲渡登記を依頼した場合は課税対象(10%)。
- 調査料・与信審査料:独立したサービス提供として課税。
- 回収代行手数料:債権管理・回収業務が独立役務となる場合は課税。
これらの費用は課税仕入れとして処理し、仕入税額控除の対象になります。一方、ファクタリング割引料は非課税のため、課税仕入れに含めてはいけません。
例:司法書士報酬を含む場合の仕訳
(借方)現金 950,000円 /(貸方)売掛金 1,000,000円 (借方)ファクタリング費用 50,000円(非課税) (借方)司法書士報酬 30,000円(課税) (借方)仮払消費税等 3,000円
この例では、司法書士報酬30,000円に対して消費税3,000円が課税されるため、仕訳で明確に区分する必要があります。
まとめると、ファクタリング利用時の会計処理はシンプルですが、「非課税部分」と「課税部分」を正しく分けることが重要です。特にインボイス制度導入後は、課税仕入れに該当する費用について適格請求書を保存しなければ、仕入税額控除が認められない点に注意してください。
ファクタリングの利用を検討するタイミング

資金繰りが厳しいとき
企業がファクタリングを検討する代表的なタイミングは、資金繰りが厳しくなったときです。売掛金の入金期日と仕入や人件費などの支払期日のズレが大きい場合、資金が一時的に不足することがあります。このような場面でファクタリングを活用することで、未回収の売掛金を即座に現金化でき、企業の資金繰りに大きな余裕をもたらします。
例えば、取引先からの入金が60日後に予定されている一方、仕入代金の支払いが30日後に迫っているとしましょう。この場合、銀行融資の審査では間に合わない可能性がありますが、ファクタリングを利用すれば、短期間で資金を調達でき、支払い遅延や取引停止といったリスクを防ぐことができます。
また、倒産リスクを意識している企業にとっても有効です。売掛先が突然経営不振に陥った場合でも、ファクタリングを活用すれば未回収リスクを軽減できる可能性があります。特にノンリコース型を選べば、売掛先の倒産リスクをファクタリング会社が引き受けてくれるため、経営の安定につながります。
迅速な資金調達が必要なとき
ファクタリングはスピード重視の資金調達手段としても有効です。銀行融資の場合、申請から実行まで数週間かかることがありますが、ファクタリングは最短で即日入金に対応する業者もあり、急な資金ニーズに応えることができます。
たとえば、急な大口注文を受けて仕入や外注費用が発生した場合、あるいは税金や社会保険料の納付期限が迫っている場合、ファクタリングを利用すれば短期間で必要な資金を確保できます。これは特に中小企業や個人事業主にとって、事業継続のための大きな安心材料となります。
ただし、契約内容の確認は不可欠です。手数料の設定、契約解除の条件、入金までの所要日数などを事前に理解しておくことで、思わぬコスト増やトラブルを避けられます。また、2社間か3社間かによっても資金化までのスピードや手数料が異なるため、自社の状況に合った方式を選ぶことが重要です。
- 資金繰りが逼迫しており、入金まで待てないとき
- 倒産リスクの高い取引先を抱えているとき
- 急な支払い(税金・仕入・人件費など)が発生したとき
- 短期間で大口の資金を用意する必要があるとき
ファクタリングは、常に利用するものではなく、ピンポイントで必要なときに使う資金調達手段です。適切なタイミングを見極めて利用すれば、資金繰りの安定やリスク回避に大きく役立ちます。
まとめと今後の展望

ファクタリングの重要性
ファクタリングは、単なる資金調達手段にとどまらず、企業の資金繰りを安定化させるための仕組みとして重要な役割を担っています。売掛金を早期に現金化することで、仕入や人件費などの支払いに余裕を持たせることができ、取引先への信頼性を高める効果もあります。また、万が一の売掛先の倒産リスクを回避するという意味でも、リスクヘッジの有効な手段となります。
さらに、ファクタリングの消費税の非課税性は、資金調達コストを抑えるうえで大きなメリットです。多くの金融取引が課税対象となるなかで、ファクタリングは消費税を支払う必要がないため、利用企業にとって実質的なコスト負担を軽減できるのです。
ただし、契約書の記載や登記費用、司法書士報酬など一部の付随費用は課税対象となる場合があります。経営者や経理担当者は、「非課税」「課税」「不課税」の違いを理解し、契約や仕訳で誤りのない処理を行うことが求められます。
今後のファクタリング市場の動向
2026年現在、ファクタリング市場は大きな変革期にあります。特に注目すべきはデジタル化の進展です。オンライン完結型のサービスが普及し、申込から入金までが従来よりも格段に迅速になっています。これにより、中小企業や個人事業主でも気軽に利用できる環境が整いつつあります。
また、業者間の競争激化も進んでいます。これまで不透明だった手数料体系も、比較サイトや口コミ情報の拡充によって明確化が進み、企業はより透明性の高いサービスを選べるようになっています。その一方で、依然として悪質業者の存在は懸念されるため、利用者は引き続き業者選びに慎重である必要があります。
さらに、規制や税制の変化も市場に大きな影響を与える可能性があります。インボイス制度の定着や今後の消費税率の改正によって、取引のルールや会計処理のあり方が変化する可能性があり、企業はこれに対応できる体制を整えておく必要があります。
- デジタル化:オンライン完結・即日入金のサービスが一般化
- 競争の激化:手数料透明化、サービス品質向上の流れ
- 規制・税制の変化:インボイス制度や消費税改正に対応する必要性
まとめると、ファクタリングは今後ますます利用しやすく、透明性の高いサービスへと進化していくと考えられます。そのなかで、消費税の扱いに関する理解は、資金調達コストや税務リスクを左右する重要な要素です。経営者や経理担当者は、制度の最新動向を常にウォッチし、適切に活用することで、事業運営をより強固なものにできるでしょう。
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する