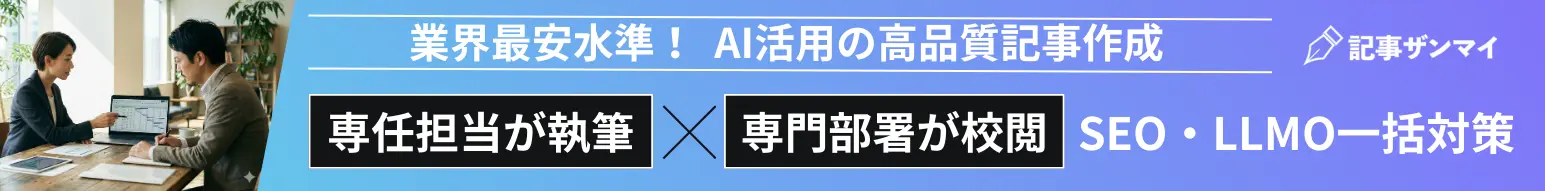キャリアアップ助成金「賞与・退職金制度導入コース」は、これまで賞与や退職金制度がなかった非正規雇用の従業員にも、安定した処遇改善を図るために設けられた支援策です。パート・アルバイト・契約社員など、幅広いスタッフへの制度導入を後押しし、企業の定着率アップや人材確保にもつながる本コース。2025年度の最新要件・申請手順から、実際に制度を活用した企業の体験談・現場で注意すべきポイントまで、専門的かつ分かりやすく解説します。今後、社内制度を見直したい経営者・人事担当者の方にこそ、知っておきたい実践的な情報を網羅します。
キャリアアップ助成金の各コースについて、以下からご覧いただけます。
- 正社員化・処遇改善で最大80万円!キャリアアップ助成金の全コース【令和7年版】
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「正社員化コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「賃金規定等共通化コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「障害者正社員化コース」
第1章 賞与・退職金制度導入コースとは ― 概要と他コースとの違い

キャリアアップ助成金「賞与・退職金制度導入コース」は、パート・アルバイト・契約社員など非正規雇用者に対して「賞与」や「退職金」などの福利厚生制度を新たに整備・導入したい事業主を支援するコースです。今まで正社員だけが対象だったボーナスや退職金も、全員が安定した処遇を得られる会社づくりを後押しする目的で設けられています。
- 長期的に働く非正規スタッフにも「年2回の賞与」や「勤続〇年以上で退職金支給」といった仕組みを作りたい
- パート・アルバイトにも「働きがい」を感じてほしい
- 人材の採用・定着を強化したい
このコースは「制度を作るだけ」でなく、実際に賞与や退職金を支給した実績が要件となります。なお、賃金規定等改定コースや賃金規定等共通化コースと主旨や対象内容が大きく異なるため、次のリスト・表で違いを整理します。
- 賞与・退職金制度導入コース… 非正規雇用者向けの賞与・退職金制度の新設・実際の支給が対象。
- 賃金規定等改定コース… 非正規雇用者の基本給や昇給ルールの改定・賃金アップの仕組み作りが対象。
- 賃金規定等共通化コース… 正規・非正規間の賃金体系や昇給ルールの共通化、待遇格差解消のための制度作りが対象。
| コース名 | 助成の対象 | 主な要件 | イメージ例 |
|---|---|---|---|
| 賞与・退職金制度導入 | 非正規雇用者向けの賞与・退職金制度を初導入 | 制度導入+実際の支給実績 | パートに「年2回の賞与」新設、アルバイトにも「勤続〇年以上で退職金」新設 |
| 賃金規定等改定 | 非正規雇用者の基本給・昇給ルールの改定 | 賃金アップ・昇給規定の明文化 | 「毎年4月にパート全員時給20円UP」などを規定 |
| 賃金規定等共通化 | 正規・非正規間の賃金体系共通化 | 待遇格差解消(同一規定化) | 「正社員と同じ等級・昇給ルールをパートにも適用」 |
このように、「賞与・退職金」といった臨時報酬・将来の備えに焦点を当てている点が、他の処遇改善系コースと大きく異なります。2025年現在も、非正規雇用者の処遇底上げ・定着率向上・働きがいアップの観点から強く推進されています。
第2章 制度概要・2025年の改正ポイント

賞与・退職金制度導入コースは、企業が「パート・アルバイト・契約社員」など非正規雇用者向けに新たに賞与(ボーナス)や退職金制度を設け、その支給実績がある場合に助成金を受けられる制度です。従来は正社員のみが対象だった福利厚生を、非正規スタッフにも広げることで、雇用の安定や人材の定着率向上を後押しします。
2025年度の改正では、支給対象となる制度の「実効性」や、制度の継続運用がより重視されるようになりました。つまり、「制度を作っただけ」でなく、「実際に運用し、全員に公平に支給した実績」が審査の重要ポイントです。また、賞与・退職金の「最低支給基準」や「支給人数」に関しても、より明確なルールが設けられています。
- 対象となる賞与・退職金制度は、賃金規定や就業規則に明記されている必要あり
- 実際に対象者全員に、制度に基づく支給を行った実績が必要
- 一定期間以上の勤続や、雇用形態の要件なども細かく規定
例えば「パート従業員全員に年2回、基本給の1ヶ月分を賞与として支給」「勤続3年以上のアルバイトに一律10万円の退職金」といった形で、制度が“実際に活用された”ことを証明できるかが鍵です。詳細な支給基準や運用例は、企業の就業規則・賃金規定に基づいて審査されます。
第3章 助成金の支給要件と対象者

賞与・退職金制度導入コースで助成金を受けるには、いくつかの具体的な条件をクリアする必要があります。この章では、支給対象となる事業所や従業員、満たすべき主な要件について、現場目線でわかりやすく解説します。
- 新たに賞与または退職金制度を導入し、非正規雇用者(パート・アルバイト・有期雇用など)に適用していること
- 就業規則や賃金規定に制度の内容を明記していること
- 制度導入後、実際に全員に支給実績があること(賞与なら支給時期や金額、退職金なら退職時の計算根拠も明示)
- 導入した制度が継続的に運用されていること(単発・名目上の制度は不可)
たとえば、以下のようなケースが「対象」になります。
- これまで賞与・退職金制度がなかったパート従業員向けに、初めて制度を設けて実際に支給した
- 一部の有期雇用者を正社員に転換し、そのタイミングで賞与・退職金規定を新設した
- 制度の導入にあたり、雇用契約書や労働条件通知書も見直し、非正規スタッフの就業環境を大きく改善した
一方、以下のケースは「対象外」です。
- 制度の条文だけ作り、実際には誰にも支給していない
- 正社員のみ対象で、非正規スタッフには適用していない
- 過去すでに同様の制度で助成金を受けており、再度の申請内容がほぼ重複している
支給対象となる「従業員区分」や「最低支給額」「勤続年数」などの細かい条件は、年度ごとに変更される場合があるため、最新の公募要項や厚生労働省・労働局の資料で必ずご確認ください。
第4章 賞与・退職金制度導入コースの助成金額と受給ポイント【2025年度最新】

2025年度の「賞与・退職金制度導入コース」では、導入する制度の種類や支給対象人数によって受給できる助成金額が決まります。
まず、本コースで助成対象となるのは、パート・アルバイト・有期雇用社員など非正規従業員に対し、新たに「賞与制度」や「退職金制度」を導入し、実際に支給や積立を行った場合です。導入内容によって以下のような金額が設定されています。
- ■「賞与制度のみ」または「退職金制度のみ」を新設した場合:各40万円
- ■両方を同時に新設した場合:80万円(個別に導入した場合の合算)
さらに、新制度の適用対象となる非正規労働者が5名以上いる場合は、上記金額に10万円が加算されます。例えば「賞与・退職金の両方を導入し、5名以上に支給」した場合は最大90万円となります。
このように、導入した制度の種類(賞与・退職金・両方)と対象労働者数(5名以上で加算)が助成金額決定のポイントとなります。下表で整理します。
| 導入内容 | 助成金額(2025年度) | 加算・備考 |
|---|---|---|
| 賞与制度のみ導入 | 40万円 | 初めて制度を導入し、実際に賞与を支給した場合 |
| 退職金制度のみ導入 | 40万円 | 初めて制度を導入し、実際に積立・支給を行った場合 |
| 両制度同時導入 | 80万円 | 両方の要件を同時に満たす場合 |
| 対象労働者が5名以上 | +10万円 | 上記金額に加算 |
- 支給対象は、有期雇用・パート・アルバイトなど正社員以外の労働者
- 5名以上で制度を導入した場合は10万円加算(例:両制度導入+5名以上で最大90万円)
助成金申請時の重要ポイントと注意事項
- 規程の新設・改定内容は、就業規則や賃金規程に必ず明記し、全従業員に周知すること
- 過去に寸志や一時金があった場合、「新設」と認められないケースがあるため注意
- 賞与・退職金は、制度導入から6か月以上継続運用し、実際に全員へ支給実績が必要(証憑書類:賃金台帳・振込明細等を準備)
- 正社員にのみ既存制度がある場合でも、非正規雇用向けに新規導入すれば対象
- 名ばかり規程や支給実績ゼロの場合は助成金不支給
- 他コース助成金との併用は、内容・対象が重複しなければOK(同一趣旨の重複申請は不可)
- 支給基準や助成額は年度ごとに変動するため、必ず最新の公募要項・厚労省資料で事前確認を
- 就業規則や賃金規程、過去運用履歴も整理し、審査・申請時にすぐ提出できる体制を整える
- 不明点は必ず事前に労働局や社会保険労務士などの専門家に相談すること
まとめ:助成金受給には「新規性・実効性・継続性」の全てが不可欠です。制度の内容・証憑の準備・社内周知まで万全に整え、要件を満たして確実に申請しましょう。
第5章 申請から受給までの流れと実務ポイント

賞与・退職金制度導入コースの助成金を確実に受給するためには、申請準備から実際の書類提出、支給決定後の手続きまで、一連の流れを正しく把握し、実務的な注意点を押さえることが重要です。2025年度の最新フローをもとに、各段階でのポイントやよくある落とし穴もあわせて解説します。
- 事前準備・制度導入
就業規則や賃金規程の改定内容を全従業員に周知し、新しい賞与・退職金制度を正式にスタートします。
【注意点】 制度導入日や支給開始日、対象者のリストアップもこの時点で明確にしておくこと。不明確だと後の証明が困難になります。 - 6か月以上の制度運用・実際の支給
制度導入後、6か月以上継続して実際に賞与や退職金を支給・積立した証拠資料(賃金台帳や振込明細など)を日々整理・保存しておきます。
【注意点】 証憑が不足していたり、支給内容が規程とずれていると審査で認められません。支給対象者・金額・時期を明確に管理しましょう。 - 申請書類の準備・提出
厚生労働省指定の申請書様式に沿って書類を作成し、必要な添付書類(規程写し、賃金台帳、出勤簿等)をすべて揃えて所轄の労働局・ハローワークに提出します。
【注意点】 書類の不備や記載ミスが多いと、申請差し戻しや審査遅延の原因になります。不明点は事前に専門家や労働局へ確認しましょう。 - 審査・現地調査
提出書類や証憑に不備がないか労働局がチェックし、必要に応じて現地調査や追加書類提出の要請があります。
【注意点】 規程の「新設」と「改定」の区別や、対象者区分が曖昧だと差し戻しリスクが高いです。説明資料や変更履歴も用意しておきましょう。 - 助成金の支給決定・入金
審査を通過すると指定口座に助成金が入金されます。支給後も一定期間、制度の継続運用と記録管理が求められます。
【注意点】 支給後も規程の形骸化や記録漏れがあると、後日の調査で返還を求められるケースがあります。制度運用の記録は継続して保管してください。
ポイント: 各段階で「証憑書類の完備」「対象・金額・規程内容の一貫性」「余裕を持ったスケジュール管理」が重要です。制度導入から支給、申請までの流れを事前にシミュレーションし、書類・記録をきちんと準備しておくことで、申請時のトラブルや差し戻しを大幅に減らすことができます。
第6章 よくある質問(FAQ)

A. 助成金申請では「どの従業員に、どのタイミングで、いくら支給するか」を明確に規定しておく必要があります。曖昧な表現や「業績次第で支給」などの条件付きは審査で否認されることがあります。賃金規程や就業規則には、具体的な支給基準(例:年2回、基本給1か月分など)を明記しましょう。
A. 対象となりますが、支給基準(勤続年数や雇用形態など)は就業規則や賃金規程で事前に定めていることが必須です。「制度導入後に退職したから急きょ退職金を払う」というケースではなく、制度設計時から支給条件に該当する人に支給していれば認められます。
A. 加算が認められるかどうかは、助成金の申請時点や審査時点で「5名以上が実際に制度の適用対象となっているか」で判断されます。導入直後は5名以上でも、申請までに減った場合は加算が認められないことがありますので注意してください。
A. 社労士の関与は必須ではありませんが、規程の作成や証憑の整備、労働局とのやりとりに不安がある場合は早めに相談することを推奨します。自社で進める場合も、申請前に労働局の相談窓口を利用するのが確実です。
A. 非正規雇用者向けに新設した分については対象となります。正社員用の制度が既にあっても、非正規に対して明確に新設し、規程・支給実績があれば、要件を満たす限り申請が可能です。
A. 一番重視されるのは「制度の新設・実効性」「実際の支給実績」「賃金規程等への明記」の3点です。書類上だけの形式的な導入や、支給・積立が形だけの場合は認められません。
A. 受給後も一定期間は制度の継続運用が求められ、調査が入ることもあります。助成金受給後すぐに制度を廃止したり、趣旨を損なう内容に改悪した場合は、助成金の返還を求められる場合があります。
A. 原則として同一内容での重複申請はできません。ただし、新たな対象者や新規の制度導入、内容が異なる場合は別枠で申請できる可能性があります。詳細は申請前に労働局等に確認してください。
A. 処遇改善の内容によっては他のキャリアアップ助成金コース(賃金規定等改定コース、共通化コースなど)や、自治体の独自助成制度が対象になる場合もあります。自社の状況に合わせて複数の制度を比較検討しましょう。
A. 助成金によっては電子申請(e-Gov等)に対応していますが、賞与・退職金制度導入コースについては地域や年度によって運用が異なる場合があります。最新情報は厚生労働省や各労働局の公式サイトでご確認ください。
第7章 活用事例・現場のリアルな声

- 背景・課題:
コロナ禍以降、パート・契約社員の入れ替わりが激しく、毎年2~3割が離職。採用コストが増大し、現場から「待遇面で不公平感が強い」という声も。 - 取り組み・導入プロセス:
社労士のアドバイスで「年2回の賞与規程」と「3年以上勤続で退職金5万円」の両方を新設。賃金規程も刷新し、制度導入の社内説明会を3回実施。「5名以上対象」の条件も意識し、導入直前に全非正規スタッフの雇用契約を見直して対象数をクリア。 - 苦労・落とし穴:
初回の申請書類で「寸志として渡していたギフト券」が過去実績扱いとされ、助成金不支給の危機。証憑を再整理し、“新設”要件の証明に2か月かかった。 - 成果:
制度導入1年で非正規の離職率が14%に低下、採用広告費が前年比60万円減。スタッフアンケートでは「長く働く意欲が上がった」との声が増加。助成金も最大額(90万円)を受給でき、社内でも「正社員以外も守る会社」とのイメージ向上につながった。
- 背景・課題:
有期スタッフの採用定着率が悪く、特に20代・30代の若手層が続かない。退職時トラブル(「退職金がもらえると思っていた」等)も多発。 - 取り組み・導入プロセス:
全有期雇用者に一律「勤続2年以上で一時金10万円」支給を明文化し、就業規則・雇用契約書を同時改定。導入時は全員対象で説明会&個別質疑応答を実施。助成金申請は社内担当と社労士がタッグを組み、3か月かけて証拠書類を徹底整理。 - 苦労・落とし穴:
実際の退職金振込後に、2名分で計算ミスが判明し、急きょ再支給&証憑を再提出。労働局からも「書類記載と実態のズレ」を厳しく指摘され、二度目の申請でようやく認定。 - 成果:
制度導入から半年で「退職時トラブル」がゼロに。3年以内の早期離職者割合も30%→13%に改善。助成金も80万円受給、制度説明会でのアンケート満足度は92%。
- 背景・課題:
首都圏で深刻な人手不足。求人広告を出しても応募が集まらず、既存スタッフから「大手は退職金も出るのに…」との不満も多かった。 - 取り組み・導入プロセス:
「全アルバイト・パートに賞与+退職金制度」を一斉導入し、就業規則・賃金規程を全店舗で統一。制度内容を求人広告・SNSでも積極発信し、「福利厚生強化」を採用PRの軸に。 - 苦労・落とし穴:
証憑準備で「実際に銀行振込した証明」と「規程どおり支給した明細」を全店舗分揃えるのが大変。現場ごとの運用ルール差をなくすため、マニュアル化と全店研修を実施。 - 成果:
制度導入後3か月で求人応募数が約1.7倍に増加。女性スタッフの平均勤続年数も11か月→16か月へ延長。助成金満額(90万円)を受給し、他店舗との差別化につながった。
まとめ:
どの事例でも「証憑書類の準備・過去実績の精査・規程の明文化・現場への周知」が重要ポイントです。特に、“新設”扱いの証明や、就業規則の記載内容、証憑と実態の一致でつまずきやすいので、事前準備は入念に。導入前後の変化を数字で比較し、「制度がどのように効果を発揮したか」を振り返るのも申請・社内アピールの両面で有効です。
第8章 まとめ・今後の実務アドバイス

賞与・退職金制度導入コースは、一時的な資金補助にとどまらず、企業の人事戦略や職場環境、中長期的な経営基盤の強化にもつながる重要な制度です。ここでは実務で押さえておきたいポイントや現場で役立つヒントを、あらためて整理します。
- 1. 助成金は制度定着のきっかけ。単発で終わらせず、現場に根付く工夫を
制度導入がゴールではありません。賞与や退職金制度を活用することで、従業員の定着率やモチベーションの向上、採用時の競争力アップといった経営面での好循環を意識しましょう。現場の声を集めて、制度内容の見直しや追加も柔軟に検討することが大切です。 - 2. 見える化・説明責任を徹底し、誰でも分かる運用ルールに
助成金の審査や現地調査では、書類や証憑だけでなく運用の透明性や周知の徹底も重視されます。説明会やマニュアル配布、全スタッフへの情報共有などを定期的に実施し、現場の声を吸い上げやすい体制づくりも意識しましょう。 - 3. 証憑や記録管理は普段からの習慣に
申請段階で証拠資料を集めるのでは遅い場合もあります。規程改定の履歴や賃金台帳、支給明細、雇用契約書などは普段から誰でもすぐ取り出せる形で整理・保管を習慣化してください。複数拠点や部署がある場合は記録のフォーマット統一も有効です。 - 4. 中小企業や多店舗経営でも活用しやすい柔軟設計を意識
従業員規模や雇用形態が多様でも、制度設計や運用方法を柔軟に調整できる点がこのコースの強みです。パートやアルバイト、有期雇用者ごとに異なる支給基準や、勤続年数による段階的な支給も可能です。自社にとって無理なく続けられる制度設計が長期的な成功につながります。 - 5. 制度活用は社内文化にも影響。小さな成功事例の共有が推進力に
実際に制度を使って定着率が上がった、スタッフのやる気が上がったなど、小さな変化や成功例は積極的に社内で共有しましょう。社内の納得感や新たな制度導入への前向きな雰囲気づくりにもつながります。 - 6. 毎年変わる要件や最新情報のキャッチアップを怠らない
助成金制度は年度ごとに運用や金額、要件が変更される場合が多いです。公式サイトや労働局、社労士などと定期的に情報交換し、「前年と同じ」と思い込まず、必ず最新の要項を確認して準備しましょう。 - 7. 専門家や外部リソースを上手に活用
自社だけで全てを完結させるより、社会保険労務士や行政書士、業界団体など外部の専門家を早めに巻き込むことで、効率的かつ確実に申請や運用が進みます。迷ったらまず相談・確認を。
現場のリアルな悩みや疑問も制度の成否を分けるポイントです。自社の規模や雇用形態でも本当に活用できるのか、過去の慣習が新設扱いになるか不安、社内周知に自信がないなど、現場での悩みはさまざまですが、どんなケースでもまずは公的資料や労働局、専門家の意見を早めに集め、事前対策を徹底しましょう。
最後に、賞与・退職金制度導入コースは、助成金の獲得だけでなく、人事施策や職場づくり全体に波及効果をもたらします。助成金の活用にとどまらず、自社の組織力やブランド力向上につながる人事戦略として、ぜひ前向きに活用してください。
外部関連記事
- 厚生労働省|キャリアアップ助成金(事業主向け総合案内)
- 資金調達ナビ(弥生)|キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入コース 解説
- 社労士法人DSG|キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)活用コラム
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する