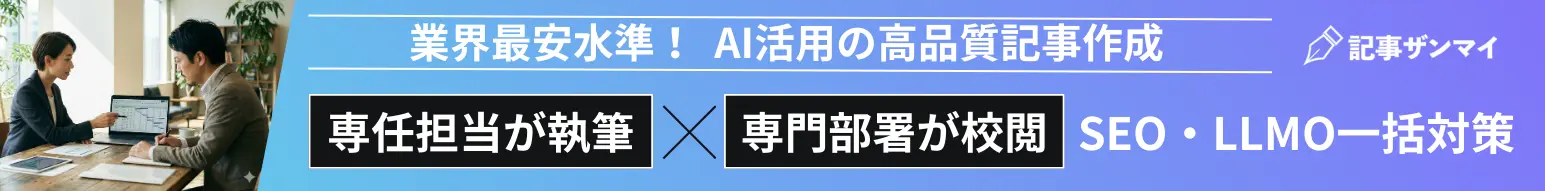近年、感染症の影響などを受け、事業者の皆様にとって支援金、助成金、補助金の重要性が増しています。しかし、これらの公的資金の受給が増加する一方で、会計処理の勘定科目や仕訳に戸惑う方も少なくありません。本記事では、個人事業主、法人、そして税理士の皆様に向けて、支援金、助成金、補助金の会計処理について、勘定科目の選択から仕訳例、税務上の注意点まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
支援金・助成金・補助金とは?返済不要の事業支援金

支援金、助成金、補助金は、国や地方自治体が事業者を支援するために交付するもので、原則として返済不要という大きなメリットがあります。これらは、事業継続や発展を強力にサポートする資金となります。申請には要件が定められており、審査がある場合もありますが、要件を満たし、虚偽の申請などがなければ、多くの事業者がこれらの資金を活用して経営を安定させることができます。
協賛金との違い:民間協力と公的支援
支援金、助成金、補助金と混同されやすいものに協賛金があります。協賛金は、企業や個人がイベントや事業に対し、その活動を支援するために提供する金銭です。支援金や助成金といった公的機関からの給付金とは異なり、協賛金は基本的に民間レベルでの協力関係に基づいて発生します。 支援金や助成金は、国や自治体が特定の政策目標を達成するために、事業者を支援する目的で給付するもので、多くの場合、申請要件や審査が存在します。一方、協賛金は、イベントの円滑な運営や広告宣伝といった対価性を期待して提供されるものであり、支援金等とは性質が異なります。協賛企業は、協賛金を提供することで、イベントを通じて自社のブランドイメージ向上や顧客との関係強化を図るといったメリットを期待します。
支援金・助成金・補助金に用いる勘定科目:状況に応じた選択

支援金、助成金、補助金を受け取った際の会計処理で使用する勘定科目は、状況によって異なります。適切な勘定科目を使用することで、正確な会計処理を行いましょう。
- 雑収入: 支援金などが実際に入金された際に使用します。他の勘定科目に当てはまらない収入を計上する場合に用います。
- 未収金: 支援金等の支給決定通知が届き、後日入金される場合に、入金までの期間に一時的に使用します。
- 事業主借: 個人事業主の場合、事業とは関係のない個人的な給付金が事業用口座に入金された際に使用します。事業主個人の資金と事業用資金のやり取りを記録するために用います。
【事例で解説】支援金・助成金・補助金の仕訳例

支援金や助成金などの仕訳例を具体的に解説します。
例:IT導入補助金50万円が振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 |
|---|
| 預金 500,000円 | 雑収入 500,000円 |
例:雇用促進助成金30万円の給付決定通知が届いた場合 未収計上時
| 借方 | 貸方 |
|---|
| 未収金 300,000円 | 雑収入 300,000円 |
入金時
| 借方 | 貸方 |
|---|
| 預金 300,000円 | 未収金 300,000円 |
事業用口座に補助金50万円が振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 |
|---|
| 預金 500,000円 | 雑収入 500,000円 |
個人口座に補助金50万円が振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 |
|---|
| 事業主借 500,000円 | 雑収入 500,000円 |
支援金・助成金・補助金の受取・会計処理時の注意点:使途、消費税、税金

会計処理で特に注意すべきポイントは、支援金等の使途、消費税の扱い、そして所得税・法人税の課税対象となるかどうかです。
- 使途の確認: 使途が定められている場合、目的外の使用は返納義務が生じる可能性があります。
- 消費税の扱い: 消費税は、支援金等が消費活動を伴わないため課税対象外ですが、会計ソフトの設定によっては課税取引として処理される場合があるため注意が必要です。
- 所得税・法人税の扱い: 所得税・法人税は原則として課税対象ですが、支援金等の種類によっては非課税となるケースもあるため、会計処理前に確認しましょう。
助成金・補助金の種類と活用事例:事業を加速させる資金

中小企業が活用できる助成金・補助金は多岐にわたります。
創業助成金:起業を支援
起業時の資金調達を支援する制度です。創業に必要な経費の一部を補助し、新たなビジネスの立ち上げを後押しします。
小規模事業者持続化補助金:販路開拓と生産性向上
小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援する制度です。広告宣伝費や設備導入費などが補助対象となり、事業の持続的な発展をサポートします。
中途採用等支援助成金:人材獲得をサポート
中途採用者の雇用を促進する制度です。中途採用者の採用や育成にかかる費用を一部補助し、企業の成長を支援します。
活用事例: ある中小企業は小規模事業者持続化補助金を活用し、新たな販路を開拓するためのウェブサイトを制作しました。その結果、売上が大幅に増加し、事業の安定化に繋がりました。
補助金・助成金の仕訳:入金までのタイムラグと未収入金処理

補助金や助成金の支給が決定してから実際に入金されるまでには、タイムラグが生じることがあります。この期間は、各制度や申請状況によって異なります。 支給決定通知が届いた時点で、まだ入金がない場合には、「未収入金」として仕訳処理を行います。例えば、30万円の助成金支給決定通知が届いた場合、借方に未収入金30万円、貸方に雑収入30万円と計上します。入金時には、借方に預金30万円、貸方に未収入金30万円と仕訳し、未収入金を消し込みます。 決算日を跨いで入金となる場合は、未収入金の計上が必須です。計上を怠ると、当期の収入として認識されず、正しい財務諸表が作成できなくなる可能性があります。
補助金・助成金の税務:消費税と法人税の取り扱い

補助金や助成金を受け取った際の税務処理について、消費税と法人税(所得税)の取り扱いを解説します。
消費税は課税対象外
補助金や助成金は、一般的に消費活動に対する対価ではないため、消費税の課税対象とはなりません。会計処理上、「雑収入」として処理する際に、誤って課税取引として処理しないように注意が必要です。
法人税(所得税)は課税対象
原則として、補助金や助成金は法人税(法人の場合)、所得税(個人事業主の場合)の課税対象となります。受け取った金額は、益金(法人の場合)または収入(個人事業主の場合)として計上する必要があります。
非課税となるケースも
例外的に、特定の要件を満たす補助金や助成金は非課税となる場合があります。例えば、国庫補助金等で固定資産を取得した場合、圧縮記帳という税務上の特例を利用することで、課税を繰り延べることが可能です。詳細については、税理士や税務署に確認することをおすすめします。
補助金・助成金の圧縮記帳:固定資産購入時の特例

圧縮記帳は、補助金や助成金を利用して固定資産を購入した際に、課税を繰り延べるための会計処理です。通常、補助金収入は益金として計上され課税対象となりますが、圧縮記帳を適用することで、固定資産の取得価額を減額し、当期の利益を圧縮できます。 会計処理としては、まず補助金収入を雑収入として計上し、その後、固定資産の取得価額を補助金額と同額だけ減額します。この減額分は、将来の減価償却費として費用化されるため、節税効果が得られます。 例えば、100万円の補助金で500万円の機械を購入した場合、圧縮記帳を適用すると、機械の取得価額は400万円となります。これにより、初年度の減価償却費が減少し、課税対象となる利益も圧縮されます。圧縮記帳は、資金繰りの改善にもつながる有効な節税策です。
補助金・助成金の人件費への充当と総額主義:会計処理の原則

補助金や助成金は、事業運営を支援する重要な資金源ですが、会計処理には注意が必要です。特に人件費への充当と総額主義の原則は、誤った処理をしないために理解しておくべき点です。
総額主義の原則とは
総額主義とは、すべての収益と費用を相殺せずに、それぞれの総額を財務諸表に計上する原則です。補助金や助成金を人件費に充当する場合、補助金収入と人件費支出をそれぞれ別々に計上する必要があります。
人件費への直接的な充当は不可
補助金や助成金を直接人件費から差し引くような会計処理は認められません。例えば、100万円の人件費に対し、20万円の補助金を受け取った場合でも、人件費は100万円、補助金収入は20万円として計上します。
適切な会計処理の方法
補助金や助成金を受け取った場合は、雑収入などの適切な勘定科目で収入を計上します。人件費は、給与手当などの勘定科目で通常通り計上します。これにより、財務諸表は正確な情報を反映し、税務上の問題も回避できます。
経理業務効率化の検討:請求管理システムの導入

請求管理システムの導入は、経理業務の効率化に大きく貢献します。請求書の発行、送付、入金消込といった作業を自動化することで、経理担当者の負担を軽減し、人的コストの削減につながります。 特に、中小企業においては、経理担当者の人数が限られている場合が多く、請求管理システムの導入による業務効率化は、より大きなメリットをもたらします。 システム導入により、請求漏れや遅延を防止し、キャッシュフローの改善にも貢献します。また、請求データの分析を通じて、売上動向の把握や顧客管理にも役立てることが可能です。
確定申告を簡単に行う方法:事前準備とIT活用

確定申告の期間は約1ヶ月と限られています。正確な申告を行うには、事前の準備が不可欠です。
確定申告の準備と期間
まずは、必要な書類を揃えましょう。源泉徴収票、控除証明書、経費の領収書などが該当します。確定申告期間は通常、2月中旬から3月中旬です。余裕を持って準備を進めることが大切です。
確定申告ソフトの活用:ミスを減らし効率化
確定申告ソフトを利用すれば、書類作成が格段に楽になります。銀行口座やクレジットカードとの連携機能を使えば、取引データの自動取り込みも可能です。勘定科目の自動推測や仕訳機能も搭載されており、簿記の知識がなくても安心して利用できます。
e-Tax利用のメリット:オンラインで申告
e-Tax(電子申告)を利用すると、税務署へ足を運ぶ必要がありません。自宅やオフィスからオンラインで申告が完了します。青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるには、e-Taxの利用が必須です。マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要になりますが、一度設定すれば、翌年以降もスムーズに申告できます。
まとめ:支援金・助成金・補助金の会計処理をマスターしよう

本記事では、支援金、助成金、補助金の会計処理について、勘定科目や仕訳例、注意点を解説しました。これらは事業者を支援する目的で国や自治体から給付されるお金であり、原則として返済は不要です。
正しい会計処理で事業をサポート
支援金などは、入金時に「雑収入」、未入金時に「未収金」の勘定科目を使用します。個人事業主の場合、事業用口座に個人名義の支援金が入金された際は「事業主借」で処理します。使途が定められている場合や、消費税・所得税の課税対象となる点に注意が必要です。
税理士への相談も検討
会計処理に不安がある場合は、税理士への相談も検討しましょう。適切な会計処理は、事業の健全な運営をサポートします。この記事が、皆様の事業運営の一助となれば幸いです。
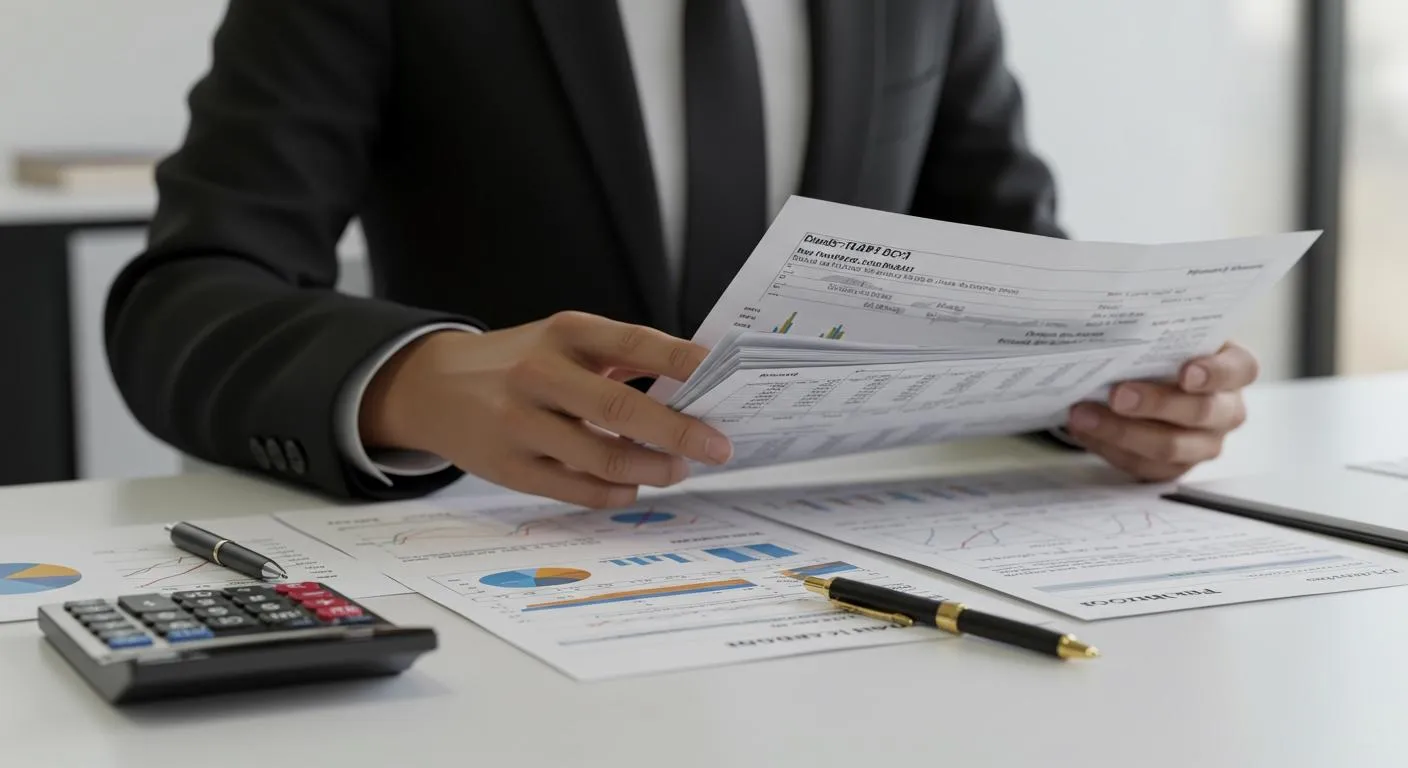
 支援金、助成金、補助金は、国や地方自治体が事業者を支援するために交付するもので、原則として返済不要という大きなメリットがあります。これらは、事業継続や発展を強力にサポートする資金となります。申請には要件が定められており、審査がある場合もありますが、要件を満たし、虚偽の申請などがなければ、多くの事業者がこれらの資金を活用して経営を安定させることができます。
支援金、助成金、補助金は、国や地方自治体が事業者を支援するために交付するもので、原則として返済不要という大きなメリットがあります。これらは、事業継続や発展を強力にサポートする資金となります。申請には要件が定められており、審査がある場合もありますが、要件を満たし、虚偽の申請などがなければ、多くの事業者がこれらの資金を活用して経営を安定させることができます。 支援金、助成金、補助金を受け取った際の会計処理で使用する勘定科目は、状況によって異なります。適切な勘定科目を使用することで、正確な会計処理を行いましょう。
支援金、助成金、補助金を受け取った際の会計処理で使用する勘定科目は、状況によって異なります。適切な勘定科目を使用することで、正確な会計処理を行いましょう。 支援金や助成金などの仕訳例を具体的に解説します。
支援金や助成金などの仕訳例を具体的に解説します。 会計処理で特に注意すべきポイントは、支援金等の使途、消費税の扱い、そして所得税・法人税の課税対象となるかどうかです。
会計処理で特に注意すべきポイントは、支援金等の使途、消費税の扱い、そして所得税・法人税の課税対象となるかどうかです。 中小企業が活用できる助成金・補助金は多岐にわたります。
中小企業が活用できる助成金・補助金は多岐にわたります。 補助金や助成金の支給が決定してから実際に入金されるまでには、タイムラグが生じることがあります。この期間は、各制度や申請状況によって異なります。 支給決定通知が届いた時点で、まだ入金がない場合には、「未収入金」として仕訳処理を行います。例えば、30万円の助成金支給決定通知が届いた場合、借方に未収入金30万円、貸方に雑収入30万円と計上します。入金時には、借方に預金30万円、貸方に未収入金30万円と仕訳し、未収入金を消し込みます。 決算日を跨いで入金となる場合は、未収入金の計上が必須です。計上を怠ると、当期の収入として認識されず、正しい財務諸表が作成できなくなる可能性があります。
補助金や助成金の支給が決定してから実際に入金されるまでには、タイムラグが生じることがあります。この期間は、各制度や申請状況によって異なります。 支給決定通知が届いた時点で、まだ入金がない場合には、「未収入金」として仕訳処理を行います。例えば、30万円の助成金支給決定通知が届いた場合、借方に未収入金30万円、貸方に雑収入30万円と計上します。入金時には、借方に預金30万円、貸方に未収入金30万円と仕訳し、未収入金を消し込みます。 決算日を跨いで入金となる場合は、未収入金の計上が必須です。計上を怠ると、当期の収入として認識されず、正しい財務諸表が作成できなくなる可能性があります。 補助金や助成金を受け取った際の税務処理について、消費税と法人税(所得税)の取り扱いを解説します。
補助金や助成金を受け取った際の税務処理について、消費税と法人税(所得税)の取り扱いを解説します。 圧縮記帳は、補助金や助成金を利用して固定資産を購入した際に、課税を繰り延べるための会計処理です。通常、補助金収入は益金として計上され課税対象となりますが、圧縮記帳を適用することで、固定資産の取得価額を減額し、当期の利益を圧縮できます。 会計処理としては、まず補助金収入を雑収入として計上し、その後、固定資産の取得価額を補助金額と同額だけ減額します。この減額分は、将来の減価償却費として費用化されるため、節税効果が得られます。 例えば、100万円の補助金で500万円の機械を購入した場合、圧縮記帳を適用すると、機械の取得価額は400万円となります。これにより、初年度の減価償却費が減少し、課税対象となる利益も圧縮されます。圧縮記帳は、資金繰りの改善にもつながる有効な節税策です。
圧縮記帳は、補助金や助成金を利用して固定資産を購入した際に、課税を繰り延べるための会計処理です。通常、補助金収入は益金として計上され課税対象となりますが、圧縮記帳を適用することで、固定資産の取得価額を減額し、当期の利益を圧縮できます。 会計処理としては、まず補助金収入を雑収入として計上し、その後、固定資産の取得価額を補助金額と同額だけ減額します。この減額分は、将来の減価償却費として費用化されるため、節税効果が得られます。 例えば、100万円の補助金で500万円の機械を購入した場合、圧縮記帳を適用すると、機械の取得価額は400万円となります。これにより、初年度の減価償却費が減少し、課税対象となる利益も圧縮されます。圧縮記帳は、資金繰りの改善にもつながる有効な節税策です。 補助金や助成金は、事業運営を支援する重要な資金源ですが、会計処理には注意が必要です。特に人件費への充当と総額主義の原則は、誤った処理をしないために理解しておくべき点です。
補助金や助成金は、事業運営を支援する重要な資金源ですが、会計処理には注意が必要です。特に人件費への充当と総額主義の原則は、誤った処理をしないために理解しておくべき点です。 請求管理システムの導入は、経理業務の効率化に大きく貢献します。請求書の発行、送付、入金消込といった作業を自動化することで、経理担当者の負担を軽減し、人的コストの削減につながります。 特に、中小企業においては、経理担当者の人数が限られている場合が多く、請求管理システムの導入による業務効率化は、より大きなメリットをもたらします。 システム導入により、請求漏れや遅延を防止し、キャッシュフローの改善にも貢献します。また、請求データの分析を通じて、売上動向の把握や顧客管理にも役立てることが可能です。
請求管理システムの導入は、経理業務の効率化に大きく貢献します。請求書の発行、送付、入金消込といった作業を自動化することで、経理担当者の負担を軽減し、人的コストの削減につながります。 特に、中小企業においては、経理担当者の人数が限られている場合が多く、請求管理システムの導入による業務効率化は、より大きなメリットをもたらします。 システム導入により、請求漏れや遅延を防止し、キャッシュフローの改善にも貢献します。また、請求データの分析を通じて、売上動向の把握や顧客管理にも役立てることが可能です。 確定申告の期間は約1ヶ月と限られています。正確な申告を行うには、事前の準備が不可欠です。
確定申告の期間は約1ヶ月と限られています。正確な申告を行うには、事前の準備が不可欠です。 本記事では、支援金、助成金、補助金の会計処理について、勘定科目や仕訳例、注意点を解説しました。これらは事業者を支援する目的で国や自治体から給付されるお金であり、原則として返済は不要です。
本記事では、支援金、助成金、補助金の会計処理について、勘定科目や仕訳例、注意点を解説しました。これらは事業者を支援する目的で国や自治体から給付されるお金であり、原則として返済は不要です。