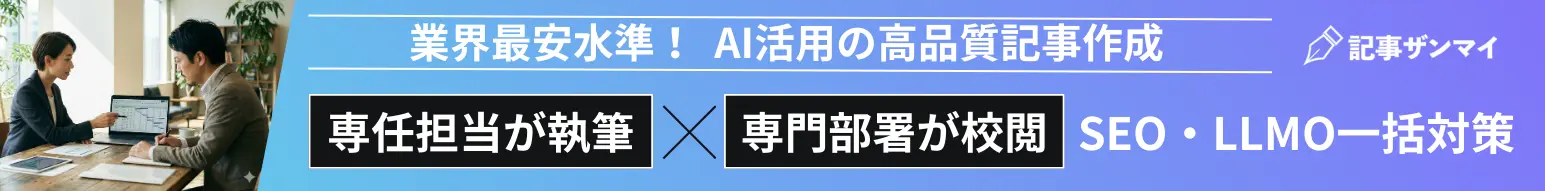支援金・助成金・補助金とは?協賛金との違いと資金調達における位置づけ
 支援金、助成金、補助金は、国や地方自治体が事業者を支援するために支給するもので、原則として返済は不要です。これらは、事業継続や新たな取り組みへの挑戦を後押しする重要な資金源となります。
支援金、助成金、補助金は、国や地方自治体が事業者を支援するために支給するもので、原則として返済は不要です。これらは、事業継続や新たな取り組みへの挑戦を後押しする重要な資金源となります。協賛金との違い:対価性の有無
協賛金は、イベントなどに対する協力金として受け取るもので、広告宣伝などの対価性が見込まれます。一方、支援金・助成金・補助金は、特定の事業や活動を支援する目的で支給され、直接的な対価を伴わない点が協賛金との大きな違いです。資金調達における位置づけ:返済不要のメリット
支援金、助成金、補助金は返済不要のため、資金調達において大きなメリットがあります。ただし、申請要件や審査がある場合が多いので、注意が必要です。これらの資金は、融資とは異なり、財務体質の改善にも貢献します。支援金・助成金・補助金に用いる勘定科目:ケース別解説
 支援金、助成金、補助金の会計処理で迷う勘定科目をケース別に解説します。適切な勘定科目を選択することで、正確な財務諸表を作成し、税務調査にも対応できます。
支援金、助成金、補助金の会計処理で迷う勘定科目をケース別に解説します。適切な勘定科目を選択することで、正確な財務諸表を作成し、税務調査にも対応できます。入金時の仕訳:原則は雑収入
支援金が入金された際は、通常「雑収入」を使用します。例えば、中小企業向けの給付金が振り込まれた場合、借方に預金、貸方に雑収入と仕訳します。雑収入は、本業以外の収入で、他の勘定科目に当てはまらない場合に用いる勘定科目です。未入金時の仕訳:未収金の活用
支給決定通知が届き、実際に入金されるまで期間がある場合は、「未収金」を活用します。後日入金された際に、未収金を消し込みます。決算を跨ぐ場合は未収計上が必要です。これにより、期間損益計算を適切に行うことができます。個人事業主の場合:事業主借の利用
個人事業主の場合、事業用口座に個人名義の支援金が入金されることがあります。この際は、「事業主借」を利用します。個人の資金が事業用口座に入金されたと考えるためです。勘定科目の選択フローチャート
どの勘定科目を使うべきか迷ったら、以下のフローを参考にしてください。- 入金があったか? → はい(雑収入)、いいえ(未収金)
- 個人事業主で、個人名義の入金か? → はい(事業主借)、いいえ(雑収入または未収金)
経費・費用として計上できるケース/できないケース
助成金や補助金を受け取った場合、その金額を「経費」や「費用」として直接計上できるかどうかは、資金の性質や使途によって異なります。
通常、受け取った助成金は「雑収入」などの収益科目で処理しますが、 その助成金で購入した備品やサービスなどが事業のための「経費」に該当する場合は、その分を経費計上できます。
ただし、助成金で賄った部分と自己資金の部分を明確に分け、助成金による補填分は「経費」から除外する必要があります。
例) 補助金を利用して10万円のパソコンを購入し、うち6万円が補助金、4万円が自己負担の場合、経費計上できるのは自己負担分の4万円となります。
この点を誤ると税務調査で指摘されるケースがあるため、支出の「金額」や「対象」を明確にし、帳簿で区分しておきましょう。
【事例で解説】支援金・助成金・補助金の仕訳例:個人事業主・法人別

支援金・助成金・補助金の仕訳処理は、「いつ・どこに・どんな資金が入るか」によってさまざまなパターンがあります。ここでは、実際の現場でよくある流れを“ケース形式”で具体的に解説します。
事例1:法人でIT導入補助金を受けたケース
ある中小企業が業務効率化のため、IT導入補助金に応募し、50万円の補助金を獲得しました。補助金は導入完了後に銀行口座へ入金されました。
- 仕訳:
(借方)預金 500,000円 /(貸方)雑収入 500,000円 - ポイント:補助金で購入したIT機器の費用は、別途「備品」や「消耗品費」で経費計上します。
事例2:雇用促進助成金が未収状態で決算を迎えた場合
製造業を営むA社は、雇用促進助成金の申請が通り、30万円の給付決定通知が届きました。しかし、実際の入金は決算後となる予定です。
- 決算時の仕訳:
(借方)未収金 300,000円 /(貸方)雑収入 300,000円 - 入金時の仕訳:
(借方)預金 300,000円 /(貸方)未収金 300,000円 - ポイント:「未収金」で処理することで、決算期の損益を正しく反映できます。
事例3:個人事業主の補助金受取と口座区分
個人事業主のBさんは、小規模事業者持続化補助金(補助率2/3、補助額20万円)を受けました。補助金は個人口座に振り込まれました。
- 仕訳:
(借方)事業主借 200,000円 /(貸方)雑収入 200,000円 - 補助対象経費(広告費30万円)のうち自己負担10万円は「広告宣伝費」などで経費計上します。
事例4:設備投資への補助金と圧縮記帳
飲食業を営むC社は、地方自治体の設備投資補助金で100万円を受給し、200万円の新しい厨房機器を購入しました。C社は圧縮記帳を選択し、税務上の課税所得を調整しました。
- 補助金の入金時:
(借方)現金 1,000,000円 /(貸方)雑収入 1,000,000円 - 機器の購入時:
(借方)機械装置 2,000,000円 /(貸方)現金 2,000,000円 - 圧縮記帳処理時:
(借方)圧縮損 1,000,000円 /(貸方)機械装置 1,000,000円 - ポイント:圧縮記帳により、補助金分は課税所得から控除され、税負担の適正化につながります。
事例5:返還が発生した場合
D社は補助金を受領後、使途制限違反で10万円の返還を求められました。D社は返金と同時に以下の仕訳を行いました。
- 仕訳:
(借方)雑損失 100,000円 /(貸方)現金 100,000円 - ポイント:返還額が過去の会計年度に計上したものであれば、修正申告が必要になるケースもあります。
よくある質問(FAQ)
- 補助金の用途と課税対象、消費税区分は?
- 補助金の大半は消費税不課税ですが、法人税・所得税は原則課税対象です。詳細は各制度ごとの規定を確認してください。
- 科目選択を間違えた場合の対処法は?
- 訂正仕訳や振替仕訳で修正できます。複雑な場合は税理士等の専門家に相談しましょう。
支援金・助成金・補助金の仕訳処理は、申請要項や交付決定通知、会計基準・税法等によってケースバイケースです。複雑な場合や迷う場合は、必ず税理士や会計専門家に相談し、帳簿や証憑の保存も徹底してください。
補助金・助成金の実務ポイントと注意点(用語強化用例文)
補助金や助成金、給付金の申請手続きでは、審査、書類提出、承認、確定通知、事後報告、支給決定など、さまざまなプロセスが関係します。また、定款、会計基準、法人格、NPO法人、社会福祉法人といった団体種別でも処理方法が異なります。
経理処理の現場では、勘定分類、仕訳帳、伝票処理、内部統制、監査、証憑、領収書、原価、付随費用、営業外収益、特別利益、流動資産、損益計算書、貸借対照表、利益剰余金、減価償却、耐用年数、一括償却、修繕費、科目細分化、附帯収益、税額控除、補助対象外経費といった多彩なキーワードが登場します。
これらの会計処理や財務管理を正しく理解することで、収益計上、費用配分、キャッシュフロー管理、資金繰り、黒字化、税務調整といった重要な経営課題にも適切に対応できるようになります。
事例:助成金と交際費の違い(実務比較)
例えば、自治体や団体から提供された交際費的支援金と、一般的な助成金は、経理処理や課税の観点で大きく異なります。交際費として処理した場合は「交際費」科目となり、損金算入限度額や税法上の調整が必要です。一方、助成金や補助金は「雑収入」や「補助金収入」として計上し、経費計上の対象とはなりません。
【仕訳例】
(借方)交際費 50,000円 /(貸方)現金 50,000円
(借方)現金 100,000円 /(貸方)雑収入 100,000円
事例:100万円を超える大型補助金の圧縮記帳・課税関係
新たに高額な補助金(例:120万円)を取得し、固定資産(例えば製造設備など)を導入した場合、圧縮記帳や一括償却、減価償却費の取り扱いが課題となります。補助金額が大きい場合は、会計処理のタイミングや課税所得、資産計上方法に注意が必要です。
【仕訳例】
(借方)機械装置 1,200,000円 /(貸方)現金 1,200,000円
(借方)圧縮損 1,200,000円 /(貸方)機械装置 1,200,000円
(借方)現金 1,200,000円 /(貸方)雑収入 1,200,000円
圧縮記帳の活用により、課税所得を適切に調整し、資産価値の管理や税務リスク低減に役立ちます。
確定申告を簡単に行う方法:会計ソフトの活用
 確定申告の煩雑さを解消し、効率化を図るために、会計ソフトの活用は非常に有効です。手作業での計算や書類作成にかかる時間と手間を大幅に削減できます。
確定申告の煩雑さを解消し、効率化を図るために、会計ソフトの活用は非常に有効です。手作業での計算や書類作成にかかる時間と手間を大幅に削減できます。確定申告ソフトのメリット:自動化と正確性
会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、仕訳を自動化する機能があります。これにより、入力ミスを減らし、正確な確定申告書類を作成できます。また、税法の改正にも自動で対応するため、常に最新の税制に基づいた申告が可能です。e-Tax利用の注意点:事前準備の重要性
e-Taxを利用することで、自宅からオンラインで確定申告ができます。しかし、利用にはマイナンバーカードやICカードリーダライタなどの事前準備が必要です。事前に必要なものを確認し、早めに準備しておきましょう。おすすめの確定申告ソフト紹介
多くの会計ソフトが提供されていますが、初心者にも使いやすいインターフェースを持つソフトや、サポート体制が充実しているソフトを選ぶのがおすすめです。無料体験版などを活用し、自分に合ったソフトを見つけましょう。助成金・補助金の探し方:最新情報をチェック
 助成金や補助金は、事業の成長を支援する重要な資金源です。しかし、その情報は多岐にわたり、探し出すのが難しいと感じる方もいるでしょう。ここでは、最新情報を効率的にチェックし、最適な助成金・補助金を見つける方法をご紹介します。
助成金や補助金は、事業の成長を支援する重要な資金源です。しかし、その情報は多岐にわたり、探し出すのが難しいと感じる方もいるでしょう。ここでは、最新情報を効率的にチェックし、最適な助成金・補助金を見つける方法をご紹介します。助成金・補助金検索サイトの紹介
まず、国や地方自治体が運営する助成金・補助金検索サイトを活用しましょう。これらのサイトでは、最新の情報を一元的に確認できます。キーワードや業種、地域などを指定して検索することで、自社に合った支援制度を効率的に見つけられます。専門家への相談:税理士、中小企業診断士
税理士や中小企業診断士などの専門家は、助成金・補助金に関する豊富な知識と経験を持っています。自社の状況や事業計画を詳しく伝え、最適な支援制度についてアドバイスを求めるのがおすすめです。専門家は、申請書類の作成や手続きのサポートも行ってくれるため、時間と労力を大幅に節約できます。申請代行サービスの活用:時間と労力の節約
助成金・補助金の申請は、煩雑な手続きや書類作成が必要となる場合があります。時間や労力を節約したい場合は、申請代行サービスの利用を検討しましょう。専門の代行業者に依頼することで、申請に必要な書類の準備から提出までをスムーズに進めることができます。「該当」「条件」「年度」など検索・比較のポイント
各種補助金・助成金制度には、それぞれ「該当」する事業者や「条件」「年度」などが細かく設定されています。自社が該当するか、金額や対象経費、交付時期などの細かな条件まで必ずチェックしましょう。必要な「資料」や「登録」も早めに準備することで、申請のタイミングを逃さず活用できます.中小企業が活用できる助成金・補助金:事例紹介
 中小企業が活用できる助成金・補助金は、事業の成長を力強く後押しする重要な資金源です。起業を支援する「創業助成金」、販路拡大をサポートする「小規模事業者持続化補助金」、そして人材育成を促進する「キャリアアップ助成金」など、様々な制度が存在します。 自社に合った制度を見つけるためには、まず事業の現状と課題を明確にし、どのような支援が必要かを具体的に把握することが重要です。その上で、各制度の申請要件や支援内容を比較検討し、最も適した制度を選びましょう。 これらの助成金・補助金は原則として返済不要であり、企業の成長戦略を加速させるための貴重なリソースとなります。積極的に活用を検討し、事業の発展に繋げましょう。
中小企業が活用できる助成金・補助金は、事業の成長を力強く後押しする重要な資金源です。起業を支援する「創業助成金」、販路拡大をサポートする「小規模事業者持続化補助金」、そして人材育成を促進する「キャリアアップ助成金」など、様々な制度が存在します。 自社に合った制度を見つけるためには、まず事業の現状と課題を明確にし、どのような支援が必要かを具体的に把握することが重要です。その上で、各制度の申請要件や支援内容を比較検討し、最も適した制度を選びましょう。 これらの助成金・補助金は原則として返済不要であり、企業の成長戦略を加速させるための貴重なリソースとなります。積極的に活用を検討し、事業の発展に繋げましょう。事例:固定資産取得や経費補助の活用
創業助成金を利用し、設備やパソコンなどの「固定資産」を取得した事例、小規模事業者持続化補助金で広告費や「経費」を補助された事例などがあります。制度ごとに対象となる「費用」「金額」「対象事業」が異なるため、該当するものを見極めて申請しましょう。「圧縮記帳」や「未収入金」処理が必要なケースもあり、専門家の助言が役立ちます。
経理業務効率化の検討:請求管理システムの導入
 経理業務における時間とコストの削減は、多くの企業にとって重要な課題です。特に請求業務は、毎月発生するルーチンワークであり、自動化による効率化が期待できます。 請求管理システムを導入することで、請求書の発行、送付、入金消込といった一連の作業を自動化し、大幅な時間短縮とコスト削減が実現可能です。 システムを選ぶ際には、自社のニーズに合った機能を備えているかどうかが重要になります。例えば、請求書の自動発行、入金状況の自動照合、未入金催促機能などが挙げられます。 様々な請求管理システムがありますが、導入を検討する際は、無料トライアルなどを活用し、実際に操作感を確かめてから導入を決定することをおすすめします。自社に最適なシステムを選び、経理業務の効率化を実現しましょう。
経理業務における時間とコストの削減は、多くの企業にとって重要な課題です。特に請求業務は、毎月発生するルーチンワークであり、自動化による効率化が期待できます。 請求管理システムを導入することで、請求書の発行、送付、入金消込といった一連の作業を自動化し、大幅な時間短縮とコスト削減が実現可能です。 システムを選ぶ際には、自社のニーズに合った機能を備えているかどうかが重要になります。例えば、請求書の自動発行、入金状況の自動照合、未入金催促機能などが挙げられます。 様々な請求管理システムがありますが、導入を検討する際は、無料トライアルなどを活用し、実際に操作感を確かめてから導入を決定することをおすすめします。自社に最適なシステムを選び、経理業務の効率化を実現しましょう。助成金・補助金の管理も自動化
請求管理システムの一部には、助成金・補助金の「申請」「資料」「登録」「年度」管理ができる機能もあります。経費補助や補助金を受けた「対象経費」の自動仕訳やレポート出力、インボイス制度対応などもサポートされており、より正確で効率的な経理業務が可能です。まとめ:支援金・助成金を活用して事業を成長させよう
 支援金、助成金、補助金は、事業の資金調達における重要な選択肢です。これらを活用する際は、適切な会計処理を行い、税務リスクを回避することが不可欠です。最新の制度情報を積極的に収集し、必要に応じて税理士などの専門家と連携することで、最適な活用方法を見つけられます。これらの資金を有効活用し、事業の成長につなげましょう。
支援金、助成金、補助金は、事業の資金調達における重要な選択肢です。これらを活用する際は、適切な会計処理を行い、税務リスクを回避することが不可欠です。最新の制度情報を積極的に収集し、必要に応じて税理士などの専門家と連携することで、最適な活用方法を見つけられます。これらの資金を有効活用し、事業の成長につなげましょう。今後の税制・制度改正にも注意
インボイス制度や圧縮記帳、未収入金・経費区分など、会計や税務の制度は毎年変化しています。最新の「条件」や「登録」「適用」情報をこまめにチェックし、「年度ごと」「タイミング」による違いにも注意しましょう。制度を正しく活用し、確実な資金調達と経営の効率化につなげてください。外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する