
- 中小企業・個人事業主必見!IT導入補助金と雇用調整助成金で資金調達のチャンスを最大化
- シニア人材が会社を変える!高齢者雇用×助成金の戦略的活用
- 高年齢者雇用を促進する「無期雇用転換コース」徹底解説:企業の成長と高齢者の活躍を支援
- 障害者雇用を支援する助成金制度:企業の課題解決と活用事例
経済状況が不安定な昨今、企業の経営安定と雇用維持は重要な課題です。本記事では、事業主が従業員の雇用を維持するための強力な支援制度である「雇用調整助成金」と、生産性向上と賃上げを支援する「業務改善助成金」について、制度の概要から申請方法、注意点までを詳しく解説します。これらの助成金を活用し、変化に強い企業体質を構築しましょう。
雇用調整助成金とは?
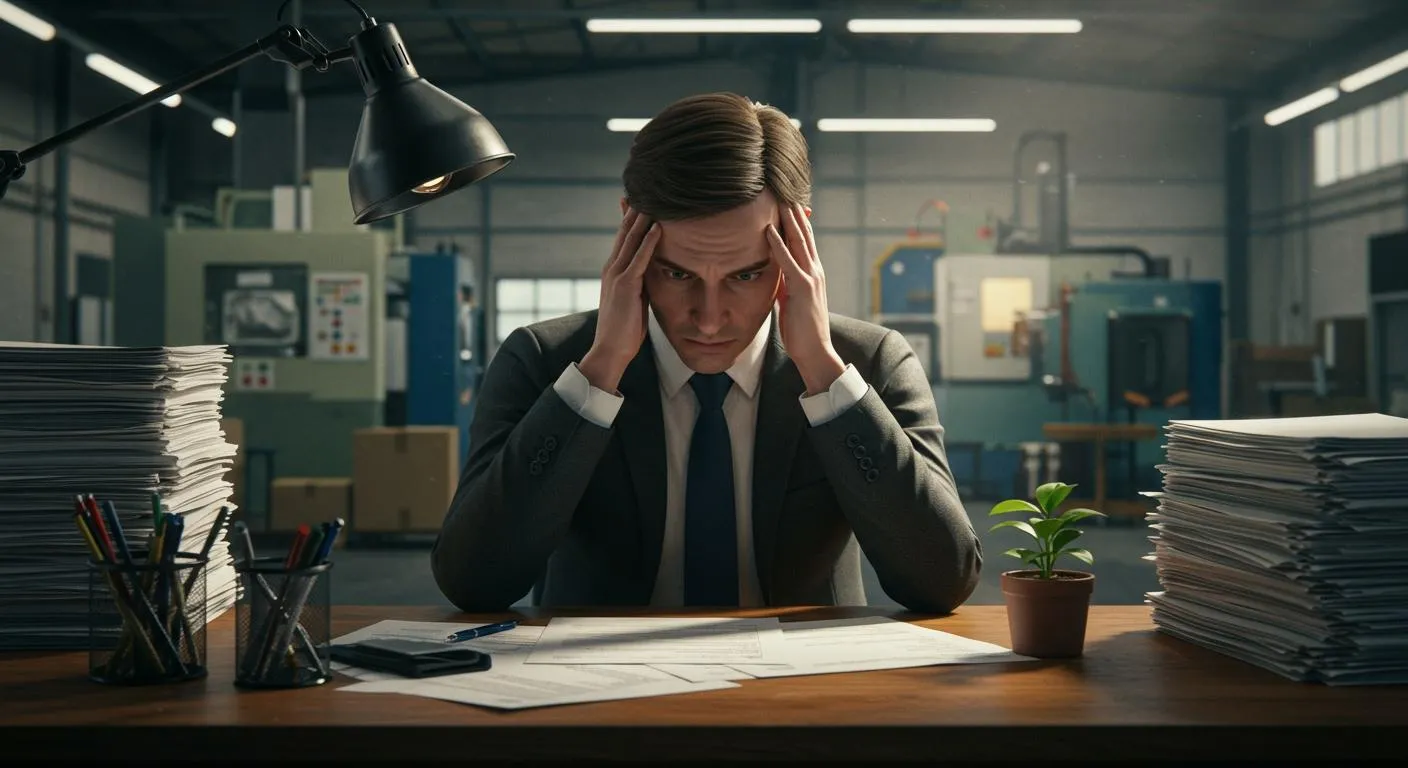
雇用調整助成金は、経済的な理由で事業活動を縮小せざるを得ない事業主が、従業員の雇用維持のために休業、教育訓練、出向といった雇用調整を実施する際にかかる費用の一部を助成する制度です。従業員の解雇を回避し、企業のノウハウや技術の流出を防ぎ、景気回復時に迅速な事業再開を可能にすることを目的としています。
今、雇用調整助成金が重要な理由

昨今の経済情勢は依然として不透明であり、多くの企業が経営の安定に苦慮しています。このような状況下で、雇用調整助成金は、企業が従業員を解雇せずに雇用を維持するための重要なセーフティネットとなります。雇用維持は、企業が培ってきた技術やノウハウの維持に繋がり、景気回復時にはスムーズな事業再開を可能にします。経済の変動に柔軟に対応し、雇用を守るために、雇用調整助成金の活用を検討することが不可欠です。
雇用調整助成金の基本:受給要件と対象となる事業主

雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持のために休業、教育訓練、出向を実施した場合に支給されます。受給には以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険適用事業主であること
- 最近3か月の月平均売上高が前年同期比で10%以上減少していること
- 雇用量の維持(一定の増加率基準あり)
雇用調整措置としては、以下のものが対象となります。
- 休業:労使協定に基づき所定労働日の全1日にわたって実施
- 教育訓練:職業に関する知識・技能の習得
- 出向:3か月以上1年以内の期間
これらの要件を満たすことで、助成金を受け、従業員の雇用維持に繋げることができます。
補助対象経費:何が助成されるのか?

雇用調整助成金では、以下の費用が助成対象となります。
- 休業手当: 労使協定に基づき、従業員に支払う休業手当。助成対象となる範囲は、休業期間中の給与に相当する額で、一定の助成率が適用されます。
- 教育訓練費: 従業員のスキルアップを目的とした教育訓練にかかる費用。訓練内容によって加算額が設けられており、職業に関する知識や技能向上が対象です。
- 出向に関する費用: 従業員を一時的に他の事業所へ出向させる場合、出向期間中の費用。出向期間は3か月以上1年以内であることが条件です。
業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資やコンサルティング費用、従業員の教育訓練費などが対象となる点が、雇用調整助成金とは異なります。それぞれの助成金の特性を理解し、自社の状況に合わせて活用を検討しましょう。
支給額の計算方法:助成率と加算額

雇用調整助成金の支給額は、休業手当や賃金相当額に助成率を乗じて計算されます。助成率は、支給日数や教育訓練実施率によって変動します。教育訓練を積極的に実施している企業には、より高い助成率が適用される場合があります。
教育訓練を実施した場合は、さらに教育訓練加算額が支給されます。これは、従業員1人1日あたりの金額で定められており、教育訓練の実施を奨励する目的があります。
支給額の計算は複雑なため、厚生労働省の関連資料やハローワークへの相談をおすすめします。
令和6年能登半島地震の影響を受けた事業主の皆様へ:雇用調整助成金に関する特例措置

令和6年能登半島地震により事業活動の縮小を余儀なくされた地域(石川県など、厚生労働省が指定する地域)の事業主を対象とした特例措置が設けられています。
特例措置の内容:対象地域と期間
対象となるのは、能登半島地震により事業活動の縮小を余儀なくされた地域(石川県など、厚生労働省が指定する地域)の事業主です。期間は、令和6年1月1日以降に開始する休業、教育訓練、出向が対象となります。通常の雇用調整助成金よりも要件が緩和されている場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
申請の際の注意点:必要書類と手続き
申請には、通常の雇用調整助成金に必要な書類に加え、地震の影響を受けたことを証明する書類が必要となる場合があります。手続きの詳細や必要書類については、各都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。早めの申請準備をお勧めします。
申請手続き:公募要領の確認ポイント

雇用調整助成金や業務改善助成金の申請には、公募要領の確認が不可欠です。
- 申請の流れ: 事前準備として、助成金の目的や要件を理解し、自社が対象となるか確認しましょう。支給までのステップを把握し、計画的に進めることが重要です。
- 必要書類: 申請には、事業計画書、賃金台帳、労働者名簿など、様々な書類が必要です。事前に準備すべき書類の一覧を確認し、不足がないようにしましょう。
- 申請先: 雇用調整助成金は都道府県労働局またはハローワーク、業務改善助成金は厚生労働省が窓口です。申請先を間違えないように注意しましょう。
- 申請期限: 各助成金には申請期限が設けられています。余裕を持った準備を心がけ、期限内に申請を完了させましょう。詳細な情報は、関連パンフレットやFAQで確認できます。不明な点は、各窓口に問い合わせるのが確実です。
不正受給に注意:適正な申請を心がけましょう

雇用調整助成金や業務改善助成金は、事業主にとって経営を安定させる上で重要な制度ですが、不正受給には十分注意が必要です。
不正受給の定義と事例
不正受給とは、偽りや不正な手段を用いて助成金を受け取る行為を指します。例えば、休業の実態がないにも関わらず休業手当を支給したと偽ったり、実際には行っていない教育訓練を実施したと申告したりするケースが考えられます。業務改善助成金においては、実際には設備投資を行っていない、または虚偽の賃上げを報告するなどが該当します。
不正受給が発覚した場合の措置
不正受給が発覚した場合、助成金の返還はもちろんのこと、事業所名の公表や、悪質な場合は詐欺罪等で告発される可能性もあります。信用を失うだけでなく、法的責任を問われる重大な事態に発展する可能性があります。
適正な申請のために
助成金の申請に不安がある場合は、都道府県労働局やハローワークなどの相談窓口を積極的に活用しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適正な申請が可能となり、不正受給のリスクを回避できます。制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
関連情報:パンフレット、FAQ、問い合わせ先

雇用調整助成金に関する詳細な情報は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。制度の概要、申請方法、最新情報などが掲載されていますので、必ずご確認ください。
具体的な相談や申請手続きについては、各都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。専門の担当者が個別の状況に応じて丁寧にサポートしてくれます。
関連パンフレットは厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。制度の概要や申請に必要な書類、手続きの流れなどが分かりやすくまとめられていますので、ご活用ください。
また、業務改善助成金との併用を検討されている場合は、それぞれの助成金の要件を確認し、両方の制度を活用できるか検討することが重要です。併用に関する詳細も、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
今後の展望と積極的な活用

助成金の制度は、経済状況や社会情勢に合わせて変更されることがあります。最新の情報を常に確認し、変更点に注意することが重要です。厚生労働省のウェブサイトや都道府県労働局、ハローワークなどで情報を収集しましょう。
雇用調整助成金は、企業の雇用維持を支援する重要な制度です。また、業務改善助成金は生産性向上と賃上げを支援します。これらの助成金を積極的に活用し、雇用を守りながら企業成長を目指しましょう。
雇用調整助成金と業務改善助成金は、企業の持続的な成長を支えるための重要なツールです。これらの制度を理解し、積極的に活用することで、厳しい経済状況を乗り越え、更なる発展を目指しましょう。
- 雇用調整助成金 – 厚生労働省
- 業務改善助成金 – 厚生労働省
- 雇用関係助成金一覧 – 厚生労働省
- 中小企業等関連予算(助成金制度) – 中小企業庁
- 最大600万円!変更点多数の業務改善助成金について – 中小企業診断士解説
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




