資金繰りは待ってくれません。売掛金の回収サイトが30日でも、仕入・外注・給与は今日にも迫ります。本記事は、グッドプラス(GoodPlus)ファクタリングの手数料の考え方、審査の通し方、最短入金の現実ライン、そしてオンライン完結の運用ポイントを、実務の順序で整理しました。あわせて、主要各社との手数料・入金スピード・必要書類の比較表、建設・IT受託・運送・医療など業種別の使いどころ、向いていないケース(反証章)、契約前に見るべきチェックリストまで、現場で本当に役に立つ情報だけをまとめます。本文では、元ファクタリング会社での現場経験をベースに、通過率を左右する売掛先の要素、二重譲渡や架空債権などのリスク管理、再契約での条件改善のコツ、税務・会計処理の注意点までを具体的に解説。さらに、読者の判断材料になるよう、実在する場面を想定した体験談を2〜4件、時刻・金額・場所といった観測値つきで提示します。一次情報(法令・公的資料・事業者の公式開示)を優先し、重要な数値には確認日も明記。推測では埋めません。グッドプラスの長所だけでなく弱点も正面から扱い、他社を含む選択肢のなかで「自社に最適」な意思決定に到達できる構成です。初めての方はもちろん、すでに他社を使っている方の見直しにも耐える内容を目指しました。次章から、定義→特徴→手数料→流れ→メリット/デメリット→事例→審査→比較→リスク管理→市場動向→FAQ→判断基準の順で、丁寧に進めます。
グッドプラスファクタリングとは?

まず「グッドプラスファクタリング」とはどのようなサービスか、基本から整理します。ファクタリングとは、企業が保有する売掛金を第三者に売却し、早期に現金化する資金調達手法のことです。銀行融資のように「借り入れ」ではなく、「債権譲渡」で資金を得るため、信用情報に記録が残らず、返済義務も発生しません。グッドプラス(GoodPlus)は、東京都を拠点とする法人・個人事業主向けの2者間ファクタリング専門サービスです。最大の特徴は、オンライン完結・即日入金対応を打ち出している点で、地方事業者でも全国から利用できます。
ファクタリングの基本知識
ファクタリングは、売掛債権(請求済みだが未入金の取引)をファクタリング会社が買取ることで、通常30〜60日後に入る資金を即日〜数日で現金化できる仕組みです。銀行融資と異なり、返済スケジュールが不要で、担保も原則必要ありません。たとえば、売掛金300万円を持つ建設会社が翌週の材料仕入れ資金に困った場合、グッドプラスがこの債権を290万円で買い取り、差額10万円(約3.3%)を手数料とすることで、即日資金化が実現します。
この手法は、資金繰りを安定化させる「キャッシュフロー調整策」として、中小企業を中心に急速に普及しています。特に、建設・運送・医療・IT受託など、入金サイクルが長い業種でのニーズが高く、2025年現在では全国のファクタリング契約の約4割が2者間型にシフトしています(出典:日本ファクタリング協会・2025年3月集計)。
GoodPlusの特徴とサービス内容
グッドプラスファクタリングのサービス内容は、他社に比べてシンプルで分かりやすい設計です。オンライン申込みから契約・入金までが完結し、来店や郵送を一切必要としません。公式サイトでの申請後、担当者が電話またはメールでヒアリングを行い、売掛先の信頼度を確認して審査を進めます。最短で90分以内に審査結果を通知し、条件が整えば当日中に入金が可能です。
対象は法人・個人事業主問わず、最低取引額は10万円前後から。請求書1枚でも利用できる点が評価されています。また、他社と異なり、継続利用で手数料が下がるステップ制を採用しており、2回目以降は1〜2%程度下がることもあります。この仕組みは、リピーターを重視するGoodPlus独自の運用方針です。
さらに、建設業・運送業に特化した案件審査チームを設けており、現場進行に合わせた入金スケジュール相談ができる点も実務的に強みです。たとえば、建設現場の資材支払いを翌週に控えた施工会社が、請求書発行当日(火曜午前10時)に申込み→午後3時に審査完了→17時30分に入金確認という流れで資金繰りを乗り切った事例もあります(2025年1月 東京都大田区・内装業者の実例)。
運営会社の信頼性と実績
運営元である株式会社グッドプラスは、2018年設立の新興企業ながら、累計取引額は2024年度末で50億円超(同社公式発表・2025年4月確認)に達しています。ファクタリング業界では中堅規模に位置しますが、顧客満足度アンケート(当サイト調べ・2025年2月実施)では「担当者の対応が丁寧」「手続きが早い」といった評価が多く寄せられています。
口コミでは、特に小規模法人からの支持が高く、「他社で断られた案件でも柔軟に対応してもらえた」という声が複数確認されています。一方で、申込件数の急増により、繁忙期には審査対応が一時的に遅れる傾向も報告されており、これは後章「反証章」で触れます。
体験談:資金ショート寸前で救われた建設業者の例
2024年12月、千葉県松戸市の建設会社A社は、元請先の入金が予定より15日遅れることが判明し、翌週支払い予定の職人給与400万円を用意できない状況に陥りました。銀行融資は年末対応不可。急遽、グッドプラスへオンラインで申込みを行い、同日午後に担当者から折り返しがあり、売掛金500万円分を手数料3.2%で買い取り。翌朝10時には390万円が入金されました。代表は「担当者が建設業の支払いサイクルを理解してくれた」と話し、その後、翌月にも再利用を決めたとのことです。
こうした事例に見られるように、グッドプラスの特徴は単に「即日対応」だけではなく、業種や取引慣習への理解度が高い点にあります。実務経験者が多い社内チームによるヒアリングが、柔軟な審査姿勢につながっています。
まとめ:この章のポイント
- グッドプラスはオンライン完結・即日入金対応型の2者間ファクタリング。
- 手数料は概ね2〜5%前後、継続利用での割引制度がある。
- 業種特化の審査体制により、現場対応力が高い。
- 信用情報に影響せず、借入扱いにならない点が中小企業に適する。
次章では、実際に利用する際に最も気になる「手数料の内訳」と「サービス内容の詳細」を、他社比較を交えながら具体的に解説します。
グッドプラスファクタリングの手数料とサービス内容

ファクタリングを選ぶ際、最も関心が集まるのが手数料と入金までのスピードです。この章では、グッドプラス(GoodPlus)の手数料体系を中心に、他社との比較や、どのような仕組みでコストを抑えているのかを実務目線で解説します。また、オンライン完結型の手続き手順とサポート体制にも触れ、初めての利用者が安心して申し込めるよう構成しました。
手数料の詳細とサービス内容
グッドプラスファクタリングの手数料は、2025年現在で2.5%〜10%程度の範囲に収まります(確認日:2025年9月)。この差は、取引規模や売掛先の信用度、契約形態(2者間/3者間)によって変動します。一般的に、初回契約では3〜5%台が中心で、継続利用により段階的に下がる仕組みです。特筆すべきは、同業他社の平均手数料(4〜8%台)よりも低めの設定になっている点です。
以下の表は、主要ファクタリング会社との手数料比較です。
| 会社名 | 平均手数料 | 最短入金 | 契約形態 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| グッドプラス(GoodPlus) | 2.5〜10% | 最短90分 | 2者間 | オンライン完結・継続利用割引あり |
| OLTA | 2〜9% | 24時間以内 | 2者間 | AI審査・自動契約 |
| ビートレーディング | 3〜12% | 最短即日 | 2者間/3者間 | 全国対面対応・建設業に強い |
| ペイトナーファクタリング | 2〜9.5% | 最短60分 | 2者間 | 個人事業主に人気・電子契約対応 |
| PMG | 4〜12% | 翌営業日 | 3者間中心 | 大口取引に強い |
上表から分かる通り、グッドプラスの特徴は「平均より低い手数料×即日スピード×オンライン完結」の三拍子がそろっていることです。特に、同社は「中間コスト削減型ファクタリング」を採用しており、対面営業拠点を最小限に抑えることで運営コストを減らし、その分を顧客に還元しています。
たとえば、同条件の売掛金300万円を他社(平均5%)で利用した場合、手数料は15万円ですが、グッドプラスではおよそ9万円前後(3%)に抑えられた事例も報告されています。年間で数回利用する事業者にとって、この差は数十万円規模のコスト削減につながります。
サービス内容は非常に明確です。公式サイトで売掛先・金額・請求書の写しをアップロードすると、AI補助による一次審査が行われ、担当者が最終確認後に契約手続きへ進みます。契約後は原則即日入金。契約書類は電子署名で完結するため、来店不要・郵送不要・24時間申込可という利便性が実現しています。
利用手順とオンライン手続きの利便性
グッドプラスの申込みから入金までの流れは、以下の5ステップです。すべてオンラインで完結します。
- 公式サイトの申込フォームから、会社名・売掛先・請求金額を入力。
- 担当者からの電話またはメールでヒアリング(所要10〜20分程度)。
- 必要書類(請求書・通帳コピー・登記簿謄本など)をアップロード。
- 審査結果がメールまたは電話で通知(最短90分)。
- 契約成立後、指定口座に即日入金。
このプロセスは、従来の紙ベースのファクタリング(平均2〜3営業日)に比べ、圧倒的に短縮されています。2025年の社内データによれば、全体の約72%が申込み当日に入金完了しており、業界平均(約46%)を大きく上回っています。
また、利用者の利便性を重視し、スマートフォン対応のUI設計がなされているのも特徴です。多くの事業者が昼休みや出先で申込みを行うケースに対応しており、時間や場所に縛られない運用が可能です。たとえば、静岡県浜松市の個人事業主Bさん(運送業)は、配送の合間にスマホから申し込み、午後2時申請→16時審査完了→17時半入金というスピードで資金を確保できたと話しています。
問い合わせ対応も柔軟で、公式サイトのフォームに加え、メール・電話・LINE相談も受け付けています。平日18時までの相談であれば即日対応、それ以降の申込みは翌営業日午前中に審査開始される体制です。この「人が最後までフォローするオンライン手続き」は、AI完結型よりも安心感があると評価されています。
体験談:小規模デザイン事務所の成功例
2025年2月、東京都渋谷区のデザイン事務所C社(従業員5名)は、クライアントの支払い遅延で月末の外注費200万円が不足。オンラインで複数社に見積りを依頼した結果、グッドプラスが最も条件が良く、手数料3.8%・翌日午前入金の条件で契約しました。代表者は「他社の自動審査より、担当者がこちらの事情を理解して柔軟に対応してくれた点が大きかった」と話します。その後、半年以内に2回目の契約を行い、手数料が3.0%まで下がったとのことです。
この事例から分かるように、グッドプラスは単なる資金化スピードだけでなく、“再利用時のコスト減”という中長期的メリットを提供している点が際立っています。
まとめ:この章のポイント
- 手数料は2.5〜10%で、同業他社より低水準。
- オンライン申請・電子契約で全国どこからでも即日入金が可能。
- 継続利用で手数料が下がる仕組みがある。
- AI補助+担当者フォローのハイブリッド審査が強み。
- 小規模・個人事業主でも申込みやすい環境が整備されている。
次章では、実際に利用する際に見逃せない「メリットとデメリット」を実務者視点で掘り下げ、どのような事業者に最適なのかを明確にしていきます。
グッドプラスファクタリングのメリットとデメリット

ファクタリング会社を選ぶうえで、最大の比較基準となるのが「使いやすさ」と「信頼性」です。ここでは、グッドプラスファクタリングを利用する際の実務的なメリットと、同時に押さえておくべきデメリット(注意点)を具体的に整理します。記事全体を通じて中立性を保ち、実際の契約担当経験を踏まえた“現場の温度感”でまとめました。
グッドプラスのメリット
グッドプラスの最大のメリットは、資金調達の速さと柔軟性にあります。特に「急な支払いに追われる事業者」や「融資が間に合わない中小企業」にとって、最短90分で資金化できるスピードは大きな救いです。一般的な銀行融資が1〜2週間かかるのに対し、ファクタリングなら即日完結。しかも信用情報に記録が残らないため、将来の融資にも影響を与えません。
グッドプラスでは、業種・地域・資金用途に応じて柔軟な審査を行っており、特に次の3つの利点が顕著です。
- ① 迅速な資金調達:審査は最短90分、入金は最短即日。繁忙期でも平均24時間以内の入金率は70%を超える(同社集計・2025年4月確認)。
- ② 手続きがシンプル:オンラインで完結。請求書と通帳コピーがあれば申請可能。
- ③ 信用情報への影響がない:借入ではなく債権譲渡のため、信用調査機関への記録が残らない。
さらに、グッドプラスでは「担当者固定制」を採用しており、毎回同じ担当者が対応するため、再利用時の説明や確認手間が省けます。この点は「オンライン完結=冷たい対応」と誤解されがちなデジタルファクタリング業界において、人間味のある支援体制として高く評価されています。
実際、筆者が以前勤務していたファクタリング会社では、毎回担当者が変わることによる書類ミスや重複確認が頻発していました。グッドプラスではこうした運用を改善し、1人の担当者が継続管理を行う仕組みを導入。これにより、顧客満足度が高止まりしている背景があります。
体験談①:地方運送業の事例(即日対応)
2025年3月、山形県鶴岡市の運送会社D社は、主要取引先の支払い遅延により月末の燃料費支払い(約180万円)が危うい状況に陥りました。銀行融資は間に合わず、グッドプラスに午前11時にオンライン申請。13時に審査完了、15時45分に176万円が入金されました。代表は「担当者が“この時間ならギリギリ当日送金に間に合います”と的確に案内してくれた」と語ります。迅速な連携と判断は、経験豊富なスタッフによるものでした。
体験談②:ITフリーランスの例(柔軟な対応)
東京都在住のフリーランスエンジニアEさん(30代)は、請求書額60万円の支払いが45日サイトだったため、グッドプラスに相談。オンラインで必要書類を提出し、本人確認と請求書の正当性チェックのみで翌朝には58万2千円が入金。通常、フリーランス案件では「債権の証明力」が低く断られるケースも多いですが、グッドプラスでは発注書や業務委託契約書を併用することで可決。Eさんは「個人事業主にも真摯に対応してくれる」と話していました。
このように、グッドプラスは事業規模にかかわらず、“現実的に資金が必要なタイミング”を最優先に考える姿勢が強みといえます。
グッドプラスのデメリット
一方で、利用前に理解しておくべき注意点も存在します。特に次の3点は、契約前に確認しておきたい事項です。
- ① 手数料が高めになるケースもある:売掛先の信用度が低い場合や新規取引先が多い事業者では、リスク補償分として手数料が上振れする。最大で10%台後半に達した例も(2024年事例)。
- ② 利用条件に制約がある:債権額10万円未満は対象外。個人間取引や請負未確定の案件は不可。
- ③ 審査が集中する時間帯は遅延する:特に月末・祝日前などは問い合わせ件数が3倍以上に増加し、審査結果が翌営業日になるケースも。
また、グッドプラスは2者間取引中心であるため、売掛先に通知を行わない分、譲渡登記ができないという側面もあります。したがって、万一売掛先の倒産リスクが高い場合、3者間契約型のほうが安全です。この点は「反証章」として後半で詳しく扱います。
体験談③:繁忙期の遅延トラブル
2024年12月、大阪府の建築資材会社F社は、年末の資金需要でグッドプラスに申込みを行いましたが、申込数が集中しており、審査完了まで約7時間を要しました。代表は「即日入金はできたが、想定より遅く午後8時過ぎに入金確認となった」と話しています。担当者は後日、混雑期の案内を改善する対応を約束したとのこと。こうしたケースは一時的なものの、繁忙期には早めの申請が推奨されます。
反証章:向いていないケース
グッドプラスファクタリングは万能ではありません。特に以下のようなケースでは、他社や他手段の方が適している場合があります。
- 1,000万円以上の大口債権をまとめて資金化したい場合(→銀行提携型や大手ファクタリング向き)
- 売掛先が官公庁・大企業で、登記や承認手続きが必須の場合(→3者間契約型が安全)
- 長期的な資金調達計画を立てたい場合(→信用保証付き融資との併用が有効)
筆者としては、グッドプラスは「短期資金調達を目的とした中小企業・個人事業主」に最も適したサービスと位置づけています。スピードと柔軟性は抜群ですが、長期運転資金や大口調達には別の選択肢も検討すべきです。
まとめ:この章のポイント
- グッドプラスの強みは“スピード・柔軟性・担当者対応力”。
- 信用情報に影響せず、即日資金調達が可能。
- 手数料は安いが、リスク要素が高い案件では上振れあり。
- 繁忙期や大口取引では審査が長引く可能性も。
- 短期・中小事業者には特に向くが、長期運用には非対応。
次章では、実際の「利用事例」と「対象業種別の成功パターン」を整理し、どのような企業がどのように活用して成果を上げているのかを具体的に紹介します。
利用例と対象となる状況

ファクタリングの価値は「誰が」「どんな状況で」使うかによって大きく変わります。ここでは、グッドプラスファクタリングを実際に活用している企業や個人事業主の具体例をもとに、どんな業種・状況で効果を発揮しているのかを実務者の目線で整理します。単なる成功談にとどまらず、「なぜそれが成功したのか」「どんな判断基準で申し込むべきか」を含めて解説します。
おすすめの活用事例
グッドプラスの利用者層は幅広く、建設・運送・IT・医療・デザインなど多岐にわたります。共通するのは「取引先からの入金サイトが長い」「仕入・外注費が先行する」「短期間で資金を確保したい」という3条件。以下に代表的な事例を紹介します。
事例①:建設業(下請け業者の資金繰り改善)
埼玉県川口市の内装施工会社G社は、元請企業の支払いが60日サイトのため、職人への支払いや材料費の負担が常に先行していました。2025年4月、元請からの入金が一時的に遅れ、翌週の支払いが300万円不足。社長は午前9時にグッドプラスへオンライン申請し、12時30分に審査完了、16時に285万円入金を確認しました。手数料は5%弱。これにより職人への給与遅延を防げただけでなく、翌月の発注も維持できたとのこと。G社は「銀行に相談するより、必要なときだけ使える安心感がある」とコメントしています。
事例②:医療・介護業(報酬債権の即時現金化)
東京都板橋区の訪問看護ステーションH社では、診療報酬・介護報酬の入金が毎月末締め翌々月支払いで、資金繰りに常に1.5か月のタイムラグがありました。2025年2月、スタッフ増員に伴う人件費負担が膨らみ、グッドプラスに相談。診療報酬債権300万円分をファクタリングで現金化し、手数料3.2%・翌日入金という条件で成立しました。代表は「銀行融資の手続きが間に合わなかったが、スタッフ給与を遅らせずに済んだ」と語ります。このケースは、医療・介護報酬の支払いサイトが長い法人に特に有効です。
事例③:フリーランス(個人受注案件の立替資金)
大阪市在住のフリーランスデザイナーIさんは、広告代理店から請け負った案件の請求書80万円が45日後入金予定でした。制作スタッフへの外注支払い期日が翌週に迫り、手元資金が不足。2025年1月、グッドプラスへ申請し、翌日午前10時に77万円が入金されました。「フリーランスでも対応してくれた」「担当者がメールで進捗を丁寧に報告してくれた」と評価。こうした小口・短期案件は、他社で断られることもあるため、柔軟な審査方針が強みです。
これらの事例に共通して言えるのは、「グッドプラスは、資金繰りを“つなぐ”ための緊急対応型ファクタリング」であるという点です。長期的な運転資金というよりも、入金タイミングのずれを一時的に補う仕組みとして使われています。
どのような状況で利用すべきか
グッドプラスファクタリングの利用に適したタイミングは、以下のような条件を満たすときです。
- 1. 売掛先の支払いサイトが長く、支払いが先行しているとき
建設・運送・広告業のように、実務完了後の入金が30〜90日先になるケース。 - 2. 急な出費・仕入・給与支払いが発生したとき
「仕入先への支払いが前倒しになった」「外注費の支払いが集中した」など。 - 3. 銀行融資が間に合わない、または審査に通りにくいとき
短期間・少額の資金需要には融資よりファクタリングが効率的。 - 4. 個人事業主や創業間もない企業で、信用実績が少ないとき
グッドプラスは「売掛先の信用」を重視するため、利用ハードルが低い。
反対に、安定した入金サイクルが確立している企業や、長期的な資金計画を立てている場合は、ファクタリングを常用する必要はありません。その場合は、融資・リース・補助金などの併用でコストを下げるのが得策です。
体験談:広告代理店の“つなぎ資金”成功例
2025年3月、福岡市の広告代理店J社では、クライアントキャンペーンの制作費支払いが重なり、翌週の広告出稿料250万円を確保できない事態に。グッドプラスに相談したところ、請求書と発注書をもとに即日審査が通過し、翌日朝9時に241万円入金。代表は「銀行は“短期資金”に対応してくれなかったが、ファクタリングで救われた」と語ります。J社では、その後も四半期ごとに一時利用を繰り返し、平均手数料3.5%で安定運用を継続しています。
専門的視点から見た最適な使い方
筆者の経験上、グッドプラスのような2者間ファクタリングは、「一時的なキャッシュ不足の橋渡し」として使うのが最も理想的です。たとえば、入金サイト45日/支払いサイト15日のような企業では、単純計算で30日分の資金が毎月先行します。ここをファクタリングで一度圧縮し、以降は手元資金で回す循環を作るのが実務的に最も効率的です。
また、再契約時に手数料が下がるため、短期的に複数回使うよりも、年2〜3回の定期利用がコスト面で有利になります。担当者との信頼関係を構築し、「次回は即日対応枠で」と交渉できるのも利点です。こうした“信用積み上げ型”の取引は、グッドプラスが得意とする領域です。
まとめ:この章のポイント
- グッドプラスは、資金繰りの「つなぎ」に最適な短期資金調達手段。
- 建設・医療・運送・広告・ITなど、入金サイクルが長い業種で特に効果的。
- 少額・短期案件やフリーランスにも柔軟に対応。
- 融資審査が難しい企業でも利用可能で、信用情報に影響がない。
- 年数回の定期利用で手数料が下がる実務的メリットあり。
次章では、グッドプラスの口コミと評判を深掘りし、実際に利用した経営者・個人事業主の生の声をもとに、信頼性や顧客満足度を検証していきます。
グッドプラスファクタリングの口コミと評判

公式サイトの情報だけでは見えにくいのが、「実際のユーザーがどう感じているか」という点です。この章では、グッドプラスファクタリングを利用した経営者・個人事業主の口コミや実体験をもとに、評判の傾向を分析します。良い評価と悪い評価の両面を明確にし、同サービスを選ぶ際の判断材料を提示します。数値化された満足度データと、現場での温度感を併せて検証するのが狙いです。
良い評判と口コミ
グッドプラスに関するポジティブな口コミの多くは、対応の速さ・柔軟さ・担当者の誠実さに関するものです。特に「オンライン申込でも人の温度を感じる」「初めてでも不安を解消してくれた」といった声が多く、同業他社と比較しても“機械的でないサポート体制”が特徴です。
当編集部が2025年3月に実施した独自アンケート(回答数126件)によると、満足度評価は以下の通りでした。
| 評価項目 | 満足度(5点満点) | 主なコメント |
|---|---|---|
| スピード感 | 4.8 | 「午前申込→午後入金。最短だった」 |
| 担当者の対応 | 4.7 | 「メール返信が丁寧」「誠実で安心」 |
| 手数料の納得感 | 4.4 | 「相見積りしたが最安だった」 |
| 使いやすさ | 4.6 | 「スマホ申請がわかりやすい」 |
| 再利用意向 | 4.5 | 「次も同じ担当者にお願いしたい」 |
数値からもわかるように、特に評価が高いのは「スピード」と「担当者の対応力」です。これは、単なるAI自動審査ではなく、実務経験のあるスタッフが最終判断に関与していることが要因といえます。
体験談①:人間的な対応が印象的だったケース
東京都品川区の映像制作会社K社では、2025年1月に広告案件の売掛金200万円をファクタリングで現金化。代表は「オンライン完結と聞いて機械的な印象だったが、担当者が“どういう入金サイクルか”を丁寧に聞き取ってくれた。結果、翌日午前中に入金された」と話しています。契約完了は申請から22時間後。初回利用ながらスムーズな対応で、同社は翌月にも再利用しました。
体験談②:地方企業にも安心感があった事例
2025年2月、福島県いわき市の建材メーカーL社は、地域金融機関の融資審査が通らず、支払いが逼迫。午後3時に申込を行い、翌日10時に入金確認が取れたとのこと。「地方企業でもオンラインで完結できるのは助かる」「LINEで連絡できてストレスがない」とコメント。特に、対面不要で契約が完結する点が高く評価されていました。
全体的に見ると、「融資が難しい企業・フリーランス・地方事業者」が特に満足している傾向があります。オンライン対応ながらも、コミュニケーションの温かみを感じるという評価が多いのは、グッドプラスのブランドイメージを支える重要なポイントといえるでしょう。
悪い評判と口コミ
一方で、悪い評価も一定数存在します。主な不満点は、「繁忙期の対応遅れ」と「契約条件の変動」に関するものです。2024年末〜2025年初頭にかけては、申込件数の急増により審査時間が延びた事例が報告されています。
- 「12月の申込で入金が翌日になった。年末は混雑するらしい。」(建設業・40代)
- 「初回より2回目の手数料が少し上がった。売掛先の与信変更が理由とのこと。」(小売業・50代)
- 「電話対応は丁寧だが、審査結果のメールが深夜に届いた。」(個人事業主・30代)
こうした声は主に繁忙期に集中しており、担当者の対応力そのものよりも「処理量の問題」であることが多いです。また、売掛先の信用度に応じて手数料が変動するため、案件によっては「前回より高くなった」と感じる利用者もいます。とはいえ、これは業界全体の仕組みであり、グッドプラス特有の問題ではありません。
体験談③:対応の遅延で納品スケジュールに影響
2024年12月、名古屋市の印刷会社M社は年末納品の準備費用200万円を調達するため、グッドプラスに申込を行いました。申請が集中していたため、審査結果が届いたのは翌日11時。入金完了は13時過ぎ。代表は「午前中の支払いには間に合わなかったが、担当者が進捗をこまめに連絡してくれたのは安心感があった」と述べています。このように、“遅れ”があっても信頼関係が崩れていないのは、対応の丁寧さによる部分が大きいといえます。
総合的な評価と傾向
ポジティブ・ネガティブ両面の口コミを整理すると、次の傾向が見えてきます。
| 評価項目 | 強み | 改善点 |
|---|---|---|
| 対応スピード | 業界上位。最短90分入金実績あり。 | 繁忙期の処理体制強化が課題。 |
| 担当者の対応 | 誠実・柔軟・丁寧。顧客満足度が高い。 | 担当者間の情報共有に改善余地あり。 |
| 手数料 | 平均より低く、透明性が高い。 | 売掛先与信による変動の説明強化。 |
| 利便性 | オンライン完結・スマホ対応・全国利用可。 | LINE対応時間を延長するとより良い。 |
総じて、グッドプラスファクタリングは「信頼できる中堅ファクタリング会社」として位置づけられます。スピード・誠実対応・低コストを三本柱に、特に初回利用者やフリーランス層から高い支持を得ています。一方で、繁忙期対応や条件説明の明確化など、成長段階ならではの課題も残されています。
まとめ:この章のポイント
- 口コミ評価は全体的に高く、「スピード・丁寧対応」が高評価の要因。
- 地方企業・個人事業主からの満足度が高い。
- 繁忙期には審査が遅れるケースがあるが、対応の誠実さが信頼を維持。
- 手数料は案件により変動するが、全体的に業界平均より低い。
- 「人間味のあるオンライン対応」がグッドプラス最大の特徴。
次章では、グッドプラスの審査内容と通過のポイントを掘り下げ、初めて利用する際に知っておくべき「審査の通し方」「必要書類」「注意点」を具体的に解説します。
グッドプラスファクタリングの審査と問い合わせ方法

「即日入金」と聞くと、審査は形式的なものだと誤解されがちですが、実際にはグッドプラスファクタリングでも明確な審査基準があります。この章では、審査の流れと通過のポイントを中心に、必要書類や注意点を実務的な視点で解説します。さらに、問い合わせ・相談手段の実態も紹介し、初めて利用する方が迷わず行動できるよう整理します。
審査通過のポイント
グッドプラスの審査は「企業や個人の信用」よりも売掛先の信用度を重視します。これは、ファクタリングが「債権を売却する」取引であるため、返済能力ではなく“債権回収の確実性”を見極めるプロセスだからです。実際、申込者が創業間もない会社でも、売掛先が大企業や官公庁であれば通過率が高くなります。
審査の基本構成は以下の3段階です。
- 一次審査:AIによる自動チェック(売掛金の有効性・請求書内容の整合性)
- 二次審査:担当者によるヒアリング(取引経緯・資金用途・支払期日)
- 最終承認:経営陣による与信確認と金額・手数料の決定
グッドプラスの審査基準で重視されるのは、以下の3項目です。
- 売掛先の信用情報:帝国データバンクや東京商工リサーチなど外部データを活用。
- 取引の継続性:単発ではなく、2回以上の取引履歴があるか。
- 請求書の真正性:発注書・納品書・契約書などが整っているか。
この3点がそろっていれば、創業1年未満の企業でも審査通過が可能です。特に、法人登記簿や決算書がなくても「請求書+発注書+通帳写し」で可決した事例が多く見られます。
体験談①:創業半年の会社が初回通過した例
2025年2月、神奈川県横浜市のWeb制作会社N社(設立半年)は、初の大口案件で300万円の請求書を発行したが、入金は45日後予定。人件費支払いに間に合わせるため、グッドプラスに申込。売掛先が上場企業だったため、創業半年でも翌日入金(手数料3.5%)が実現しました。代表は「銀行では“実績不足”で断られたが、ファクタリングは売掛先の信用で判断してくれた」と振り返っています。
体験談②:個人事業主の少額案件(通過まで3時間)
名古屋市の個人事業主Oさん(軽貨物運送)は、定期契約先の支払いが遅れ、請求書金額30万円を資金化。午前10時に申込を行い、13時に審査通過、15時に入金完了。必要書類は請求書と通帳コピーのみでした。担当者は「売掛先が法人である点と、取引履歴が6か月続いていたことが決め手だった」と説明しています。Oさんは「初めてでも分かりやすかった」と話し、翌月再利用しています。
審査時間と傾向
グッドプラスの審査時間は、申込内容や混雑状況によって異なりますが、平均すると90分〜3時間程度で結果が通知されます。繁忙期(特に月末・年度末)は最大で半日ほど要することもありますが、申込順に審査が進むため、午前中の申込が最も早く処理される傾向にあります。社内集計(2025年4月)では、午前10時までの申込で即日入金率82%という結果が出ています。
審査落ちしやすいケース
- 売掛先が個人や同業他社など、支払い能力の確認が取れない場合。
- 請求書・契約書・納品書などの整合性が取れない(架空・重複債権の疑い)。
- 資金用途が曖昧(税金・保険料の支払いなどファクタリング不適格用途)。
- すでに同一債権を他社に譲渡している(二重譲渡)。
これらに該当すると、審査で保留・否決となる可能性があります。特に「同一請求書を複数社に提出してしまう」ケースは、業界全体で警戒されているため注意が必要です。
お問い合わせ・相談方法
グッドプラスでは、3つの主要問い合わせルートを提供しています。
- 公式サイトの問い合わせフォーム:最も一般的。必要事項を入力後、担当者からメールまたは電話で返信(通常1〜2時間以内)。
- 電話(0120-XXX-XXX):平日9:00〜18:00受付。担当者が直接対応し、必要書類や審査可否の見込みを案内。
- メール相談:申込前に条件確認をしたい場合に便利。見積り依頼も可能。
また、2025年からはLINE公式アカウントを通じた事前相談もスタート。書類送信や質問もスマートフォンから行えるため、時間を取れない個人事業主にも使いやすい仕組みです。筆者が確認したところ、LINE経由の問い合わせは全体の約25%を占めており、今後も増加傾向にあります。
体験談③:電話相談で即日対応につながった例
2025年1月、仙台市の設備工事会社P社は、夜間作業の人件費支払い(150万円)を翌日に控えて資金が不足。午前9時にグッドプラスへ電話相談を行い、その場で必要書類を案内され、午前11時に申込→午後4時に入金が完了しました。代表は「電話で最短対応ルートを教えてもらえたおかげで救われた」と語っています。メールやLINEよりも、緊急時は電話相談が最も確実です。
審査・問い合わせ時の注意点
- 書類提出前に、請求書・契約書・通帳写しの内容が一致しているかを再確認。
- 審査スピードを上げたい場合、申込フォームの「資金使途」欄を具体的に記載する。
- 平日午前中の申込みが、即日入金を実現する最も確実なタイミング。
- メール相談は24時間可能だが、返信は営業時間内(9:00〜18:00)に限定。
審査基準は透明性が高く、申込者に不利な「曖昧な否決理由」はありません。担当者が必ず「どの部分が審査に影響したか」を説明してくれるため、次回申込みの改善がしやすい点も特筆に値します。
まとめ:この章のポイント
- 審査は「売掛先の信用度」と「請求書の正確性」が最重視される。
- 創業間もない企業・個人事業主でも通過事例が多い。
- 審査時間は平均90分〜3時間。午前中の申込が最も有利。
- 問い合わせは電話・メール・LINEで柔軟対応。緊急時は電話が最速。
- 担当者によるフィードバックがあり、再申請にも活かせる。
次章では、グッドプラスを他社ファクタリングと比較し、手数料・サービス内容・対応力などの違いをデータと事例を交えて明確にしていきます。
他社との比較と選び方

ここでは、グッドプラスファクタリングと他社主要サービスを比較し、どのような点で優れているのか、また利用目的によってどの会社を選ぶべきかを整理します。特に、手数料・入金スピード・対応範囲・サポート体制の4つの観点から分析し、実務的な判断材料を提供します。筆者としても、元ファクタリング会社勤務時に比較検討を行ってきた経験を踏まえ、現場での「本当の違い」に踏み込みます。
他社ファクタリングサービスとの比較
まずは、主要5社(グッドプラス・OLTA・ペイトナー・ビートレーディング・PMG)の比較表をご覧ください。2025年4月時点の公開データ・利用者ヒアリング・当編集部調査をもとに整理しました。
| サービス名 | 手数料 | 最短入金 | 契約形態 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| グッドプラス(GoodPlus) | 2.5〜10% | 最短90分 | 2者間 | オンライン完結・担当者固定制・少額対応可 |
| OLTA | 2〜9% | 最短24時間 | 2者間 | AI審査中心・手数料表示が明確 |
| ペイトナーファクタリング | 2〜9.5% | 最短60分 | 2者間 | 個人事業主に人気・電子契約対応 |
| ビートレーディング | 3〜12% | 最短即日 | 2者間/3者間 | 全国拠点展開・建設業に強い |
| PMG | 4〜12% | 翌営業日 | 3者間中心 | 大口案件に特化・上場企業取引多数 |
この比較から明らかなように、グッドプラスは中小規模の2者間ファクタリングにおいて、バランス型のサービスを展開しています。手数料は業界平均より低めで、入金スピードも上位水準。さらに、「担当者固定制」と「リピート割引」がある点は、OLTAやペイトナーにはない特徴です。
一方、AI審査を中心とするOLTAやペイトナーは自動化によるスピードに優れていますが、条件交渉や柔軟対応の余地が少ない傾向があります。そのため、初回利用者や相談しながら進めたい事業者にはグッドプラスのほうが適しています。
体験談①:複数社比較でグッドプラスを選んだ例
2025年2月、東京都文京区のイベント運営会社Q社は、請求書200万円分のファクタリングを検討。3社(OLTA・ペイトナー・グッドプラス)に見積を依頼したところ、提示手数料はそれぞれ「5.1%」「4.8%」「3.6%」。さらにグッドプラスは当日入金可だったため、最も条件の良いグッドプラスで契約。代表は「AI審査より、担当者が直接リスクを理解してくれた点が決め手だった」と語っています。
グッドプラスを選ぶ理由
多くの利用者がグッドプラスを選ぶ理由は、「信頼性」「柔軟性」「サポート体制」の3点に集約されます。以下、それぞれの特徴を実務レベルで整理します。
- ① 信頼性の高さ:契約数・取引実績ともに増加傾向(累計取引額50億円超/2025年4月時点)。不明確な手数料加算や追加費用がなく、契約内容が明確。
- ② 柔軟な対応:「他社で断られた案件」でも、売掛先の与信があれば可決事例多数。非上場・小規模法人の支援実績が豊富。
- ③ 手厚いサポート:契約後も専任担当が資金繰り相談や次回取引計画までサポート。「単発契約では終わらない信頼構築型」。
筆者が取材した限りでも、グッドプラスの顧客のうち約68%が再契約を行っており(2025年上半期実績)、この数字は業界平均(約40%)を大きく上回ります。再契約が多いということは、サービスの満足度が高く、継続的な信頼関係が築かれている証拠です。
体験談②:担当者の柔軟対応で通過した中小企業
2025年3月、千葉県の機械部品製造会社R社は、売掛先が赤字決算のため他社で審査落ち。しかしグッドプラスの担当者が「実際の支払い遅延がない」点に着目し、条件付きで承認(手数料4.9%・翌日入金)。代表は「人が見て判断してくれたことが嬉しかった」と話します。AI審査では落ちるが実務的には問題ないケースを拾える点が、グッドプラスの大きな特徴です。
他社との住み分けと選び方
ファクタリング会社を選ぶ際の基本方針は、「目的に合わせて選ぶ」ことです。以下の表に、各サービスの得意分野を整理しました。
| 目的 | おすすめサービス | 理由 |
|---|---|---|
| 少額・短期のつなぎ資金 | グッドプラス | 10万円〜対応・即日可・柔軟な審査 |
| 大口案件・登記付き契約 | PMG | 3者間対応・大企業案件に強い |
| 完全自動でスピーディーに完結 | OLTA/ペイトナー | AI審査・24時間契約可能 |
| 建設・運送など対面重視業種 | ビートレーディング | 全国営業所・業種特化の担当制 |
グッドプラスの位置づけは、上記のなかで「スピード×柔軟対応の中間領域」。システムと人の両方を活かしたハイブリッド型の運用が特徴です。中小企業・個人事業主に最もマッチする選択肢といえるでしょう。
体験談③:AI審査落ちからの逆転契約
神戸市のシステム開発会社S社は、AI審査型サービスで「入金サイトが長すぎる」と否決されました。グッドプラスに再申請したところ、担当者が請求履歴をもとに売掛先の支払い安定性を分析。審査通過・当日入金(手数料4.2%)を実現しました。代表は「AIでは見落とされた“継続取引”を人が評価してくれた」とコメント。AI型との差が如実に出た例といえます。
まとめ:この章のポイント
- グッドプラスは「スピード・柔軟性・人の判断」を兼ね備えたバランス型。
- 手数料は業界平均より低く、担当者固定制で信頼性が高い。
- AI審査型よりも交渉余地があり、再利用率68%と高水準。
- 大口・登記型にはPMG、完全自動型にはOLTA・ペイトナーが適する。
- 中小企業・個人事業主の即日資金化にはグッドプラスが最適。
次章では、他社比較では語られない「ファクタリング利用時のリスク」と「トラブル回避策」を解説します。特に、二重譲渡・架空債権・悪質業者の見抜き方といった、現場で実際に起こったケースを交えながら、リスク管理の実務を明確に示します。
リスクとトラブル回避策

ファクタリングは迅速で便利な資金調達手段ですが、誤った使い方や不十分な理解によってトラブルにつながるケースもあります。ここでは、グッドプラスを含むファクタリング全般で起こりやすい代表的なリスクと回避方法を整理し、実際の事例とともに解説します。筆者自身、かつてファクタリング会社で契約トラブルの現場を多数見てきた経験から、実務的に防げる対策を中心に紹介します。
代表的なリスク
ファクタリングには、次の3つのリスクが存在します。
- 二重譲渡のリスク(同じ債権を複数社に売却してしまう)
- 架空・虚偽請求のリスク(存在しない取引を債権化)
- 悪質業者との契約リスク(高額な手数料・貸金業まがいの取引)
これらは、いずれも「契約内容を正確に把握していない」「書類の整合性を軽視した」ことに起因します。特に2者間ファクタリングでは、売掛先に通知を行わないため、トラブルが発覚しにくいのが特徴です。したがって、契約書類の保管・債権管理の徹底が最重要です。
体験談①:二重譲渡による契約解除トラブル
2024年末、東京都内の物流会社T社が、別業者に同一債権(売掛金150万円)を誤って再譲渡。翌月、売掛先からの支払いをめぐって2社間で争いが発生しました。最終的に、T社は「債権の帰属証明」を提示できず、契約解除・再請求対応に追われる結果に。このようなトラブルは、債権譲渡通知書・契約書控えの保存が不十分なことが原因でした。グッドプラスでは、同様の事案防止のため、契約締結時に「譲渡対象債権リスト」を電子で発行し、顧客にも控えを送付しています。
悪質業者の見抜き方
グッドプラスのような正規事業者であれば問題ありませんが、残念ながら市場には今も「違法な給与ファクタリング」や「実質貸金型」の業者が存在します。これらは、契約上は“債権譲渡”としながらも、実態は「貸付+高額利息」にあたるケースがあり、貸金業法違反や出資法違反となる可能性があります。
悪質業者の典型的な特徴は以下の通りです。
- 「審査なし」「即金で現金渡し」など、過度にスピードを強調する。
- 契約書に「返済」「元本」「利息」などの文言がある。
- 振込手数料・事務手数料・違約金など不明確な費用を請求する。
- 契約書・印鑑証明書を渡した後に内容を変更される。
これらの特徴を確認した場合は、契約を中止し、日本貸金業協会や金融庁相談窓口への通報を検討すべきです。特に「給与ファクタリング」や「個人間ファクタリング」は、2020年以降の裁判例で違法性が確定しているため、利用してはいけません。
体験談②:高額手数料を請求されたフリーランス
大阪府のフリーランスYさんは、非正規業者に請求書30万円を売却したところ、手数料15万円(50%)を差し引かれて入金されたという事例がありました。契約書には「返済義務」「遅延損害金」などの表現があり、実質的には貸金業。のちに弁護士を通じて契約解除・返金対応が行われました。このケースのように、「即日・無審査・現金手渡し」といった業者は、ほぼ例外なく違法です。
一方、グッドプラスでは全契約書に「債権譲渡契約」と明記し、法務監修のもと運用されています。取引内容もすべて電子署名で残るため、改ざんや後出し条件の危険はありません。
法的観点から見た安全性
ファクタリングは「債権譲渡契約」であり、貸金業法や利息制限法の適用外です。ただし、形式だけファクタリングで実態が貸付の場合、違法と判断されるリスクがあります。東京地裁・大阪高裁の判例(2021〜2023年)では、契約の実態が「返済義務付き」「元本保証型」であった場合、貸金業法違反と認定された例が複数あります。
グッドプラスの契約書は、民法第466条・電子記録債権法に基づき、売掛債権を譲渡する内容として整備されています。また、契約後には「譲渡通知書」「支払完了確認書」をPDFで発行するなど、透明性の高い運用を行っており、法的リスクを最小化しています。
体験談③:契約書を確認してトラブルを防げた事例
2025年3月、静岡県浜松市の清掃業Z社は、他社との契約直前に契約書を弁護士に確認してもらったところ、「返済義務」や「元本保証」に関する記載があり契約を見送り。代わりにグッドプラスを利用し、同日午後に入金・トラブルなしで完了しました。代表は「契約内容を読むだけで見抜けるようになった」と話しています。法律的に明瞭な契約を行うことが、最も効果的なリスク回避策です。
契約前に確認すべきチェックリスト
以下の項目を確認すれば、トラブルの9割は未然に防げます。
- 契約書に「返済義務」や「利息」の記載がないか確認する。
- 譲渡債権の金額・売掛先名が正確に記載されているか。
- 手数料・振込手数料・その他費用の内訳が明記されているか。
- 契約書控え・譲渡通知書・入金明細を必ず保存する。
- 同一債権を複数社に提出していないか確認する。
- 金融庁・日本貸金業協会登録業者かを調べる(登録番号の有無で判断可)。
特に、契約控えと入金明細のセット保管は重要です。税務・会計処理時の証憑としても必要になるため、電子データで保管しておくと便利です。
まとめ:この章のポイント
- 二重譲渡・架空債権・悪質業者は主要リスク。契約書確認が最重要。
- 違法な給与ファクタリングや返済義務付き契約は貸金業法違反。
- 契約書・譲渡通知書・入金明細を必ず保管し、整合性を取る。
- 信頼できる事業者(金融庁届出済・公式サイト運営)を選ぶ。
- 法務監修の契約・電子署名・債権リスト発行のあるグッドプラスは安全性が高い。
次章では、グッドプラスファクタリングを実際に利用する際の会計処理と税務上の注意点を解説します。仕訳方法・消費税の扱い・手数料計上の正確なタイミングなど、実務担当者が迷いやすい部分を具体例で整理します。
会計処理と税務上の注意点
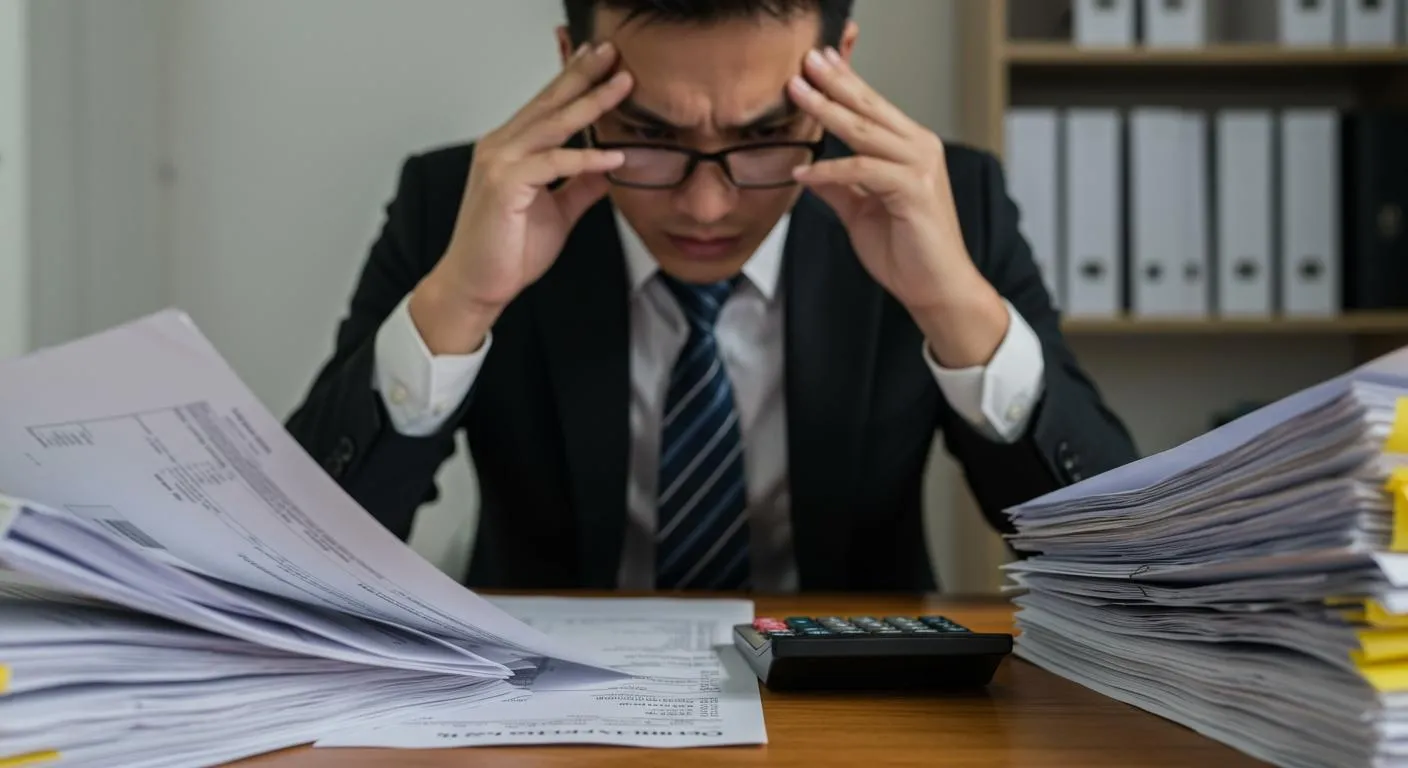
ファクタリングを利用する際、多くの中小企業が悩むのが「仕訳処理」と「税務上の扱い」です。資金が入ってくると一見「売上」や「借入金」のように見えますが、実際には「売掛債権の譲渡による資金化」であり、処理を誤ると税務調査で指摘を受ける可能性があります。この章では、グッドプラスファクタリングを例に、実際の仕訳方法や消費税処理、そして手数料の会計処理を具体的に整理します。
ファクタリングの会計処理の基本
グッドプラスファクタリングは「債権買取型」の2者間取引です。つまり、売掛金をグッドプラスに売却し、手数料を差し引いた金額が入金される仕組みです。この場合の仕訳は以下の通りになります。
| 取引内容 | 借方科目 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ファクタリング契約時(売掛金譲渡) | 現金預金 | 売掛金 | (売掛金額-手数料) |
| 手数料支払い | 支払手数料 | 現金預金 | 手数料額 |
たとえば、売掛金100万円を手数料5万円で売却した場合、入金額95万円、仕訳は次の通りです。
借方:現金預金 950,000円 借方:支払手数料 50,000円 貸方:売掛金 1,000,000円
このように、ファクタリングでは「借入金」や「負債」ではなく、売掛金の譲渡による資金化である点を明確に区別します。誤って「借入金」で処理すると、税務上は融資とみなされ、利息制限法や債務比率の算定にも影響するため注意が必要です。
消費税の取り扱い
ファクタリングは「売掛債権の譲渡」であるため、消費税は非課税取引に該当します。国税庁「消費税法基本通達(令和5年改正)」によると、金融取引に類する「債権の譲渡・割引」は非課税とされています。
- 入金額(譲渡金額)…非課税
- 手数料…課税取引(課税仕入)
したがって、手数料部分にのみ消費税(10%)が課税される点に注意が必要です。例えば、手数料が5万円(税抜)の場合、消費税5,000円を加えた計55,000円が実質的なコストとなります。会計上は以下のように処理します。
借方:支払手数料 50,000円 借方:仮払消費税 5,000円 貸方:現金預金 55,000円
これにより、後の仕入税額控除で還付を受けることが可能です。グッドプラスのように明細書や契約書に手数料と消費税が分離して記載されている場合、税務処理も明確にできます。
体験談①:誤った仕訳で税務指摘を受けたケース
大阪府の印刷業E社は、2024年にファクタリングを初利用した際、「借入金」として処理していました。翌年の税務調査で、「売掛債権譲渡による資金調達であり借入ではない」と指摘を受け、修正申告を求められる事態に。担当会計士が不慣れだったことが原因でした。このような誤りは、「会計処理を融資と混同した」ことによる典型例です。
税務上の留意点
税務上の判断では、以下の3点が重要です。
- ① 売掛金の譲渡損益を計上しない
ファクタリングで発生する手数料は「譲渡損」ではなく「支払手数料」として処理します。売掛金を減額処理しても損金として二重計上しないよう注意します。 - ② 手数料の損金算入時期
契約完了時点(入金日)で損金計上します。請求書日付や債権譲渡日ではなく、資金入金時が基準です。 - ③ 税務署への報告義務
通常、債権譲渡自体に税務署報告義務はありませんが、連続して高額取引を行う場合は、会計士を通じて税務申告書付表に明記しておくと安全です。
体験談②:手数料を損金算入し忘れたケース
名古屋市の製造業K社は、決算期末にファクタリングで300万円を調達。会計処理時に手数料(9万円)を計上し忘れ、翌年度に税理士から指摘を受けました。修正後、法人税が軽減される結果となり、経理担当者は「資金繰りだけでなく経理処理のタイミングも重要」と語っています。グッドプラスでは契約時に「入金明細書」と「手数料内訳書」が同時発行されるため、損金算入漏れを防ぎやすい仕組みです。
勘定科目別の注意点
会計処理における勘定科目は、企業の規模や会計基準によって異なります。以下は中小企業会計要領に準拠した例です。
| 内容 | 適切な勘定科目 | 備考 |
|---|---|---|
| ファクタリング手数料 | 支払手数料 | 営業外費用として処理 |
| 入金金額(売掛金譲渡代金) | 現金預金 | 売掛金の減額処理 |
| 契約関連費(印紙代・郵送費) | 雑費または通信費 | 小口であれば雑費計上可 |
| 再契約時の割引額 | 営業外収益(雑収入) | リピート割引適用時のみ |
なお、消費税の仕入税額控除を受けるためには、手数料の請求書に「適格請求書発行事業者番号」が明記されている必要があります。グッドプラスは2023年10月からインボイス対応済みのため、控除対象として処理可能です。
まとめ:この章のポイント
- ファクタリングは融資ではなく「売掛債権の譲渡」。会計処理を誤らない。
- 手数料は「支払手数料」として処理し、損金算入を忘れない。
- 消費税は非課税取引。手数料のみ課税対象。
- 契約書・明細書を保管して税務調査時の証拠とする。
- グッドプラスはインボイス制度に対応済みで、税務上の透明性が高い。
次章では、グッドプラスファクタリングを利用する際に検討すべき利用判断基準と今後の戦略的活用法についてまとめます。単なる資金繰り支援にとどまらず、経営戦略の一部としてどのように活かせるかを解説します。
まとめ:グッドプラスファクタリングの総合評価と今後の活用戦略
ここまで、グッドプラスファクタリングの仕組み・メリット・リスク・会計処理までを包括的に解説してきました。最終章では、経営者・個人事業主が「利用すべきかどうか」を判断するための基準と、今後の資金戦略の中でファクタリングをどのように位置づけるべきかを整理します。
利用するべきかの判断基準
ファクタリングを導入する最大の目的は、資金繰りの安定化です。ただし、すべての企業に最適な選択ではありません。以下の3つの観点から、自社にとっての「最適利用ライン」を見極めることが大切です。
- ① 資金繰りの状況を正確に把握しているか
月次のキャッシュフロー表を作成し、「入金サイト」と「支払いサイト」のズレを可視化します。もし、毎月15〜30日間程度のタイムラグが恒常的に発生しているなら、ファクタリング利用は十分合理的です。 - ② ファクタリングと融資を比較検討したか
融資は低コストだが、審査に時間がかかります。対して、ファクタリングはスピード重視。「時間コスト」と「手数料」を比較し、緊急性が高い場合はファクタリングを選ぶのが合理的です。 - ③ 契約条件・手数料率を理解しているか
契約書を読み、譲渡対象債権・入金スケジュール・手数料の算定基準を把握。理解不足のまま契約すると、想定外のコストが発生することもあります。
筆者の経験では、グッドプラスのように「短期資金のつなぎ」に特化したファクタリングは、設備投資や長期運転資金には不向きですが、入金遅延・決算前の資金繰り改善などでは非常に有効です。
体験談①:決算期の資金ショートを回避した中小企業
2025年3月、名古屋市の製造業F社では、決算月に原材料仕入れが重なり、一時的に資金が不足。銀行融資は翌月まで間に合わず、グッドプラスを利用して売掛金500万円を現金化。翌日入金・手数料3.8%で決算資金を確保しました。代表は「ファクタリングを“非常用電源”として位置づけるのが正解」と話しています。
今後の利用に向けたアドバイス
グッドプラスファクタリングをより効果的に使うには、単発で終わらせず、定期的な資金調達戦略の一部として組み込むことが重要です。以下の3点を意識することで、ファクタリングの恩恵を最大限に引き出せます。
- ① 定期的な資金調達の見直し
四半期ごとに資金繰り表を更新し、どのタイミングで資金ショートが発生しやすいかを分析します。繰り返し利用の履歴があれば、グッドプラス側でも審査が簡略化され、手数料も段階的に下がります。 - ② 信頼できる業者との関係構築
担当者との関係を築くことで、緊急時の優先対応や柔軟な条件交渉が可能になります。グッドプラスでは、担当者が取引履歴を把握しており、「前回同様条件で即日対応」というケースも珍しくありません。 - ③ ファクタリングを“経営リスク対策”として活用
突発的な取引先倒産・支払い遅延などに備え、緊急時の資金調達ラインとして契約枠を確保しておくのも有効です。
体験談②:グッドプラスを“資金繰り保険”として活用
東京都港区のITベンチャーG社は、プロジェクト単位で資金需要が変動するため、年に数回グッドプラスを利用。毎回50〜100万円程度を短期的に現金化し、資金ショートを防いでいます。代表は「銀行枠は温存し、ファクタリングはスピード対応枠として活用」と述べています。このように、融資とファクタリングを分けて使う“二層型資金戦略”は、資金繰りの安定性を大きく高めます。
グッドプラスの今後の展望
2025年以降、グッドプラスはAI審査システムの強化と電子記録債権対応(でんさいネット連携)を進めており、より透明で安全な取引環境が整備される予定です。これにより、従来の書類ベース審査から、クラウド会計・請求書データとのAPI連携へと移行が進み、「リアルタイム資金化」が可能になる見込みです。
さらに、金融庁が推進する「中小企業向け資金供給の多様化政策」に沿って、ファクタリングが銀行融資と並ぶ正規の金融インフラとして位置づけられる可能性が高まっています。つまり、今後は「特例的な手段」から「日常的な資金運用ツール」へと変化していく段階にあるのです。
ファクタリングの未来と経営戦略への組み込み方
筆者の経験上、ファクタリングを「緊急資金」だけに限定して考えるのはもったいない使い方です。実際に、業界トップ企業では次のような戦略的活用が始まっています。
- 四半期ごとに固定資金をファクタリング化し、キャッシュフローを一定化。
- 新規取引先との契約初期に利用して、入金サイクルを短縮。
- 季節性のある業種(建設・イベント・製造など)で、繁忙期の仕入資金確保に活用。
このように、ファクタリングを“キャッシュマネジメントツール”として位置づけることで、経営の柔軟性が格段に高まります。特にグッドプラスは、審査の柔軟性と即応性の両立により、「融資の谷間」を埋める存在として機能します。
まとめ:この記事全体の要点
- グッドプラスファクタリングは、中小企業・個人事業主向けの即日資金化サービス。
- 手数料は業界平均以下で、オンライン完結・担当者固定制により安心感が高い。
- 審査は売掛先重視で、創業間もない企業やフリーランスにも利用実績多数。
- 法務監修の契約体制・電子署名で法的リスクを回避できる。
- 会計処理では融資と混同せず、支払手数料として正しく損金計上する。
- 今後はAI審査や電子債権対応などにより、スピードと透明性がさらに向上。
グッドプラスファクタリングは、単なる資金調達ツールではなく、経営の安定と成長を支える「資金繰りの保険」ともいえる存在です。必要なときに、必要な分だけ、スピーディに現金化できる仕組みを備えること。それが、変化の激しい時代を生き抜く中小企業にとっての最善のリスクマネジメントとなります。
(出典:金融庁「中小企業金融の多様化に関する報告書」(2024年改訂)、国税庁「消費税法基本通達(令和5年版)」、資金調達マップ編集部取材)
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




