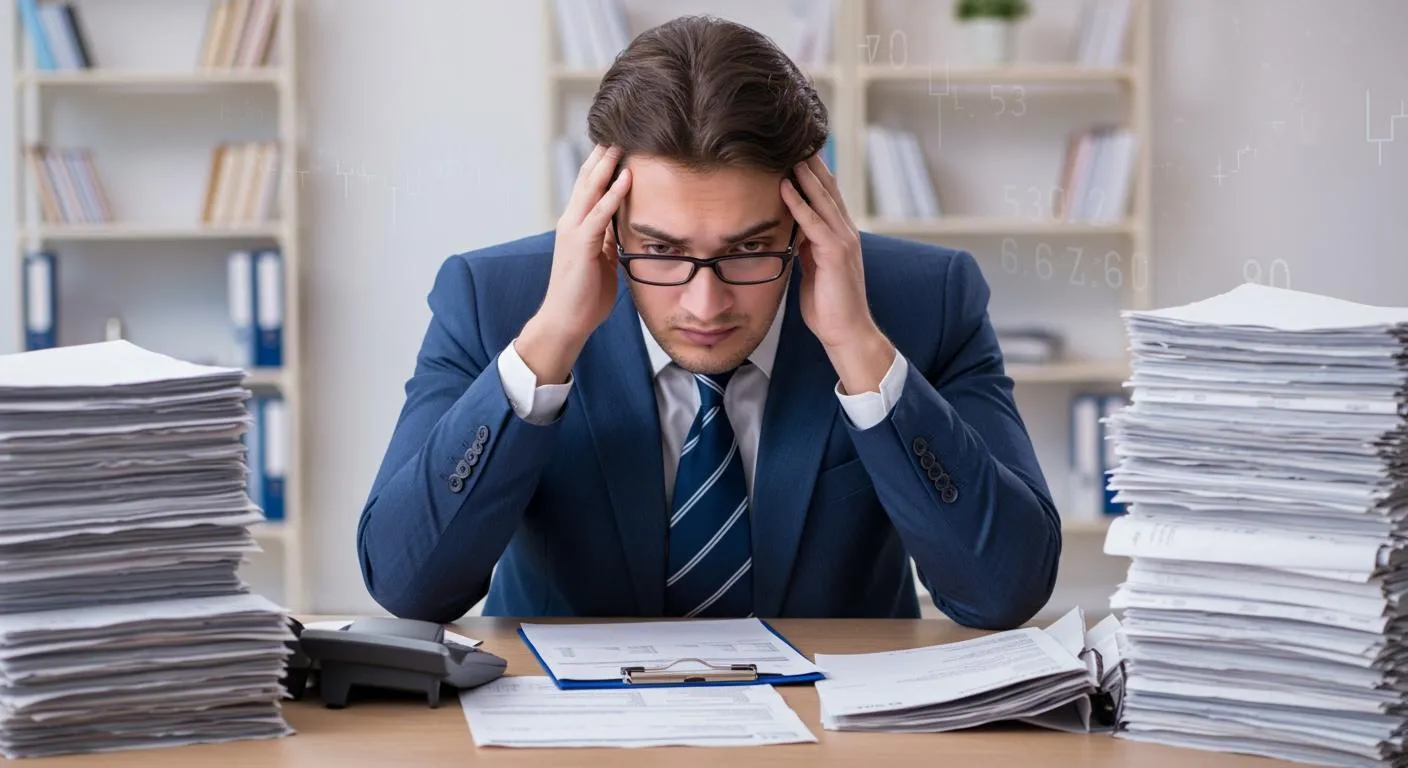企業経営において、資金繰りは最も重要な課題のひとつです。特に売掛金の回収が遅れることで、資金不足に陥るケースは少なくありません。その解決策のひとつが「ファクタリング」です。本記事では、ファクタリング返済仕訳に焦点を当て、仕組み・種類・勘定科目・税務・実務経験や企業の導入事例、会計士の見解を交え徹底解説します。ファクタリングを初めて検討する経営者から、既に利用中で仕訳に悩む経理担当者まで、幅広い方に役立つ情報を提供します。
関連記事
ファクタリングとは?基本概念と定義

ファクタリングの基本的な定義
ファクタリングとは、企業が取引先に対して保有している売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に現金を調達する仕組みを指します。通常、取引先からの入金は30日から90日後になることが多く、その間に資金繰りが悪化するケースがあります。ファクタリングを利用することで、売掛金を「債権譲渡」という形で現金化でき、スピーディーに資金を確保できます。
銀行融資との大きな違いは、返済義務がない点です。融資は借入金として利息を払いながら返済していく必要がありますが、ファクタリングは「債権の売却」であるため返済の概念はなく、手数料を支払えばそれで完結します。したがって、財務状況を悪化させずに資金繰りを改善できるという特徴があります。
- 資金調達を直接・迅速に行える
- 返済義務がない(ノンリコース型の場合)
- 銀行融資と異なり、審査基準は「自社」ではなく「取引先の信用力」に依存する
ファクタリングの仕組み
基本的な流れは次の通りです。
- 企業が売掛金をファクタリング会社に売却する契約を締結
- ファクタリング会社が売掛金の一定割合(通常80〜95%)を即日または数日以内に入金
- 取引先から売掛金が支払われた時点で、残額から手数料を差し引いて精算
この仕組みにより、企業は本来入金される時点を待たずして資金を得られます。
銀行融資との違い
| 項目 | ファクタリング | 銀行融資 |
|---|---|---|
| 資金調達の性質 | 売掛金の売却 | 借入(返済義務あり) |
| 審査基準 | 売掛先の信用力 | 自社の財務状況・信用力 |
| スピード | 即日〜数日 | 数週間〜数か月 |
| 費用 | 手数料 | 利息・保証料 |
経験談①:製造業A社のケース
地方で金属部品を製造するA社では、大手取引先からの入金が常に60日後となっており、従業員への給与支払や仕入代金の支払いに苦労していました。銀行融資も検討しましたが、担保と保証人が必要で時間もかかるため断念。
そこでファクタリングを導入し、売掛金1,000万円を即日で現金化。翌日の仕入代金支払に間に合わせることができ、経営の安定化につながりました。「資金ショートを防げたのは大きな安心材料になった」と社長は語っています。
経験談②:ITスタートアップB社のケース
クラウドサービスを提供するB社は、売上の大部分が法人契約で、入金サイトが長期化していました。特に初期の成長期には開発人材の採用に多額の資金が必要でしたが、融資実績も乏しく資金調達が困難でした。
そこでファクタリングを利用し、売掛金を現金化して採用コストを賄うことに成功。代表は「返済が不要で、成長スピードを落とさずに済んだ」と振り返っています。
ファクタリングの種類と特徴

ファクタリングには複数の種類が存在し、それぞれ仕組みやメリット・デメリットが異なります。ここでは代表的な種類を整理し、どのような状況で適切かを解説します。
主な種類の一覧
- リコース型ファクタリング:売掛先が倒産した場合、債権を譲渡した企業が買戻し義務を負う形式。
- ノンリコース型ファクタリング:売掛先が倒産しても買戻し義務がなく、リスク移転が可能。
- 2者間ファクタリング:売掛先には通知せず、利用企業とファクタリング会社のみで契約を行う。
- 3者間ファクタリング:売掛先も含めて契約する透明性の高い形式。取引先が承諾する必要がある。
- 国内ファクタリング:国内取引を対象とした一般的なサービス。
- 国際ファクタリング:輸出取引など海外の売掛金を対象にしたサービス。為替リスクへの対応が特徴。
各種類の特徴
リコース型は手数料が低めですが、万が一売掛先が支払不能になった場合、利用企業が責任を負うためリスクがあります。一方でノンリコース型は手数料が高いものの、リスク移転によって倒産リスクを回避できる点が魅力です。
2者間ファクタリングは資金化までのスピードが速く、即日対応も可能です。ただし、売掛先に通知しない分、透明性に欠け、取引先との信頼関係に影響するリスクもあります。
対して3者間ファクタリングは、売掛先も契約に関与するため透明性が高く、取引先の承認を得ることが前提となります。結果として、法的安定性や税務上の処理が明確になるメリットがあります。
実務での選択ポイント
- スピードを優先するか、透明性を重視するか。
- 売掛先の信用度が高いか低いか。
- 自社がリスクを取れるかどうか。
経験談③:建設業C社のケース
建設業を営むC社は、取引先からの入金が90日後となる長期サイトに悩まされていました。急な資材購入費用が必要になったため、2者間ファクタリングを利用し即日で1,500万円を調達。
しかし後日、売掛先から「なぜファクタリング会社が介入しているのか」と不信感を持たれ、取引に影響が出かけた経験があります。これを機に、C社は3者間ファクタリングへ切り替え、透明性を確保することで取引先との信頼を維持できました。
ファクタリングの種類と仕訳方法

買取型ファクタリングの仕訳
買取型ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却して現金化する最も一般的な方式です。売掛先からの入金を待たずに資金を得られるため、資金繰り改善に直結します。
例えば、売掛金50万円をファクタリング会社に譲渡し、手数料として2万円が差し引かれたケースを考えてみましょう。
(借方)現金 480,000円 /(貸方)売掛金 500,000円 (借方)売上債権売却損 20,000円
この仕訳では、売掛金を全額消し込み、手数料部分を「売上債権売却損」として計上します。これにより、資金繰りと損益計算書の整合性が保たれます。
注意点
- 誤って「借入金」として処理しないこと。ファクタリングは融資ではなく債権の譲渡です。
- 売上債権売却損は営業外費用として処理するケースが一般的ですが、会計基準に従って適切に分類することが必要です。
- 決算期をまたぐ場合、売掛金の消込処理を正確に行わないと資産残高が誤表示されるリスクがあります。
経験談④:小売業D社の事例
小売業を営むD社では、シーズンごとの仕入れ資金が必要でした。売掛金をファクタリングで現金化したところ、即日入金され、在庫を確保することができました。しかし経理担当者が誤って「借入金」として仕訳してしまい、監査法人から修正を指摘されるトラブルが発生。
その後、D社は会計ソフトにファクタリング専用の勘定科目を設定し、再発防止に成功しました。このケースからも、仕訳処理の正確性が非常に重要であることが分かります。
保証型ファクタリングの仕訳
保証型ファクタリングとは、売掛金の支払いが万一遅延・不履行となった場合に、ファクタリング会社や保証会社が代わりに債権を保証する仕組みです。つまり、資金をすぐに受け取る「買取型」とは異なり、リスク移転が主目的のサービスといえます。
仕訳上の特徴は「保証料」を費用として計上する点にあります。例えば、売掛金1,000,000円に対して保証料が20,000円発生した場合の仕訳は次の通りです。
(借方)支払手数料 20,000円 /(貸方)普通預金 20,000円
この場合、売掛金はそのまま資産として計上され続け、保証料だけが費用となります。つまり、保証型ファクタリングは資金化よりも信用リスクの管理に重きを置いた方法であることが仕訳からも分かります。
注意点
- 保証料は「支払手数料」として処理するのが一般的ですが、契約内容によっては「保険料」として計上される場合もある。
- 保証型は資金調達を目的としたものではなく、あくまで債権の保全・信用リスク管理に利用する点を誤解しない。
- 売掛金自体は貸借対照表から消えないため、資産計上が続くことを認識しておく必要がある。
経験談⑤:運送業E社のケース
運送業を営むE社では、取引先の一部が資金繰りに不安を抱えており、代金の未回収リスクが常に存在していました。そこで保証型ファクタリングを導入し、売掛金1,000万円に対して年間保証料30万円を支払い、安心して取引を継続。
実際にある取引先が支払いを遅延した際、保証会社が代位弁済を実施し、資金繰りに影響が出なかった経験があります。経理担当者は「資金化はできないが、安心料としては十分価値がある」と語っています。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い
ファクタリングには大きく分けて「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」があります。両者の違いを理解することは、仕訳処理だけでなく、実務上の選択にも直結します。
2者間ファクタリングの特徴
利用企業とファクタリング会社の2者だけで契約を結び、売掛先には通知しない形式です。スピードが早く、即日入金も可能ですが、売掛先には知られない一方で透明性が低く、リスクが高い点に注意が必要です。
仕訳例(売掛金500,000円、手数料15,000円の場合):
(借方)現金 485,000円 /(貸方)売掛金 500,000円 (借方)売上債権売却損 15,000円
3者間ファクタリングの特徴
利用企業・売掛先・ファクタリング会社の3者間で契約を締結します。売掛先が債権譲渡を承認するため、法的安定性が高く、会計処理も明確になります。ただし、売掛先への通知が前提となるため、関係性によっては「資金繰りが苦しいのではないか」と捉えられるリスクも存在します。
仕訳例(売掛金1,000,000円、手数料30,000円の場合):
(借方)現金 970,000円 /(貸方)売掛金 1,000,000円 (借方)売上債権売却損 30,000円
比較表
| 項目 | 2者間ファクタリング | 3者間ファクタリング |
|---|---|---|
| 契約形態 | 企業とファクタリング会社 | 企業・売掛先・ファクタリング会社 |
| 資金化スピード | 即日〜数日 | 数日〜1週間程度 |
| 透明性 | 低い(売掛先非通知) | 高い(売掛先承認あり) |
| 法的安定性 | やや低い | 高い |
| 手数料率 | 高め | 比較的低め |
実務での選択基準
- 「資金調達のスピード」を最優先 → 2者間が有利
- 「取引先との信頼関係」や「法的安定性」を重視 → 3者間が望ましい
- 決算書や監査に備えて透明性を確保したい場合も3者間が推奨される
経験談⑥:広告代理店F社のケース
広告代理店を営むF社は、成長期に多額の広告費立替を行い、資金繰りに悩まされていました。最初は即日資金化を目的に2者間ファクタリングを利用しましたが、売掛先から「なぜ第三者が関わっているのか」と問い合わせを受け、関係悪化のリスクを痛感。
その後、3者間ファクタリングに切り替えた結果、売掛先も事情を理解し、むしろ「資金繰りを透明化する健全な取り組み」と評価されました。これにより、取引先との信頼が維持されただけでなく、監査法人からも処理の妥当性を認められる結果となりました。
売掛金と未収入金の仕訳方法
ファクタリングを仕訳する際に迷いやすいのが、売掛金と未収入金の使い分けです。両者は似ているようで役割が異なります。
売掛金とは
売掛金は、商品やサービスを販売した後に発生する営業取引に基づく債権です。通常の取引先との売上代金は、売掛金として計上されます。
未収入金とは
未収入金は、営業活動以外で発生する金銭債権を処理するための科目です。例えば固定資産の売却代金、保険金の受け取り、補助金などが該当します。
仕訳例:売掛金のファクタリング
売掛金500,000円をファクタリング会社へ譲渡し、手数料20,000円を差し引いて入金された場合の仕訳は次の通りです。
(借方)現金 480,000円 /(貸方)売掛金 500,000円 (借方)売上債権売却損 20,000円
仕訳例:未収入金のファクタリング
補助金や保険金など未収入金として計上している債権をファクタリングした場合は、売掛金ではなく未収入金を減額します。
(借方)現金 970,000円 /(貸方)未収入金 1,000,000円 (借方)売上債権売却損 30,000円
注意点
- 営業取引由来 → 売掛金
- 営業外取引由来 → 未収入金
- 仕訳を誤ると貸借対照表の表示区分が乱れ、監査時に修正を求められるリスクがある
経験談⑧:サービス業H社のケース
サービス業H社では、補助金の受給権をファクタリングにかけましたが、経理担当者が誤って「売掛金」として処理してしまいました。監査法人から「補助金は営業外取引に該当するため未収入金を用いるべき」と指摘を受け、修正することに。
この経験からH社では「営業活動か否か」で勘定科目を判断するチェックリストを導入し、以降は同様のミスを防止しています。
売上債権売却損と支払手数料の仕訳
ファクタリングにおいては、資金調達に伴って売上債権売却損や支払手数料といった費用が発生します。これらは混同されやすい科目ですが、正しく使い分けることが重要です。
売上債権売却損とは
売上債権売却損は、売掛金を譲渡する際に発生する差額(手数料)を表す勘定科目です。これは営業外費用として計上されるケースが多く、売掛金を完全に消込むと同時に処理します。
例:売掛金1,000,000円をファクタリングにより970,000円で現金化(手数料30,000円)の場合
(借方)現金 970,000円 /(貸方)売掛金 1,000,000円 (借方)売上債権売却損 30,000円
支払手数料とは
支払手数料は、保証型ファクタリングや事務手続きに対して支払う手数料です。債権売却差額とは性質が異なり、こちらは営業費用や販売費および一般管理費に計上されるケースもあります。
例:保証型ファクタリングにより保証料20,000円を支払った場合
(借方)支払手数料 20,000円 /(貸方)普通預金 20,000円
両者の違い
| 項目 | 売上債権売却損 | 支払手数料 |
|---|---|---|
| 発生する場面 | 売掛金の譲渡による差額 | 保証型や事務手続き費用 |
| 性質 | 営業外費用 | 販売費および一般管理費 |
| 決算書への影響 | 損益計算書の営業外費用に計上 | 販管費に計上 |
経験談⑨:人材派遣業I社のケース
I社では、複数のファクタリング取引を行っていましたが、経理担当が「売上債権売却損」と「支払手数料」を区別せずにすべて売却損として処理してしまいました。
監査法人から「保証料は売上債権売却損ではなく支払手数料で処理すべき」と指摘され、修正を余儀なくされました。これにより、I社は社内規程を改定し、契約内容に応じて科目を仕分けるフローチャートを作成。結果として経理精度が向上しました。
ファクタリングの仕訳例と注意点
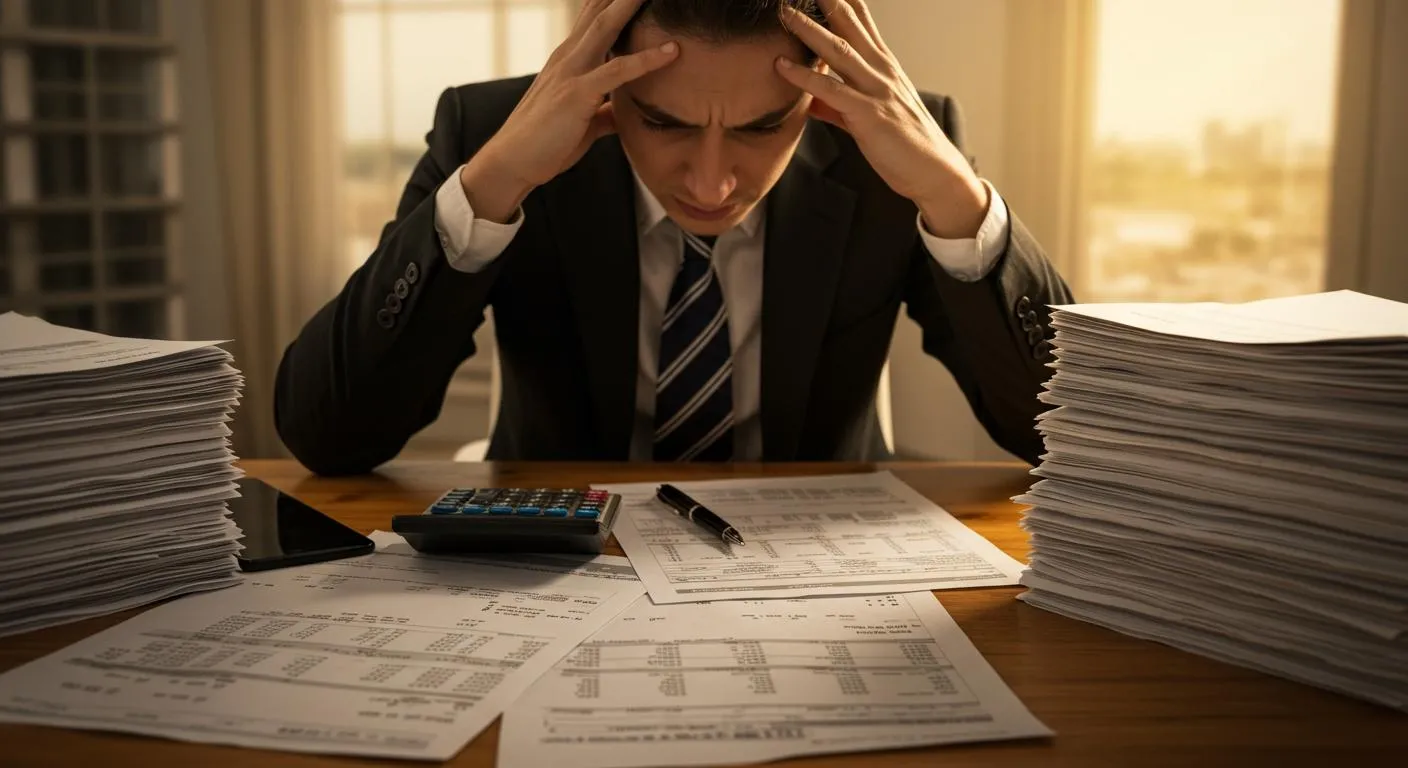
具体的な仕訳例の紹介
ファクタリング取引は、契約形態や金額に応じて仕訳方法が異なります。ここでは代表的なケースを挙げ、実務で利用しやすい具体例を紹介します。
例1:売掛金500,000円をファクタリング会社に譲渡(手数料20,000円)
(借方)現金 480,000円 /(貸方)売掛金 500,000円 (借方)売上債権売却損 20,000円
例2:売掛金1,000,000円をファクタリング(3者間契約、手数料30,000円)
(借方)現金 970,000円 /(貸方)売掛金 1,000,000円 (借方)売上債権売却損 30,000円
例3:保証型ファクタリングで保証料50,000円を支払った場合
(借方)支払手数料 50,000円 /(貸方)普通預金 50,000円
これらの仕訳例はあくまで基本形であり、実際の契約内容や税務処理方針によって調整が必要になる場合があります。
ファクタリング仕訳の注意点
ファクタリング仕訳にはいくつかの注意点があります。
- 仕訳の正確性:誤って「借入金」で処理すると融資と誤解され、税務上のトラブルにつながる。
- 取引形態の違い:買取型・保証型・2者間・3者間で仕訳が異なるため、契約内容に応じて適切に選択する。
- 期末処理:決算期をまたぐ場合、売掛金や未収入金の消込処理を正確に行わなければならない。
消費税の取り扱いについて
ファクタリングの手数料は消費税課税対象となります。したがって、消費税の処理を忘れると申告漏れのリスクが生じます。
例:手数料20,000円(消費税10% 2,000円を含む)の場合
(借方)売上債権売却損 18,000円 /(貸方)普通預金 20,000円 (借方)仮払消費税 2,000円
契約内容によっては非課税とされるケースもあるため、必ず契約書や税理士の確認を行うことが重要です。
経験談⑩:建設業J社のケース
建設業のJ社は、ファクタリングを初めて利用した際に、経理担当が「借入金」として計上してしまいました。その結果、融資と同様に利息を計上してしまい、税務署から指摘を受ける事態に。
修正後は「売上債権売却損」専用の仕訳マニュアルを社内で作成し、再発を防止しました。この経験から、経理担当者がファクタリング特有の処理方法を理解しておく重要性が浮き彫りになりました。
ファクタリングの利用に関する税務上の注意

確定申告とファクタリングの関係
ファクタリングを利用した場合、得られた資金は「借入」ではなく売掛債権の譲渡による収入として扱われます。したがって、確定申告や決算時には正確な計上が求められます。
- 収入計上:譲渡した売掛金は消し込み、受け取った金額との差額は「売上債権売却損」として計上。
- 必要書類:契約書、債権譲渡通知書、入金明細などを整理・保管しておくこと。
- 期限遵守:確定申告や法人税申告の期限を過ぎると、加算税や延滞税が発生する可能性がある。
特に個人事業主や中小企業では、仕訳を誤って「借入金」として扱ってしまうケースが散見されます。この誤りは税務署から指摘されやすいため注意が必要です。
経験談⑬:フリーランスデザイナーMさんのケース
Mさんは法人顧客からの入金サイトが長いため、売掛金をファクタリングで資金化していました。しかし確定申告時に「借入金」として処理してしまい、税務署から「売掛債権の譲渡は収入計上が必要」と指摘を受け、修正申告を行うことに。以降は税理士に相談し、正しく「売上債権売却損」として計上するようになりました。
税務上の注意点
ファクタリング取引における税務処理には、以下の注意点があります。
- 税務調査のリスク:売掛金の消込や手数料処理が曖昧だと、調査時に否認される可能性がある。
- 手数料の扱い:手数料は「売上債権売却損」または「支払手数料」として経費計上できるが、契約内容に応じて使い分ける必要がある。
- 非課税・課税の区分:債権譲渡差額は非課税取引とされる一方、手数料部分は消費税課税対象となる場合が多い。
- 法人税の影響:売上債権売却損は法人税の計算上、損金算入が可能。ただし経理処理を誤ると否認リスクあり。
税理士のアドバイス
筆者が相談した税理士は「ファクタリングは資金繰りには有効だが、仕訳や税務処理を誤ると、資金調達のメリット以上にリスクが高まる」と指摘しています。特に契約書を正しく読み解く力と科目の適切な使い分けが重要であり、疑問がある場合は必ず専門家に確認するべきです。
ファクタリングを利用する際の検討事項
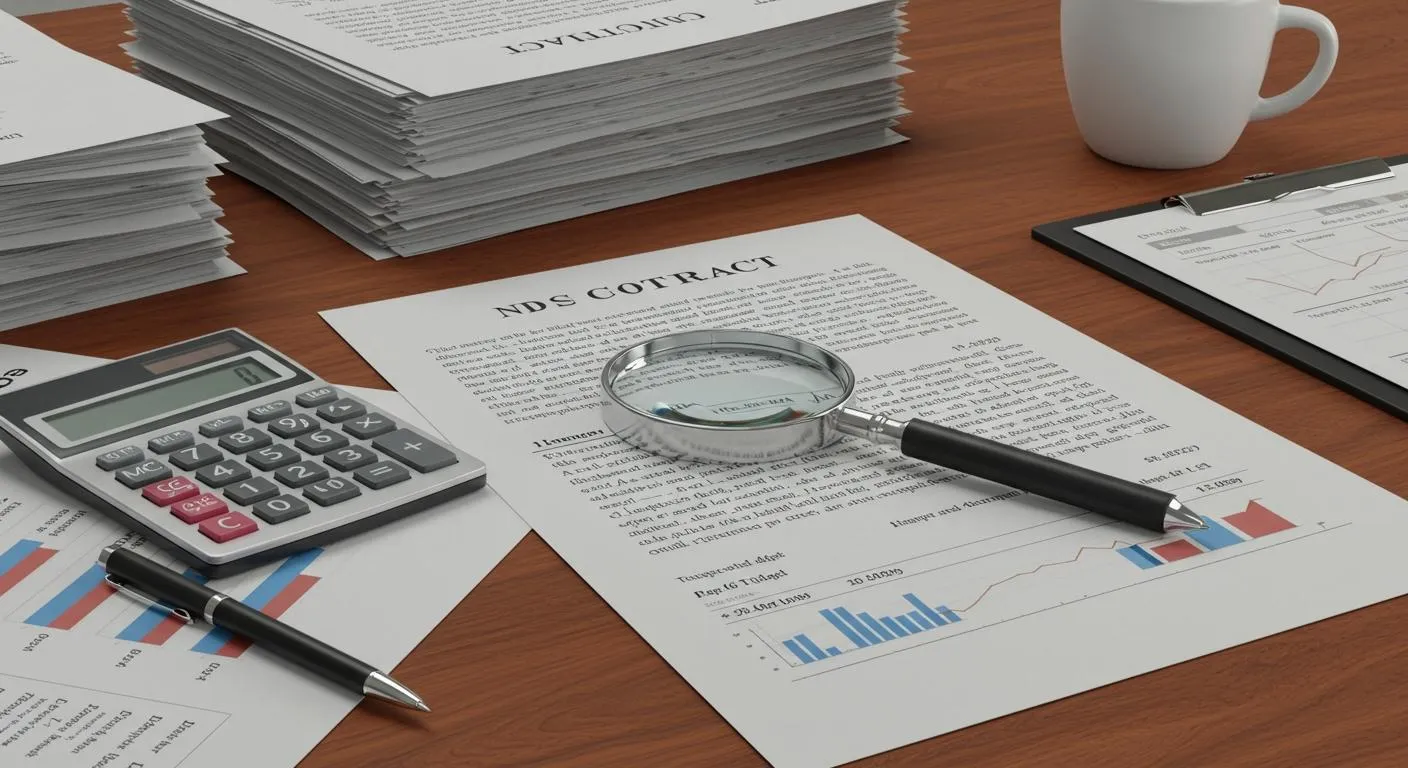
資金調達としてのファクタリングの検討
ファクタリングを資金調達の手段として検討する際には、まず仕組みの理解が不可欠です。売掛金を譲渡して即時に現金化する点は魅力的ですが、他の資金調達手段(銀行融資、ビジネスローン、助成金など)と比較したうえで選択する必要があります。
- 銀行融資:低金利だが審査が厳しく、時間がかかる。
- ビジネスローン:スピードは速いが、利息負担が大きい。
- 助成金・補助金:返済不要だが、申請や審査に時間がかかる。
- ファクタリング:即時性が高く、返済不要。ただし手数料は発生する。
特に中小企業や個人事業主の場合、短期的な資金繰り改善にはファクタリングが有効ですが、長期的にはコスト負担を考慮しなければなりません。
返済条件や手数料の把握
ファクタリングには返済の概念はないものの、「返済型」のように分割精算される契約も一部存在します。その場合、支払時点ごとに仕訳が必要となり、資金繰り計画との連動が欠かせません。
また、手数料は契約内容によって3〜20%と幅があります。必ず以下を確認しましょう。
- 手数料率の明確化
- 支払スケジュール
- 追加費用の有無(事務手数料・保証料など)
経験談⑭:建築資材業N社のケース
N社は、資材購入のために急ぎで資金を必要としていました。ファクタリング契約を結んだものの、契約書を十分に確認せずに進めた結果、想定外の「事務手数料」と「更新料」が発生。最終的に調達額の15%がコストとなり、資金繰りをさらに圧迫しました。
この経験からN社は契約書の全条項を精査し、専門家に相談したうえで契約する体制を整備しました。
ファクタリング契約の確認事項
契約書のチェックポイントは以下の通りです。
- 手数料や利息の計算方法が明記されているか。
- 契約解除条件や違約金の有無を確認しているか。
- 契約期間が明確であるか。
- 信頼できる業者かどうか(過去の実績や口コミ、金融庁登録の有無を確認)。
契約トラブルを避けるために
契約内容を理解しないまま進めると、資金調達の効果が薄れるばかりか、トラブルの原因になります。必ず契約前に条項を精査し、必要であれば税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
ファクタリングの活用事例
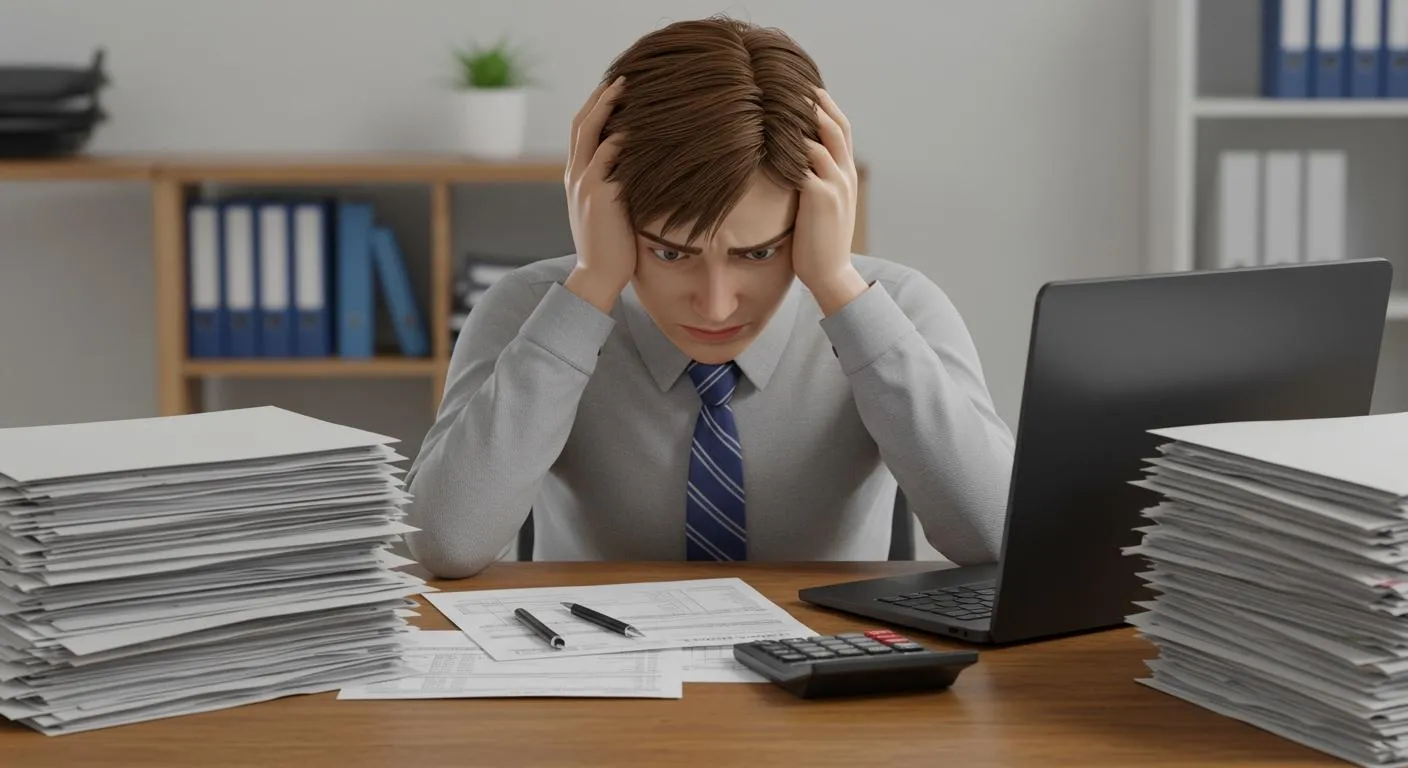
中小企業の成功事例
実際にファクタリングを導入して資金繰りを改善した企業の事例を紹介します。これらは、単なる理論ではなく現場での実体験に基づくものです。
事例1:製造業O社
O社は下請けとして大手企業と取引をしていましたが、入金サイトが90日と長期であり、仕入先への支払が先行して資金繰りが厳しい状況にありました。そこで、売掛金2,000万円をファクタリング会社に譲渡し、1,900万円を即日調達。これにより仕入代金を期限通りに支払え、取引先からの信頼を維持できました。
導入後は「急場をしのぐ手段」としてだけでなく、定期的に活用する資金繰りの仕組みとして組み込むことに成功しました。
事例2:ITサービス業P社
P社は急成長中のスタートアップで、広告宣伝費や人材採用に多額の費用が必要でした。しかし、取引先からの入金は毎回60日後。資金不足から採用を見送る場面も出ていました。
そこで、売掛金1,000万円をファクタリングで現金化し、開発人材を計画通り採用。結果として、翌年度には売上が150%に拡大しました。代表は「返済義務がなく、スピード感を持って成長投資できた」と振り返っています。
業種別の活用方法
ファクタリングは業種によっても有効な使い方が異なります。
- 建設業:材料費や人件費の支払が先行しやすいため、工事代金の売掛金を資金化して資材購入や人件費に充当。
- 医療・介護業:診療報酬や介護報酬は入金が2か月遅れるため、運転資金の安定化にファクタリングが役立つ。
- 運送業:燃料費や車両維持費が即時必要なため、売掛金の早期回収が資金繰り改善に直結。
- 小売・卸売業:仕入代金の支払いが入金よりも先に来るため、ファクタリングで差を埋める。
- IT・サービス業:広告宣伝費や人件費を先行投資する際に、売掛金を資金源として活用。
事例3:介護事業Q社
介護サービスを展開するQ社は、介護報酬の入金が2か月後になるため、常に資金不足に悩んでいました。銀行融資を検討しましたが、審査に時間がかかり即時資金化が難しい状況。
そこで介護報酬債権をファクタリングで資金化し、運転資金を確保。結果として、従業員の給与を安定して支払えるようになり、離職率の低下につながりました。
まとめ
これらの事例から分かるのは、ファクタリングは単なる「資金調達手段」ではなく、事業継続・成長を支える戦略的ツールになり得るという点です。業種や経営状況に応じて適切に活用することで、資金繰りの改善だけでなく、事業拡大や従業員の安定雇用といった波及効果をもたらします。
ファクタリングに関するよくある質問(FAQ)
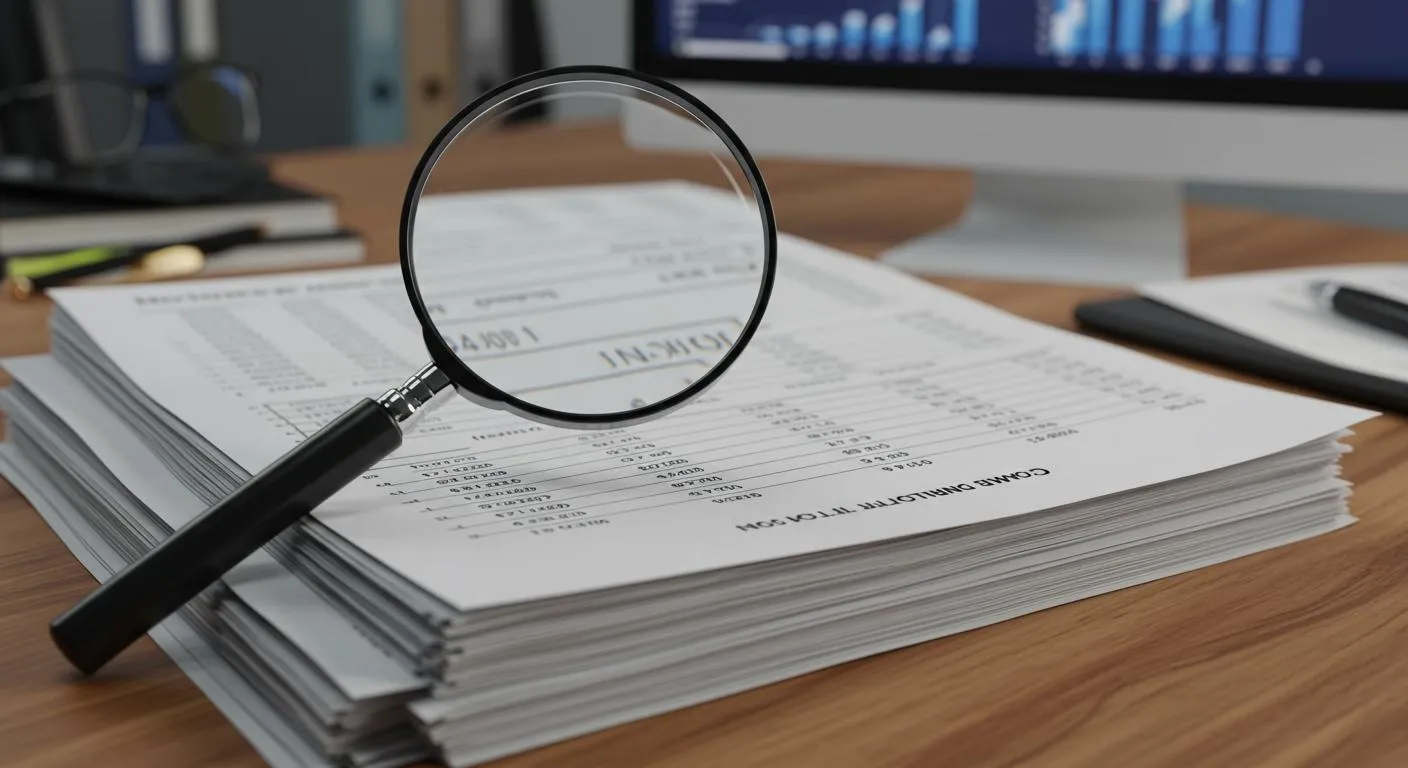
ファクタリングに関する一般的な質問
Q1. ファクタリングとは融資と同じですか?
A. いいえ、異なります。ファクタリングは「売掛金の譲渡」であり、融資のような返済義務はありません。そのため、バランスシートに借入金が増えることはなく、財務体質を圧迫しません。
Q2. 手数料はどのくらいかかりますか?
A. 一般的には売掛金額の3〜20%程度です。契約形態(2者間か3者間か)、売掛先の信用度、利用金額によって変動します。
Q3. 売掛先に知られずに利用できますか?
A. 可能です。2者間ファクタリングであれば売掛先に通知せずに利用できますが、透明性に欠けるため契約書や税務処理に注意が必要です。3者間は通知されますが、法的安定性が高くなります。
Q4. ファクタリング利用は信用情報に影響しますか?
A. 基本的には信用情報機関には登録されません。ただし、繰り返し利用していると取引先に「資金繰りに困っている」と誤解されるリスクは存在します。
具体的なケーススタディと回答
ケース1:急な資金不足に直面した小売業者
小売業を営むR社は、仕入代金の支払期限が迫っていたものの、売掛金の入金は翌月末。銀行融資では間に合わないため、ファクタリングを利用しました。結果、即日で500万円を調達し、仕入れを滞りなく実行できました。
回答: このように、ファクタリングは緊急の資金需要に対応できる柔軟な手段として有効です。ただし、手数料負担があるため長期的な依存は避けるべきです。
ケース2:税務処理に悩むフリーランス
フリーランスのデザイナーSさんは、売掛金をファクタリングで資金化しましたが、仕訳を「借入金」として処理してしまい、税務署から修正を求められました。
回答: ファクタリングは「借入」ではなく「債権譲渡」です。受け取った金額との差額は「売上債権売却損」として処理するのが正しい方法です。
ケース3:継続利用する建設業者
建設業T社は、材料費や人件費が先行するため、毎月のようにファクタリングを利用していました。しかし年間の手数料負担が増え、利益を圧迫する結果に。
回答: ファクタリングは短期的な資金繰り改善には有効ですが、長期的には融資や補助金との併用を検討し、依存度を下げることが望ましいです。
まとめと今後の展望

ファクタリングの今後の利用可能性
ファクタリングは、従来から中小企業の資金繰り改善手段として活用されてきましたが、2026年以降はさらに需要が拡大すると予想されています。背景には以下のような要因があります。
- 市場の成長:日本国内における中小企業の資金調達ニーズは高まっており、ファクタリング市場は拡大傾向にある。
- 新サービスの登場:オンライン完結型ファクタリングやAI審査を導入する事業者が増加し、利便性とスピードがさらに向上。
- 中小企業支援の強化:政府や自治体による資金繰り支援策と組み合わせて利用できる可能性が広がっている。
体験談⑮:スタートアップ企業U社のケース
U社は、海外展開を見据えたITサービスを提供していましたが、開発費用が先行し資金繰りに不安がありました。銀行融資は審査に時間がかかるため、オンライン完結型のファクタリングを選択。即日で1,000万円を調達し、海外向けサービスのローンチに間に合わせることができました。代表は「スピード感のある資金調達が競争優位につながった」と語っています。
ファクタリングを利用する際のポイント
ファクタリングは有効な資金調達手段ですが、利用にあたっては以下の点を必ず確認する必要があります。
- 契約内容の確認:契約書には手数料率、精算条件、契約解除条項などが明記されているかを確認する。
- 手数料の理解:単純な手数料だけでなく、事務手数料や更新料などの隠れコストがないかをチェックする。
- 業者選び:金融庁に登録された業者や、実績があり評判の良い会社を選定することが重要。
今後の展望
今後は、電子記録債権(でんさい)やブロックチェーンを活用した取引など、より透明性と効率性の高いファクタリングサービスが登場すると見込まれます。これにより、従来は利用が難しかった小規模事業者や個人事業主も、より簡単に安全に利用できるようになるでしょう。
ただし、普及が進む一方で、不透明な業者や高額な手数料を請求する業者も残存する可能性があります。利用者側は正しい知識を持ち、信頼できるパートナーを選ぶ力が求められます。
まとめ
ファクタリングは、「返済不要」「迅速」「信用力に依存しない」という独自の特徴を持つ資金調達手段です。適切に活用すれば、資金繰り改善や事業拡大の大きな助けとなります。しかし、仕訳の誤りや税務処理の不備、契約内容の不理解はリスクを生じさせます。
この記事で紹介した事例・仕訳例・注意点を参考に、信頼できる業者を選び、計画的に活用することで、ファクタリングを攻めの経営戦略へと昇華させることができるでしょう。
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する