
本記事では、ファクタリングと融資という二大資金調達手法を最新の業界動向・現場の声・専門家の視点で徹底比較。仕組みや違いはもちろん、業種別の活用法、実際の体験談や失敗事例まで、2026年の経営判断に欠かせないリアルな情報を詳しく解説します。
関連記事
ファクタリングと融資の基本概念

ファクタリングとは何か
ビジネスにおいて「資金繰り」は常に課題の一つです。とくに中小企業や成長期のベンチャーは、売上が上がっているにもかかわらず「手元に現金がない」状態に直面することが珍しくありません。売掛金回収まで数十日~数カ月かかる商習慣が続く日本では、この“入金待ち”によって経営危機に陥る企業も多いのが現実です。
ファクタリングとは、この売掛金(まだ入金されていない請求権)を、専門業者が前もって現金で買い取ることで、すぐに資金化できる仕組みです。つまり、本来1か月後や2か月後に受け取る予定の売上を、必要なタイミングで現金化できるという、現代ビジネスのスピード経営を支える資金調達法です。
具体的な利用シーンとして多いのは、
・仕入れや人件費の支払いに間に合わせたい
・急な大型案件で運転資金が足りない
・金融機関の審査に落ちたが、売掛金だけはある
といったタイミング。
「ビジネスが拡大して受注は増えているのに、現金が回らない」という悩みを持つ企業にとって、ファクタリングはまさに“即効性の高い資金調達”となります。
ファクタリングの流れは、1)売掛金の内容・証拠書類を提出→2)審査・契約→3)資金受け取りという極めてシンプルなものです。取引先の同意が不要な2者間ファクタリングや、取引先に通知して行う3者間ファクタリングなど複数の方式がありますが、いずれも数日以内に現金化できるスピード感は大きな魅力です。最近はオンラインで申請・契約まで完結できるサービスも登場し、資金調達の利便性は飛躍的に高まっています。
ファクタリングの実際の現場での声(体験談)
「当社は新規取引先との大型契約が続き、手形決済まで2カ月待ちという状況。運転資金がショートしかけた時にファクタリングを知り、売掛金を分割して現金化できることに驚きました。銀行融資は時間も手間もかかる上、審査も厳しい。ファクタリングは資金繰りの“安全弁”として、今では繁忙期ごとに利用しています」(製造業・従業員30名・経営者)
多くの企業が「なぜファクタリングを選ぶのか?」という理由は明確です。
・自社の信用力が弱くても、売掛先の信用で資金調達ができる
・手続きがオンラインで完結する場合も多く、スピード対応が可能
・返済義務がなく、バランスシート上の負債が増えない
・リスク分散の観点から、銀行融資と組み合わせる事例も多い
一方で、「手数料が割高」「取引先との関係悪化の懸念」などデメリットや注意点も存在します。これらは後述の章で詳しく掘り下げますが、重要なのは、ファクタリングは万能の資金調達法ではなく、“必要な時に、必要な分だけ使う”ことで本来の価値が最大化されるという視点です。
業界の裏話:近年、ファクタリングを巡るトラブルも増加傾向にあり、悪質な業者による高額手数料や、契約内容の不備による法的紛争も発生しています。利用する際は、複数社の見積もりを取り、契約書の内容を十分に精査することが極めて重要です。後述の「リスクと対策」章で、失敗事例も具体的に紹介します。
このように、ファクタリングは「現金化できる売掛金がある企業」にとって非常に強力な選択肢であり、急成長市場となっている背景には、日本ならではの商慣習と、スピード経営の必要性が色濃く反映されています。
融資とは何か
融資は、銀行やノンバンクなどの金融機関が、企業や個人に対して“将来的な返済”を前提に資金を貸し付けることです。古くからある資金調達手段であり、設備投資・新規事業・既存事業の運転資金など幅広いニーズに対応します。
一般的な流れは、1)申し込み→2)審査→3)契約・入金→4)返済となりますが、金融機関によっては事前相談や面談、追加書類提出など、プロセスは多岐に渡ります。
融資の種類も多岐にわたり、
・銀行融資(プロパー融資・保証協会付き融資など)
・ビジネスローン(ノンバンク・信販会社など)
・消費者金融による個人事業主向けローン
などが存在します。融資枠や金利、返済期間、担保や保証人の有無など、条件も千差万別です。
融資の最大のメリットは「大口資金の一括調達が可能」「返済期間や金利を自社に合わせて設定できる」ことです。
たとえば、長期的な設備投資や人材確保など、成長戦略を描く経営者にとっては、融資は不可欠なファイナンスツールとなります。一方で、審査基準が厳しく、財務状況や信用力が評価の中心となるため、赤字や債務超過、過去の金融事故があると審査落ちのリスクも高まります。
実務現場のリアル(体験談)
「わが社では、コロナ禍で売上が激減した2021年、銀行からの追加融資に救われました。返済義務と金利負担は大きいものの、長期計画のもとで資金を確保できるのは大きな安心材料。審査書類は煩雑でしたが、担当者との信頼関係構築が決め手となりました。」(サービス業・経営歴20年)
融資を利用する際は、「事業計画や返済計画の現実性」「金利や手数料、保証料などの総コスト」「万が一の時の対応(リスケや債務免除の可能性)」まで、事前に十分な準備と調査が不可欠です。経営判断に直結するため、専門家のアドバイスや過去の事例も積極的に参考にしましょう。
豆知識:日本では「銀行融資=最も安全で安い資金調達」と見なされることが多いですが、近年はクラウドレンディングやオンライン型のローンサービスも増加。審査スピードや条件の柔軟さを求めて、金融商品を使い分ける企業が増えています。
逆に、「借入は最後の手段」と考える経営者も少なくなく、その理由は、返済義務や金利負担の長期化が事業経営に与える心理的プレッシャーも大きいからです。
ファクタリングと比べて、「借り入れる資金」という意識を持ち、将来のキャッシュフローと返済のバランスを冷静に計算することが重要です。
ファクタリングの仕組み

ファクタリングの流れ
ファクタリングを初めて利用する際、最も気になるのが「どういった手順で資金が手に入るのか」という点です。
ファクタリングの取引は、基本的に売掛金の譲渡を軸に進みます。企業は、まだ回収できていない売掛金をファクタリング会社に売却し、その代金を受け取ります。ここで重要なのは、融資とは異なり“借りる”のではなく、“売る”ことで現金化するという仕組みであることです。
代表的な流れは以下のとおりです。
- 売掛金の発生…企業が商品やサービスを取引先へ提供し、売掛金(請求権)が発生
- ファクタリング会社への申込…売掛金の内容、取引先情報、契約書や請求書などの証拠書類を提出
- 審査…ファクタリング会社が、売掛先や請求内容の信頼性、債権の発生理由、過去の取引実績などをチェック
- 契約締結…条件が合意すれば契約書を交わし、譲渡手続きに進む
- 資金の受け取り…最短で即日、通常は2~3営業日以内に指定口座へ現金が入金
- 売掛先からの入金…期日到来後、売掛先から本来の代金が支払われ、ファクタリング会社が手数料を差し引き精算
ファクタリング取引の特徴は、「売掛先が大企業や安定企業なら、中小企業でも高い審査通過率で利用できる」点です。取引先の信用情報や決算内容をもとに審査が行われるため、利用者側が過去に赤字決算や資金繰りに不安を抱えていても、売掛債権自体の信頼性が高ければ十分に利用できる場合が多くなっています。
資金調達までの期間もファクタリングの大きな魅力のひとつです。たとえば「午前中に申込、午後には口座に現金入金」というケースもあり、通常の銀行融資では考えられないスピードです。最近では、スマートフォンやパソコンで書類提出から契約まで完結できる“オンラインファクタリング”のサービスも広がっており、平日なら即日入金対応が標準化しつつあります。
【現場コラム:手続きのリアル】
「初めて利用した際、オンラインで書類をアップロードしただけで、担当者からすぐに電話が来て必要事項をヒアリング。その後、電子契約書が届き、印鑑レスで全て完結。驚くほど簡単で、しかも2日後には現金化。これまで“資金繰り=銀行融資”という先入観があったが、時代は変わったと感じた」(IT業・経営者)
なお、ファクタリングは「売掛債権の譲渡」という法律行為を伴います。契約内容や手数料率、万が一の債権回収不能時の責任分担など、基礎的な仕組みを理解し、必要に応じて専門家にも相談しながら進めることが安心につながります。
ファクタリングの種類
一口にファクタリングと言っても、その形態は複数存在します。取引方法・リスク分担・取引先との関与度合いによって、主に以下の種類に分けられます。
- 2者間ファクタリング:自社(売り手)とファクタリング会社(買い手)だけで完結する取引。売掛先には原則通知されません。資金調達のスピードと柔軟性が高い一方、手数料はやや高めになる傾向。
- 3者間ファクタリング:売り手・ファクタリング会社・売掛先の三者で契約を交わし、売掛先が債権譲渡を承認。取引先に通知されるため透明性が高く、手数料も安くなりやすいが、取引先の理解や承諾が必要。
- リコースファクタリング(償還請求権付き):万が一売掛先が代金を支払わなかった場合、売り手がその債務を負担。手数料は低めだがリスクは残る。
- ノンリコースファクタリング(償還請求権なし):売掛先が倒産などで支払い不能となっても、ファクタリング会社がリスクを負う。手数料は高いが、経営リスクを完全に切り離せる。
- 医療・介護報酬ファクタリング:医療機関や介護事業者が国保・社保などからの報酬請求権を現金化する特化型。審査が緩やかで安定した調達が可能。
このように種類ごとに特徴やリスクの分担が異なります。「すぐ現金が必要」「取引先に知られたくない」「万一の回収不能リスクを取りたくない」など、事業の実情や経営者の考えに応じて、最適なファクタリングを選ぶことがポイントです。
利用シーン別の事例も参考になります。たとえば、創業間もないスタートアップがオンライン2者間ファクタリングを利用し、広告費の前払い資金を確保した事例や、地方の製造業が3者間ファクタリングでメイン取引先の大型案件に対応できた事例などがあります。自社の業態や財務状況を冷静に分析し、「どの手法が最も合理的か」を判断しましょう。
融資の仕組み

融資の流れ
融資は、基本的に「申し込み」→「審査」→「契約」→「入金」→「返済」というステップで進行します。
まずは、企業側が金融機関へ申し込みを行い、事業計画書や決算書、資金使途を明確にした資料を提出します。これがしっかりしていないと、書類段階で門前払いとなるケースも少なくありません。とくに事業計画やキャッシュフローの予測が重視されるため、「資金を何に使うのか」を論理的に説明できる準備が不可欠です。
金融機関は提出書類に基づき、過去の業績や財務状況、取引先や市場環境まで幅広く審査を実施。ここで銀行によっては担当者との面談や追加資料の提出を求められることもあり、審査基準は「過去の実績+将来の事業性」をバランスよく評価されます。
一般的な銀行融資では、申し込みから入金まで1か月程度を要するケースが多いですが、ノンバンクやビジネスローンでは「最短即日審査・数日で入金」というスピード型商品も増えています。
契約時には「返済期間・金利・担保・保証人・返済方法(元利均等返済・元金一括など)」など、細かな条件が設定されます。これらをしっかり確認し、将来的なキャッシュフローに無理のない返済計画を立てることが成功の鍵となります。
【実例・経験談】
「過去に2度目の銀行融資を受ける際、1回目よりも提出書類が多くなり、現場の厳しさを痛感しました。ただ、経理担当者と一緒に資料の準備を徹底したおかげで、スムーズに審査を通過し、必要な額を確保。長年の実績と取引履歴が信用構築につながると実感しました。」(製造業・財務部長)
融資の流れにおいて重要なのは、「わからない点は遠慮なく金融機関の担当者に確認する」「契約内容は必ず書面で残す」ことです。条件交渉や、万一の返済猶予(リスケ)なども事前に相談しておくと安心です。
銀行融資の種類
銀行が提供する融資には、さまざまな形態があります。それぞれ特徴や利用シーンが異なるため、目的や自社の状況に応じて最適な方法を選ぶ必要があります。
- 無担保融資:担保(不動産や在庫など)を差し入れずに資金を借りる方法。信用力や事業性が重視され、金利は高め。中小企業向け・創業支援型などが主流。
- 担保融資:土地や建物などの資産を担保に差し入れ、その価値を元に借り入れ。低金利・大口資金が調達しやすい反面、返済できない場合は資産を失うリスクがある。
- ビジネスローン:主にノンバンク系が提供。書類審査が簡素化されており、スピード重視の調達が可能だが、銀行融資より金利は高め。
- 手形貸付・証書貸付:運転資金や設備資金の一時的なニーズに合わせた短期融資。証書貸付は長期・分割返済型が主流。
- 保証協会付き融資:信用保証協会が保証人となることで、銀行のリスクが軽減され、中小企業や創業間もない企業でも利用しやすい。
融資制度は、全国の地方銀行や信用金庫、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)でもそれぞれ異なる独自のサポートや補助制度があり、最新情報は公式サイトや専門家に確認するのが確実です。
また、「債権譲渡担保融資」「ABL(動産担保融資)」など、売掛金や在庫など流動資産を担保とする新しいタイプの融資も普及しています。
ビジネスの現場では「どの融資を使うか」「複数制度を組み合わせるか」など、きめ細かな判断が求められます。
「2%未満の低金利で長期資金を借りられた」「ノンバンクのビジネスローンで急場をしのいだ」「地方銀行と公庫のダブル利用で事業再構築を実現」など、ケースバイケースの活用事例が現場には溢れています。
融資は単に「お金を借りる」だけでなく、企業の信用構築や事業拡大の戦略的なツールです。担当者や外部専門家と連携しながら、自社に最適な条件を引き出していく姿勢が、長期的な経営の安定と成長を支えます。
ファクタリングと融資の主な違い
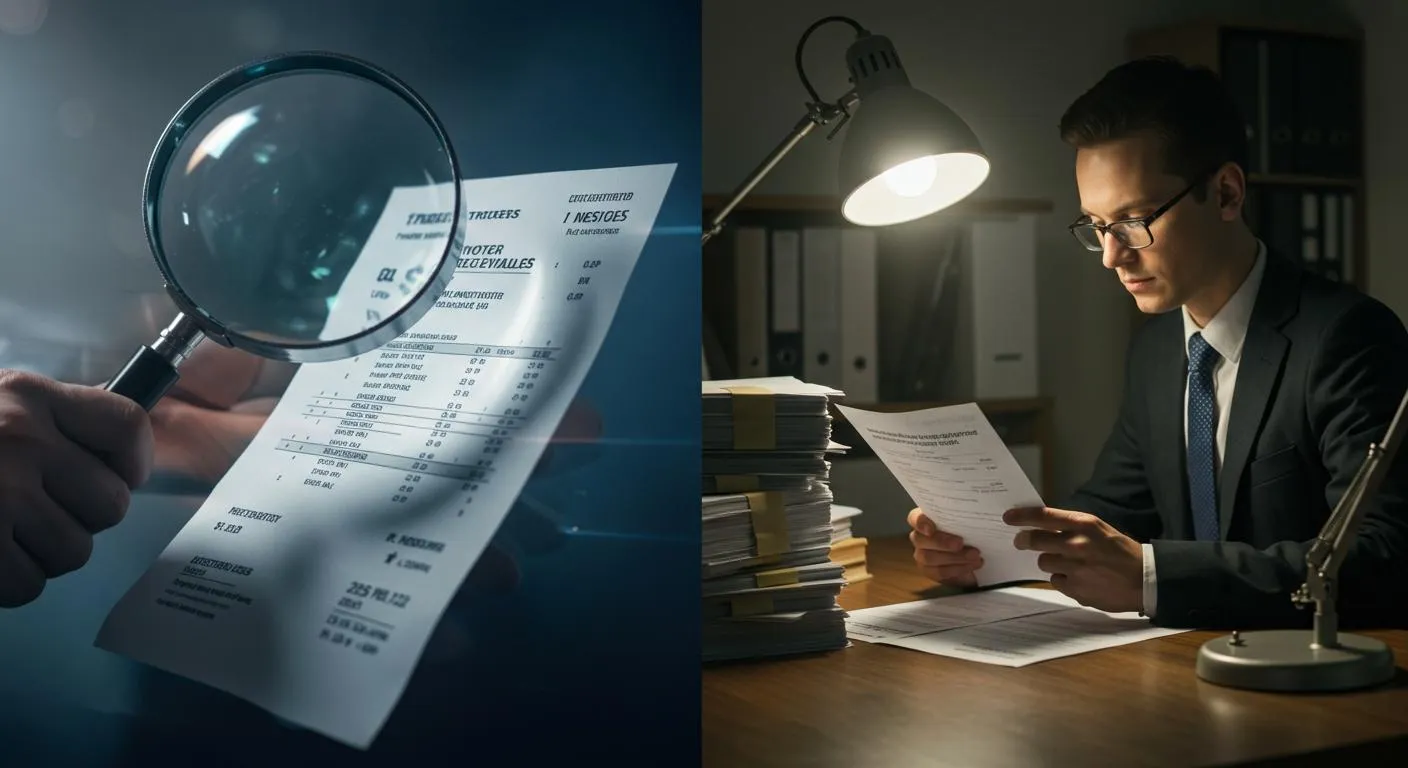
審査対象と内容の違い
ファクタリングと融資は「資金調達」という目的は同じでも、根本的な仕組みや審査基準がまったく異なります。最大の違いは「審査の対象」と「求められる証明・確認項目」です。
ファクタリングでは、審査の中心は売掛金そのものに置かれます。「売掛先がどんな会社か」「債権が実際に存在しているか」が最大のチェックポイント。売掛先が大手企業や官公庁であれば、中小企業や創業間もない会社でも通過率が高くなります。一方、ファクタリング利用企業自体の財務状況や経営実績は、さほど厳しく問われません。「自社の信用ではなく、取引先の信用が資金調達力を左右する」という点が大きな特徴です。
融資はこの逆で、「借り手である企業・個人の信用力」が審査の中心。過去の決算や現在の財務内容、代表者の経歴や過去の借入・返済実績、保有資産、将来のキャッシュフロー予測など、多面的に検討されます。とくに銀行融資では、売上規模や利益率、資本構成、返済能力、経営者の資質まで詳細に評価。「信頼を“数字”で証明する」のが銀行型資金調達の本質とも言えます。
審査内容は、ファクタリングが「売掛金の発生・取引先との契約書・請求書・入金履歴」の確認が中心なのに対し、融資は「決算書・納税証明・事業計画・資金使途明細・返済計画書」など幅広い書類が求められます。
そのため、「審査にかかる期間」「準備すべき資料の量と難易度」も両者で大きく異なります。
【現場体験談:比較のリアル】
「新規の大型案件が決まり急ぎで資金が必要になったとき、最初は銀行に融資相談をしましたが、“1か月以上は審査に時間がかかる”との返事。並行してファクタリングを申し込んだら、2日後に必要な資金が確保できた。経営規模が小さい当社には、審査のスピードと柔軟性の違いがとても大きかった」(イベント運営会社・代表)
資金調達までの期間の違い
資金調達に要する時間は、両者の選択に直結する重要なポイントです。
ファクタリングの最大の強みは「スピード調達」。早いサービスでは最短即日~数営業日で現金が振り込まれます。
一方、融資は金融機関の審査プロセスに時間がかかり、特に銀行融資では1か月~2か月程度かかることも珍しくありません。ビジネスローンやノンバンク系は短期間(1週間~10日程度)で実行される場合もありますが、金利や条件は厳しくなりがちです。
この違いが実務上どう影響するかというと、「今すぐに資金が必要」な状況ではファクタリングが有力な選択肢となり、「事前に準備を進めておき長期的な事業計画に合わせた調達」には融資が適しています。
【参考:調達期間比較表】
| 手法 | 最短調達期間 | 一般的な調達期間 |
|---|---|---|
| ファクタリング | 即日~2日 | 2日~1週間 |
| 銀行融資 | 1週間 | 1か月~2か月 |
| ノンバンクローン | 即日 | 3日~2週間 |
手数料と金利の違い
ファクタリングの主なコストは手数料です。これは、売掛金の買取額に対して数%~20%程度が設定されます(取引先の信用や金額規模、契約方式で変動)。例えば、100万円の売掛金を2者間ファクタリングで現金化する場合、5%~15%程度の手数料がかかることが一般的です。
一方、融資のコストは金利です。借入金に対して年2%~10%前後の金利が課され、返済期間全体で支払う利息が発生します。公的融資や銀行の優遇金利では1%台も珍しくありませんが、ノンバンクやビジネスローンになると5%以上が普通です。
コスト比較は「一時的にまとまった現金が必要なときはファクタリング」「長期的にコストを抑えたいなら融資」という棲み分けが現実的です。
なお、ファクタリングは手数料以外にも「契約書発行費用」「譲渡登記費用」などが別途発生する場合があり、必ず見積書や契約書で総費用を確認しましょう。
契約内容・支払い/返済・法律・会計処理の違い
ファクタリングは「売掛金譲渡契約」であり、資産の売却という会計処理になります。
契約が完了すると、売掛先から代金が入金された時点で契約も完結します。返済義務はありません。
融資は「借入契約」で、負債として貸借対照表に計上されます。契約期間中は定期的な返済(元利均等返済や元金一括返済など)が発生し、遅延や滞納があると信用情報に記録されます。
また、法律面でもファクタリングは商法や民法の債権譲渡に基づく取引であり、金融商品取引法とは異なる扱いとなります。融資は金融商品取引法や貸金業法が関与し、行政監督下での運営が求められます。
この違いが、「会計上の分類」「税務申告上の処理」「債務超過リスク」などにも直結します。
【現場の注意点】
「ファクタリング会社の中には、実態は“貸付”に近いグレーな契約を結ばせる業者も存在。契約前には“売掛債権の譲渡か、単なる借入か”を必ず確認。わからない場合は専門家や公的機関に相談した方が安全です」(中小企業診断士)
ファクタリングと融資のメリット・デメリット

ファクタリングのメリット
ファクタリングの最大のメリットは資金調達のスピードです。
多くのサービスで「即日入金」や「最短2営業日以内の現金化」が可能であり、急な支払い・突発的な経営課題にも柔軟に対応できます。
また、ファクタリングは借入ではないため「信用情報に記録が残らない」「貸借対照表の負債が増えない」というメリットもあります。銀行融資やリスケ(条件変更)を検討中の企業にとって、信用情報や今後の金融交渉に影響しない資金調達は大きな安心材料です。
さらに、手続きが比較的簡単であることも利用拡大の要因です。申請に必要なのは、請求書や契約書・取引履歴などの基本的な書類のみ。経営者の個人保証や担保も不要で、創業間もない企業や個人事業主でも利用しやすい点が特徴です。
「一括現金化」や「売掛債権の一部のみ現金化」「複数の取引先分をまとめて現金化」など、資金繰りの自由度も高く、さまざまな経営状況にフィットします。
【経営者の実感】
「設立1年目で銀行からの借入は難しかったが、ファクタリングを利用して販促活動の資金を確保できた。新しい取引先の拡大も順調で、結果的に経営の安定に直結した」(飲食チェーン運営・社長)
ファクタリングのデメリット
最大のデメリットは手数料の高さです。売掛先や取引規模によっては10%以上かかるケースもあり、資金調達コストとしては融資より割高になることが多いです。
また、ファクタリングは売掛先の信用や取引履歴が不十分な場合は利用できない(または手数料が大幅に上がる)ことがあります。資金調達額にも限界があり、売掛債権の範囲内でしか現金化できません。
さらに、取引先への通知が必要な3者間ファクタリングの場合、「自社の資金繰り状況が伝わることで取引先との信頼関係に影響が出る」などのリスクや懸念もあります。
「悪質な業者による高額手数料請求」「契約内容の不備によるトラブル」など、まだ法整備が十分ではない業界ゆえの課題も無視できません。
サービスを選ぶ際は、料金体系や運営会社の実績・評判を慎重にチェックしましょう。
【実際の悩み】
「数回利用したが、毎回手数料が予想以上に高く、結局現金化できる金額が少ない。事前に手数料シミュレーションと契約条件を徹底確認することが大切だと痛感した」(イベント企画業・経理担当)
融資のメリット
融資のメリットはなんといっても大きな金額をまとめて調達できる点と、金利が比較的低いことです。公的融資や銀行のプロパー融資なら、年利2%前後も可能。長期資金や設備投資など、数百万円~数千万円単位の資金調達に向いています。
返済期間も柔軟に設定でき、資金繰り計画を長期的に組み立てることができます。
「資金調達=会社の信用力構築」という側面もあり、実績を積むことで次回以降の融資枠拡大や他金融機関での調達にも有利になることがあります。
「売掛債権や不動産、保証人を活用して低金利を引き出す」「資本性ローンを組み合わせて自己資本比率を改善する」など、応用の幅も広いです。
【経営実例】
「3度目の銀行融資を受けて、必要だった新店舗用資金を一括調達。月々の返済計画を銀行担当者と緻密に作成し、無理なく返していける体制を整えられた」(アパレル業・経営者)
融資のデメリット
融資には審査が厳しいという大きな壁があります。
赤字や債務超過の状態では審査通過が極めて困難になり、担保や保証人が求められる場合もあります。
また、融資を受けると返済義務が必ず発生し、返済が滞れば信用情報に傷が付き、最悪の場合は資産の差し押さえや経営破綻につながります。
申請から入金までの期間も長く、「いますぐ現金が必要」というケースには間に合わないことも。消費者金融やノンバンクローンはスピード型ですが、金利負担が重くなります。
さらに、借入金は貸借対照表上の負債として計上されるため、財務健全性や資本調達力にマイナス影響を及ぼす場合もあります。
特に赤字決算や債務超過に陥っている企業の場合、新たな融資が難しくなったり、金利や条件が悪化する可能性もあるため注意が必要です。
【現場の声】
「審査が厳しく、何度も追加書類を要求されて苦戦した。返済義務がプレッシャーになり、経営判断の自由度が狭まる面もある」(製造業・経営幹部)
ファクタリングを選ぶべき状況

急な資金が必要な場合
ビジネスの現場では、予想もしないタイミングで「すぐに現金が必要」という状況が発生します。たとえば、急な大型注文や設備の修繕費用、従業員へのボーナス支払いなど、通常の資金繰りサイクルでは対応できないことも。
こうした「今すぐ」「なるべく早く」まとまった資金が必要な場面では、ファクタリングが非常に有効です。申込みから最短即日、遅くとも数営業日で現金が手元に届くため、銀行融資の審査を待つ余裕がないときには頼れる選択肢です。
ファクタリングの利用企業では、「支払い期限まで3日しかないが、売掛金の入金は1か月先」といった状況で活用する例が多いです。手元に未回収の売掛金さえあれば、現金化までの最短ルートが開かれます。
【体験談】
「夏の繁忙期直前、仕入先から“現金払いのみ”を要求されたが、取引先からの入金は翌月末。銀行融資は間に合わないと判断し、ファクタリングを利用。即日で資金を受け取り、無事に仕入れができた。緊急時のスピード感は本当に頼りになる」(飲食業・店長)
信用情報に不安がある場合
銀行融資では「信用情報」が重視され、過去に返済遅延や赤字決算があると審査で不利になります。しかしファクタリングは、企業自身の信用情報よりも売掛先の信用力が重視されるため、「過去に金融事故歴がある」「創業まもなく実績が少ない」といった企業にも門戸が開かれています。
信用保証協会の保証や第三者保証が不要なため、融資と比べて審査のハードルが低くなり、結果的に幅広い層が利用できるのも特徴です。
実際、「過去の税金滞納やカードローン延滞で銀行融資を断られたが、ファクタリングは利用できた」という声は多いです。売掛債権の価値や取引先の与信が担保になるからこそ、こうしたケースで活躍します。
【現場コラム】
「以前、資金調達に困っていた知人経営者が“もう借り入れは無理だ”と諦めかけていたところ、顧問税理士からファクタリングを勧められた。実際に利用して数百万円の資金を現金化し、危機を乗り切った。金融商品への理解が深まるほど、選択肢が広がると痛感した」(IT業・財務担当)
融資を選ぶべき状況

長期的な資金調達が必要な場合
企業が設備投資や人員拡充、店舗拡大など、長期計画に基づく大口資金を必要とするときは、融資が第一選択肢となります。ファクタリングは基本的に短期の資金需要向けで、売掛金の範囲内しか現金化できませんが、融資なら売上規模を超えた大きな金額の調達も可能です。
たとえば、事業拡大を見据えて1年~3年計画で資金を使いたい場合、返済スケジュールを企業の収支計画に合わせて調整できる融資は非常に合理的です。
月々の返済額を無理のない範囲で設定できれば、資金繰りの安定にも直結します。
【現場の実例】
「2店舗目のオープン資金を銀行融資で調達。1,000万円以上の金額はファクタリングでは到底まかないきれないので、返済期間5年の計画を組み、無理なく資金を回している。大きな夢には、長期返済の融資が不可欠と実感した」(美容サロン経営)
低金利での借入を希望する場合
融資の最大の魅力は金利の低さです。銀行や公的機関の融資であれば年利2%以下も可能で、手数料型のファクタリングと比べると長期的なコスト負担を大きく抑えられます。
「返済義務がある」というハードルはありますが、安定した事業計画がある企業や、すでに銀行との信頼関係が築けている場合、最も合理的かつ安価な資金調達方法となります。
銀行融資の場合、低金利だけでなく「追加融資や他行への紹介が受けやすい」「信用力の証明になる」などの副次的なメリットもあります。今後の事業拡大や新たな取引先開拓を見据えるうえでも、低金利での資金調達は大きな武器です。
【経営者の声】
「資金繰りが安定し始めたタイミングで、銀行に長期融資を申し込んだ。過去のファクタリング利用とは異なり、2%未満の金利で数百万円を借りられたのは大きい。毎月の返済負担も事前にシミュレーションできるので安心感がある」(製造業・経営者)
ファクタリングと融資の選び方

ビジネスの状況に応じた選択
資金調達の選択肢は多様化しており、「どちらが優れているか」ではなく「自社の状況や経営課題に最適な方法をどう選ぶか」が重要です。
まず経営者がすべきは、現状の資金繰りや将来のキャッシュフローを正確に把握すること。売掛金の回収タイミングや、今後の支出予定を可視化することで、短期的な資金需要なのか、長期的な成長投資なのかが見えてきます。
ファクタリングは、突発的な現金ニーズや、融資審査に不安がある企業に適しています。短期的な資金繰りの改善や、事業拡大初期の資金調達など、「今ある売掛金を最大限活用する」ための手段として効果的です。
融資は、長期の資金計画が立てられる、ある程度事業実績がある、信用力に自信がある場合に有力です。まとまった資金が必要なときや、事業を拡大・再構築するタイミング、低金利での調達を希望する場合には、返済計画をしっかり立てて融資を活用するのが理想的です。
両者の組み合わせも一つの戦略です。たとえば、短期的な現金ニーズにはファクタリング、長期資金や設備投資には融資というように、「事業ごと・時期ごとに使い分ける」ことで経営の安定と成長の両方を実現しやすくなります。
【現場のケース】
「急な資金需要はファクタリングで対応しつつ、長期的な成長計画には銀行融資を利用。双方のメリットを組み合わせることで、リスク分散と資金の最適化が図れた」(製造業・経営管理部)
専門家の意見を参考にする
ファクタリングや融資は、どちらも資金調達の重要な選択肢ですが、条件や契約内容、業者・金融機関ごとのサービス内容は多種多様です。情報収集や比較検討を怠ると、不要な手数料や金利負担、思わぬトラブルにつながる恐れがあります。
信頼できる税理士や会計士、中小企業診断士など、資金調達や経営改善の経験が豊富な専門家のアドバイスを受けることで、自社にとって最も合理的な方法や、最新の市場トレンドが把握できます。
また、複数の専門家や同業者の意見を比較検討し、多角的に判断することで失敗リスクを抑えやすくなります。
「どのサービスが自社の業態に合うのか」「どんなリスクや落とし穴があるのか」「過去にどんな成功・失敗事例があるのか」など、外部の知見を積極的に活用しましょう。
【専門家コラム】
「資金調達は“調べたもの勝ち”。各サービスの公式サイトで料金シミュレーションを使ったり、複数社の見積もりや契約条件を徹底比較するのが成功の第一歩です。特に新しいオンライン型サービスは、専門家にも一度確認を取るとより安全です」(中小企業診断士・資金調達アドバイザー)
ファクタリングのリスクと対策
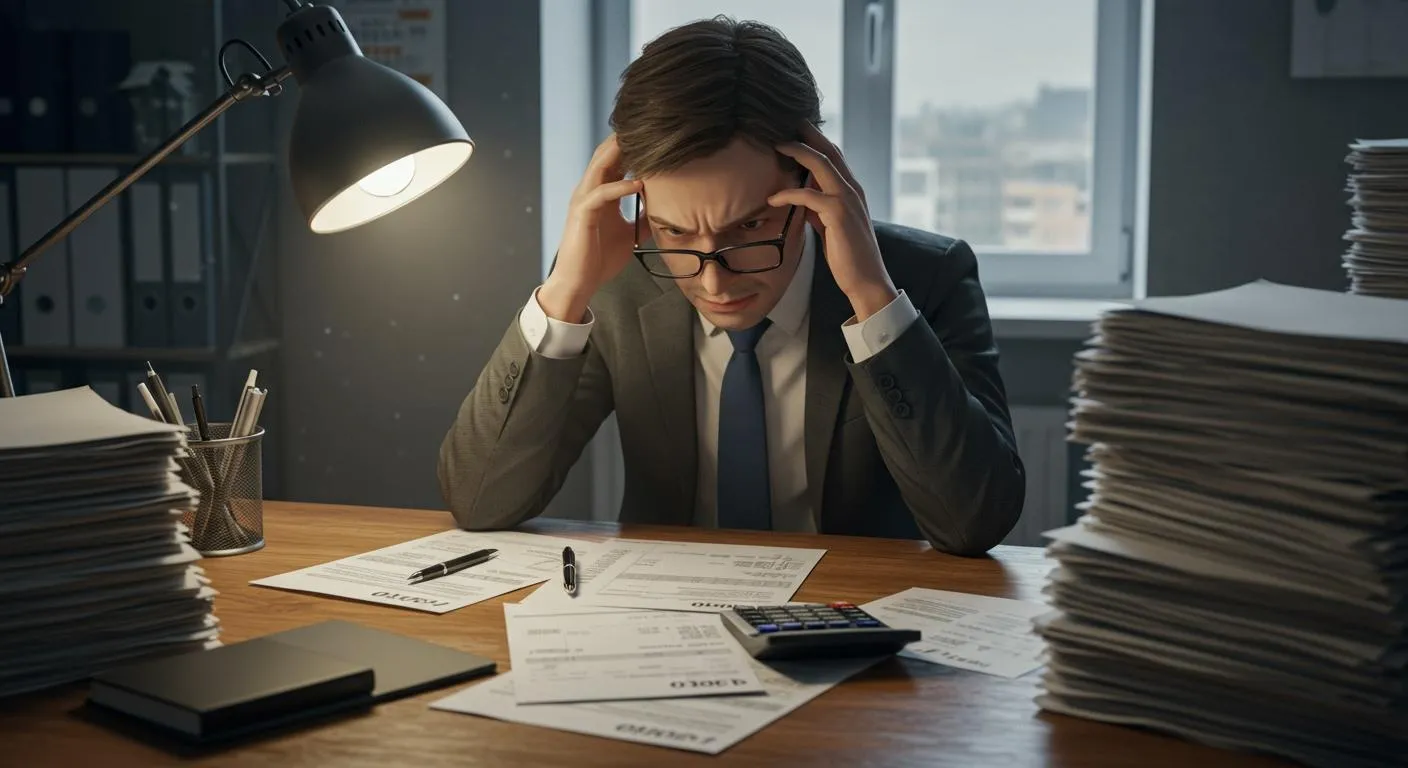
ファクタリングに関するリスク
ファクタリングは便利な資金調達手段ですが、いくつかのリスクも存在します。
まず資金調達コストが高い場合がある点です。急いで契約を結ぶと、想定以上の手数料や諸費用が発生し、最終的な手元資金が大きく減ることがあります。
また、取引先がファクタリングの利用を知ったことで「資金繰りに困っているのか」と不信感を持たれ、信頼関係に悪影響を及ぼすケースも。特に3者間ファクタリングは売掛先への通知が前提となるため、十分な説明や事前合意が重要です。
さらに、契約内容を誤解したまま手続きを進め、思わぬトラブルに発展するリスクも無視できません。例えば、ノンリコース(償還請求権なし)と思って契約したら実際はリコース(債務引受義務あり)だった、といったケースが実際に報告されています。
【失敗事例】
「ネット広告で見つけたファクタリング業者と契約したところ、手数料が20%以上で、資金繰りは改善したが利益がほぼ残らなかった。契約内容もわかりづらく、後から知人に相談して問題点に気づいた」(小売業・経営者)
悪質な業者の場合、「実質は貸付なのにファクタリングと称している」「手数料以外に高額な保証料や運営費が追加でかかる」などのトラブルも。運営会社の実績や口コミ、行政処分歴の有無など、事前調査が非常に大切です。
リスク対策の方法
ファクタリング利用時のリスクを抑えるには、いくつかのポイントがあります。まず契約書の内容を細かく確認し、わからない点は遠慮せず業者や専門家に質問しましょう。料金体系、手数料、返金義務や債務引受の有無、トラブル時の対応など、疑問点をすべてクリアにしてから契約に進むことが不可欠です。
次に、信頼できる業者選びが何より大事です。大手や行政認可を受けた事業者、実績・利用者の多い業者を優先し、ホームページや比較サイトの情報、口コミも参考にしましょう。あわせて複数業者から見積もりを取り、条件や対応力を比較するのも有効です。
資金調達の手段をファクタリングだけに絞らず、融資や他の方法と併用してリスク分散を図るのもリスク管理の基本です。経営計画に合わせて、短期資金はファクタリング、長期は融資といった組み合わせが有効な場合も多くなっています。
【専門家のアドバイス】
「見積もりや契約条件の比較を怠ると、想定以上のコストや契約リスクに気づかないまま取引してしまう。契約前の下調べと、少なくとも2~3社の比較は必須です。万が一トラブルが起きた場合は、金融庁や消費者庁、中小企業庁などの公的相談窓口も積極的に活用しましょう」(ファイナンシャルプランナー)
ファクタリングと融資の利用事例

成功事例の紹介
実際にファクタリングや融資を活用し、経営改善や成長に結びつけた企業の事例は数多く存在します。ここでは代表的なケースを紹介します。
【ケース1:ファクタリングで資金ショートを回避】
地方の建設会社C社は、年度末の大型プロジェクトで工事代金の入金が遅延。仕入れ業者や下請けへの支払いが迫る中、銀行融資は審査に時間がかかり間に合わない状況でした。C社は保有していた売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、2日後には必要な現金を確保。結果的に信用不安を回避し、すべての支払いを期日どおりに完了。経営者は「ファクタリングがなければ信頼を失っていた」と振り返ります。
【ケース2:創業間もない飲食店が融資で拡大】
首都圏の飲食店D社は、開業資金の大半を自己資金で賄いましたが、早々に2号店出店の話が浮上。初期投資を賄うため、日本政策金融公庫に事業計画書を提出。創業融資を活用し、500万円を年1.8%の低金利で調達。返済計画も無理のない範囲で組み、半年後には安定的なキャッシュフローを確立。店舗拡大を実現した好事例です。
【ケース3:ファクタリングと融資の併用で危機脱出】
アパレル系EC事業者E社は、繁忙期に複数の大口取引が重なり、資金繰りが逼迫。短期資金はファクタリングで即時調達し、設備拡大や新規システム導入の長期資金は銀行融資を活用。「短期・長期を分けた調達戦略で乗り切れた」と経理責任者は語っています。
失敗事例の分析
一方で、資金調達において失敗したケースやトラブルに見舞われた事例も少なくありません。
「失敗の原因」と「教訓」を明確にしておくことは、今後のリスク回避に直結します。
【ケース4:高額手数料による赤字転落】
小規模な広告代理店F社は、ファクタリング会社との契約を急ぎすぎて手数料率の高さ(15%超)を見落とし、複数回利用した結果、利益がほぼ消失。毎月現金化するたびに「資金繰りは楽になったが、経営は苦しくなった」という本末転倒の状況に。契約条件やシミュレーションを軽視したことが失敗の原因でした。
【ケース5:融資返済計画の甘さが倒産リスクに】
地方の小売店G社は、事業拡大のため安易に追加融資を重ね、最終的に返済負担がキャッシュフローを上回り、債務超過に陥る寸前に。経営改善計画を早期に専門家へ相談し、条件変更や返済猶予で何とか倒産は回避。経営者は「返済能力の見極めを怠ったことが一番の反省点」と語っています。
こうした失敗例からは「目先の現金調達だけでなく、手数料・金利・返済能力・長期の収支見通しまで総合的に判断すること」「契約内容の細部確認や第三者のアドバイスを受けること」の重要性が浮き彫りになります。
まとめ

ファクタリングと融資の総括
本記事では、ファクタリングと融資という2大資金調達手法を、実務的な視点と現場の声を交えて比較・解説してきました。
ファクタリングは「売掛金を即現金化したい」「審査スピードを重視したい」「信用情報に不安がある」「手続きの簡便さを求める」企業に強みがある一方、手数料の高さや信頼できる業者選び、取引先への影響などのリスク管理が欠かせません。
融資は「大口資金を調達したい」「長期的な資金繰りを安定させたい」「低金利で返済計画を組みたい」企業に向いていますが、審査の厳しさ、返済義務、財務体質への影響にも十分な注意が必要です。
どちらも万能な資金調達法ではありません。経営の状況や将来計画に合わせて、最適な方法を選択し、場合によっては両者の組み合わせも検討することが、健全な経営と持続的成長につながります。
今後の資金調達の選択肢
2026年以降、資金調達の選択肢はさらに多様化していくことが予想されます。
クラウドファンディングやオンラインレンディング、売掛債権を活用した新たなデジタルファイナンス商品、ノンリコース型の新しいファクタリングなども登場し、経営者にとって「選ぶ力」「調べる力」「比較する力」がますます重要になる時代です。
市場の動向や最新のサービス情報を継続的にチェックし、自社に最適な資金調達の方法を常にアップデートする習慣を持ちましょう。
経営者や財務担当者、個人事業主すべての方にとって、資金調達の知識と判断力がこれまで以上に問われる時代が到来しています。ぜひ、本記事の事例やポイントを参考に、より良い経営判断に役立ててください。
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




