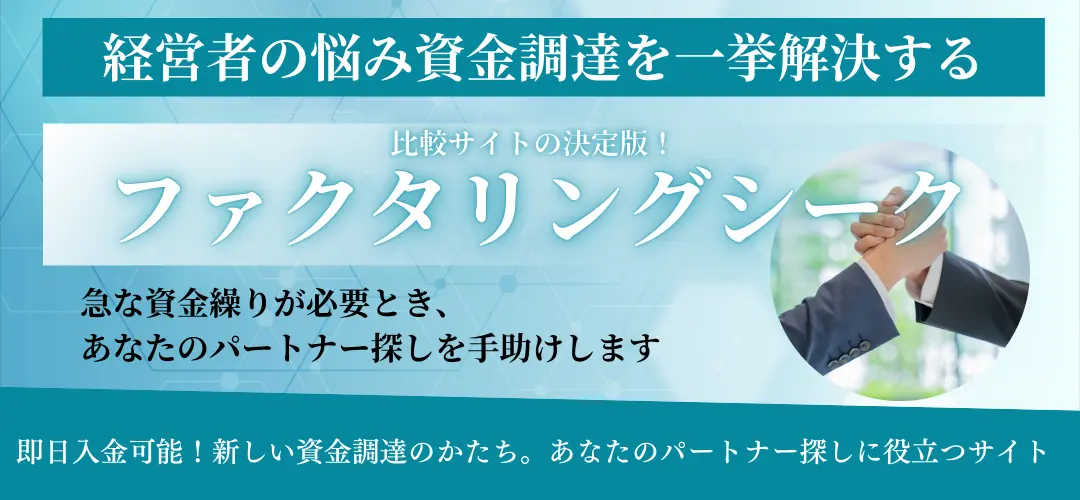重度障害者や通勤困難な障害者を雇用する事業主にとって、従業員の通勤は大きな課題です。この課題を解決し、障害者雇用を促進するために、「重度障害者等通勤対策助成金」という制度があります。本記事では、令和7年度(2025年度)版の通勤用バス購入助成金に焦点を当て、その申請資格、助成額、申請方法の概要をわかりやすく解説します。この助成金制度を理解し、活用することで、企業は障害者雇用の促進と従業員の定着率向上を実現できます。
重度障害者等通勤対策助成金とは?

助成金制度の概要
「重度障害者等通勤対策助成金」は、通勤が困難な重度障害者、知的障害者、精神障害者を5人以上雇用する事業主、または事業主団体を対象とした制度です。この助成金は、障害者の通勤を容易にするための措置として、通勤用バスの購入費用の一部を補助し、障害者の雇用促進と継続的な就労を支援することを目的としています。
なぜ通勤用バスの購入が重要なのか?
障害者の通勤には、個々の状況に応じた特別な配慮が不可欠です。通勤用バスの導入は、安全で快適な通勤環境を提供し、従業員のストレス軽減や定着率向上に大きく貢献します。また、企業イメージの向上にも繋がるでしょう。
助成対象となる経費と令和7年度最新情報
助成の対象となるのは、通勤用バスの購入費用です。令和6年度の情報では、1台あたり上限700万円、経費の75%が補助されました。令和7年度の最新情報については、高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ウェブサイトで必ずご確認ください。制度の変更点や詳細な情報が掲載されています。
通勤用バス購入助成金の詳細:対象と要件

対象となる障害者の定義
この助成金は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを所持する、通勤に特別な配慮が必要な従業員を対象としています。具体的には、重度障害者、知的障害者、精神障害者などが該当します。
通勤用バスの要件
助成対象となる通勤用バスは、単なる移動手段ではなく、障害者の特性に合わせた特別な構造や設備を備えている必要があります。例えば、車椅子での乗降を容易にするリフトやスロープ、手すり、座席の配置などが考慮されます。
雇用継続の必要性
助成金を受けるためには、通勤用バスの購入が、対象となる従業員の雇用継続に不可欠であると認められることが重要な条件となります。バスの導入によって従業員の離職を防ぎ、安定した雇用を維持できる見込みがあることを示す必要があります。
中古バスは対象?購入先は?注意点まとめ
原則として、中古バスの購入は助成対象外となることが多いです。また、購入先についても、特定の関係会社からの購入は制限される場合があります。申請を検討する際は、事前に高齢・障害・求職者雇用支援機構に詳細を確認し、要件を満たすバスを選定することが重要です。
助成額と支給要件:いくらもらえる?

助成額の詳細
通勤用バスの購入費用に対し、1台あたり上限700万円、経費の75%が補助されます(令和6年度の情報)。ただし、令和7年度の助成額については、必ず最新情報を確認してください。
支給要件
支給要件としては、バスの納入完了、経費の支払い完了、所有権移転完了が必須です。これらの手続きが完了していることを証明する書類が必要となります。
他の助成金との併用
他の助成金との併用については、個別のケースによって判断が異なります。詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
申請の流れと必要書類:手続きをステップごとに解説

認定申請:発注・契約予定日の前日までに申請
通勤用バスの購入を検討している事業主・事業主団体は、バスの発注・契約を行う前に認定申請が必要です。申請は、発注・契約予定日の前日までに行いましょう。
事前着手の禁止と例外:事前着手申出書について
原則として、認定後に購入手続きを開始する必要があります。ただし、やむを得ない事情で認定前に着手する必要がある場合は、「事前着手申出書」を提出することで例外的に認められる場合があります。
支給請求:受給資格認定日から1年以内
受給資格の認定を受けた後、支給請求を行います。支給請求は、受給資格認定日から1年以内に行う必要があります。バスの納入完了、経費の支払い完了、所有権移転が完了していることが条件です。
申請に必要な書類一覧:申請書、事業計画書、見積書など
申請には、以下の書類が必要です。
- 障害者助成金受給資格認定申請書
- 事業計画書
- 見積書(バスの購入費用がわかるもの)
- その他、必要に応じて追加書類
申請書類の書き方と注意点
記入例とサンプル
申請書類の記入例やサンプルは、高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトで公開される予定です。2025年5月頃に最新情報が掲載される予定ですので、必ず確認しましょう。
審査に通る事業計画書とは?
事業計画書は、助成金の審査において重要な判断材料となります。重度障害者等の通勤における課題、通勤用バス導入による具体的な改善策、雇用継続への貢献などを明確に記載することが重要です。具体的には、バスの導入によって通勤時間が短縮される、安全性が向上する、従業員の負担が軽減されるといった具体的な効果を数値で示すと、より説得力が増します。
申請時の注意点とよくある質問(FAQ)

事前着手について
重度障害者等通勤対策助成金を申請する際、原則として事前着手は認められていません。バスの購入契約前に認定を受ける必要があります。ただし、事情により事前着手が必要な場合は、必ず「事前着手申出書」を提出してください。
申請書類の不備
申請書類に不備があると審査が遅れる原因となります。提出前に再度確認し、不明な点は事前に各都道府県支部に問い合わせましょう。
審査期間
審査期間は申請内容や時期によって異なりますが、通常数週間から数ヶ月程度かかる場合があります。余裕をもって申請することをおすすめします。
よくある質問
よくある質問としては、「中古バスは対象になるか?」「助成金の支給対象となる障害者の条件は?」などがあります。詳細については、高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトや各都道府県支部に確認してください。
問い合わせ先と参考情報:どこに聞けばいい?

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
制度全般に関する一般的な質問はこちらへ。
各都道府県支部の高齢・障害者業務課/窓口サービス課
具体的な申請手続きや、個別のケースに関する相談はこちらがおすすめです。事業所の所在地を管轄する支部に連絡しましょう。
高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ウェブサイト
助成金に関する最新情報や詳細な資料(PDF形式)は、公式ウェブサイトから入手できます。「重度障害者等通勤対策助成金」で検索してみてください。申請に必要な様式もダウンロード可能です。
令和7年度の変更点と最新情報

令和6年度からの変更点:最新情報をチェック
重度障害者等の通勤を支援する「重度障害者等通勤対策助成金」。令和6年度からの変更点として、申請書類や手続き方法の変更が予想されます。高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ウェブサイトで最新情報を確認しましょう。
今後の制度改正の可能性
障害者雇用の促進に向け、助成金制度は社会情勢に合わせて改正される可能性があります。通勤支援の対象範囲拡大や、助成金額の見直しなどが考えられます。常に最新の情報を把握しておくことが重要です。
最新情報を入手するための情報源
高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイト、各都道府県支部の高齢・障害者業務課などが情報源として有効です。補助金ポータルなどの情報サイトも活用し、自社に適した助成金情報を収集しましょう。
まとめ:通勤用バス購入助成金を活用して障害者雇用を促進しよう

障害者雇用促進への貢献
通勤用バス購入助成金は、障害者の雇用機会を拡大する上で重要な役割を果たします。通勤が困難な障害者にとって、専用バスの存在は就労への大きな後押しとなります。企業がこの助成金を活用することで、より多くの障害者が社会参加できる環境が整います。
今後の展望:より良い社会の実現に向けて
通勤用バス購入助成金は、障害者がより活躍できる社会の実現に向けた一歩です。企業と従業員が共に成長できる環境を整備し、誰もが平等に活躍できる社会を目指しましょう。この助成金制度を積極的に活用し、障害者雇用を促進することで、企業は社会貢献を果たし、持続可能な成長を実現できます。