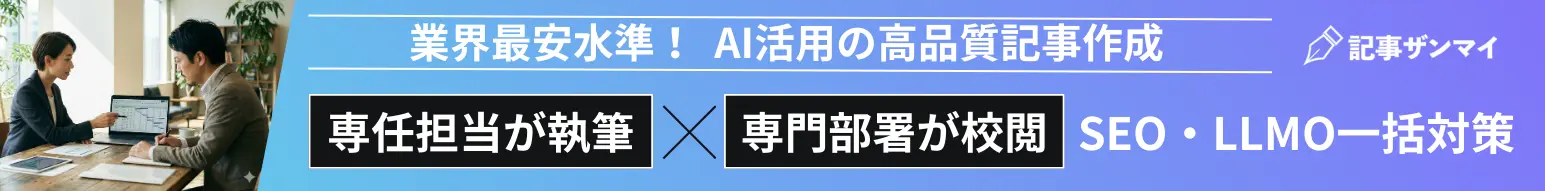キャリアアップ助成金の各コースについて、以下からご覧いただけます。
- 正社員化・処遇改善で最大80万円!キャリアアップ助成金の全コース【令和7年版】
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「正社員化コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「賞与・退職金制度導入コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「障害者正社員化コース」
キャリアアップ助成金の「賃金規定等共通化コース」は、パート・アルバイト・契約社員など非正規スタッフと正社員との“処遇格差”をなくし、全従業員に同じ賃金ルールを適用することを支援する制度です。
従来は正社員と非正規で異なる昇給・賞与・手当の規定を設けていた企業が、“全員に共通の賃金規定”へ見直し、適用する際に活用できます。
2025年度改正により、共通化の基準や助成内容がさらに明確化され、制度の使い勝手も向上しています。本記事では、「賃金規定等改定コース」との違いをはじめ、制度の全体像と実務現場でのポイント、申請・運用の具体例、現場の体験談まで徹底解説します。
キャリアアップ助成金の各コースについて、以下からご覧いただけます。
- 処遇改善で最大80万円!キャリアアップ助成金の全コース・支給額・申請ガイド【令和7年版】
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「正社員化コース」徹底解説
- 2025年最新版|キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」徹底ガイド
第1章 賃金規定等共通化コースの概要と「賃金規定等改定コース」との違い

賃金規定等共通化コースは、「非正規雇用の方にも公平な昇給や賞与、手当のルールを設けたい」と考える企業のための支援策です。
ただし、「賃金規定等改定コース」と混同されやすく、どちらを選ぶべきか悩む声が非常に多いのも現場のリアルな課題です。ここでは両者の違いを、なるべく噛み砕いて分かりやすく解説します。
- 賃金規定等改定コース: 非正規スタッフにも“昇給制度”を新たに導入、あるいは既存の昇給ルールをより良く改定することが目的。たとえば「今まで昇給ルールがなかったパートさんに、年1回の昇給制度を新設する」など。
- 賃金規定等共通化コース: 正社員と非正規スタッフ、全員に“同じ昇給や賞与のルール”を設けて運用することが求められる。たとえば「正社員だけにあった定期昇給制度や賞与支給ルールを、パート・アルバイトにも同じ内容で適用する」など。
| 賃金規定等改定コース | 賃金規定等共通化コース | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 非正規に昇給・賞与の制度を新設・改定する | 正社員と非正規の昇給・賞与ルールを一本化する |
| 適用範囲 | 非正規雇用のみ | 全従業員(正社員・非正規) |
| 典型例 | パートに昇給制度を初めて導入 | 既存の正社員向け昇給・賞与制度をパートにも同じ基準で適用 |
| 必要な取り組み | 非正規向け賃金規定等の新設・変更 | 全従業員共通の賃金規定等の作成・運用 |
- 今まで正社員しか昇給がなかった → 非正規だけに新設したい場合は改定コース
- 正社員と非正規でルールが分かれていた → 両者のルールをまとめて共通化したい場合は共通化コース
多くの企業では、まず「賃金規定等改定コース」で非正規スタッフの昇給ルールを整えた上で、会社全体の処遇格差をなくすために「共通化コース」を活用する流れも一般的です。自社の現状や目標に合わせて、最適なコースを選びましょう。
第2章 賃金規定等共通化コースの助成対象・支給要件・支給額

賃金規定等共通化コースは、単に「就業規則を変えればOK」というものではありません。国が示す要件を満たし、「本当に現場で運用できているか」まで審査されるため、注意が必要です。
ここでは、支給対象となる従業員や事業所の条件、助成対象となる取り組み内容、実際の支給額と加算要素について分かりやすく整理します。
- 支給対象となる企業・事業所:正社員・非正規を問わず「全従業員に共通の賃金規定等」を適用する中小企業・個人事業主・大企業も対象。ただし、雇用保険適用事業所であることが必須。事前に「キャリアアップ計画書」の提出が必要(場合によっては不要となるケースも)。
- 助成対象となる主な取り組み:「昇給制度」「賞与」「手当」などの賃金規定を全従業員共通の内容で新設または改定。就業規則等に明文化し、実際に6か月以上運用。運用期間中に昇給や賞与の支給などが実施されていること。
- 支給要件の主なポイント:昇給や賞与などが正社員・非正規を問わず同じ基準で適用されていること。昇給額や賞与支給額、適用人数などが国の基準値(例:一定金額以上、対象人数の割合)を満たしていること。規程改定後6か月間は同内容で安定的に運用されていること。必要に応じて労働局等の実地調査・書類確認に対応できること。
| 項目 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 1事業所あたりの基本額 | 1人あたり 最大50,000円 | 1人あたり 最大40,000円 |
| 加算例(対象者多数の場合など) | 人数に応じて加算あり | 同左 |
| 減額例(既存制度の一部改定など) | 内容によって減額・不支給も | 同左 |
※助成額・基準は年度や改正ごとに変更の可能性があるため、最新情報を必ずご確認ください。
- 昇給の金額や対象人数が基準未満だった、実際にはルール通りに支給していなかった場合などは不支給の典型例です。
- 適用前に就業規則や賃金規定のドラフトを労働局などに相談し、トラブルを未然に防ぐ事例が多いです。
第3章 申請手順と準備すべき書類・実務上の注意点

賃金規定等共通化コースの申請は、事前準備から支給決定まで複数のステップがあります。どの段階でも「書類の不備」や「制度運用が実態と伴っていない」ことで不支給となるケースが多く、実務的なポイントを丁寧に押さえることが重要です。以下、各段階ごとに具体的な流れと注意点を解説します。
- キャリアアップ計画書の作成・提出
原則、事前に労働局へ「キャリアアップ計画書」を提出します。会社の状況に応じた「賃金規定等共通化」の計画を具体的に記載し、計画期間を設定してください。
※すでに全員共通の賃金規定が就業規則上存在し、制度変更を伴わない場合など、例外的に提出不要となるケースもあります。 - 新しい賃金規定・就業規則の作成と社内周知
正社員・非正規雇用を問わず全従業員に共通の昇給・賞与・手当のルールを「就業規則」「賃金規定」として文書化します。作成後は従業員への説明や同意、掲示などで“周知義務”を満たすことが不可欠です。 - 新ルール運用開始・6か月間の継続運用
新しく策定した共通ルールを実際に6か月以上、現場で継続運用します。
・就業規則や賃金規定の変更届出書の提出(労基署)
・規定内容通りの昇給・賞与・手当の支給実績(賃金台帳等で証明)
運用中に解雇・雇用形態変更がある場合、対象者が助成対象外になる場合があるため注意しましょう。 - 支給申請書類の作成・提出
運用開始から6か月経過後、必要な添付書類(改定後の就業規則、賃金規定、賃金台帳、労働条件通知書、出勤簿、従業員リスト、労働保険関係書類など)を揃えて、管轄の労働局へ期限内(原則、運用終了2か月以内)に申請します。 - 審査・実地調査(必要に応じて)
書類審査や、必要に応じて職場の実地調査が行われます。書類不備や“実態と異なる運用”が発覚した場合は不支給となるため、日頃から帳簿・台帳の整備を徹底してください。 - 支給決定・助成金の入金
審査をクリアすれば支給決定通知が届き、指定口座に助成金が入金されます。
よくある書類・手続きミスと現場アドバイス
- 「就業規則」「賃金規定」の周知・従業員同意が不十分なまま申請 → 社内掲示・配布・説明会などで“周知の証拠”を必ず残す
- 賃金台帳・出勤簿・労働条件通知書などが最新の内容で揃っていない → 昇給・賞与の支給記録が帳簿で証明できるように管理を徹底
- 計画書や書類に矛盾点・食い違いがある → 事前に労働局へ相談・下書き確認してもらうのが安全策
第4章 現場でよくある疑問・トラブルと解決アドバイス

賃金規定等共通化コースを実際に活用する現場では、「申請書類の整備や就業規則の変更は難しくないのか?」「運用中に思わぬミスやトラブルが起きるのでは?」といった不安や疑問の声がよく聞かれます。ここでは、よくある現場の悩みとその対応策を、具体例を交えながら解説します。
よくある疑問・相談
- 就業規則や賃金規定の変更って、どのくらい大変?
└ 社労士や専門家に依頼すればスムーズに作成できるケースが多いですが、費用がかかります。社内で作成する場合は、厚生労働省の雛形やガイドを活用しましょう。 - 助成金の対象になる「共通化」の定義は?
└ “正社員と非正規雇用で同一の昇給・賞与・手当ルールを定めること”が必要です。書類上だけでなく、実際の賃金台帳・支払い記録でも共通ルールの運用実績が確認されます。 - 既存の従業員の理解や反発はどう防ぐ?
└ 制度導入の際は、「説明会」や「個別相談」の場を設け、不公平感や誤解が生じないよう丁寧に説明を行うことが大切です。経営陣の本気度や説明力が、制度の定着に大きく影響します。
実際に現場で起こりがちなトラブル
- 昇給や賞与の支給時期・対象が規定と違ってしまった
└ 対象者の入れ替わりや勤務日数・期間の誤認識などで、規定通り運用できないケースがしばしば発生します。
└ 事前に、全従業員の対象・非対象を一覧表やシステムで“見える化”しておきましょう。 - 申請期限や添付書類の不備で申請が却下された
└ 「6か月経過から2か月以内に申請」「添付書類の不足・記載ミス」など、手続きのルールを失念しがちです。
└ 忙しい時期に重なる場合は、事前に書類作成スケジュールやダブルチェック体制を確保することがポイントです。 - 申請内容に不明点や疑義が出た場合の対応
└ 不安な点は、都道府県労働局や専門家(社労士)に早めに相談しましょう。現場ごとに細かい解釈や運用基準が異なる場合もあります。
トラブル防止のワンポイント
- 「自社だけでなんとかしよう」とせず、疑問点や不安があれば積極的に労働局や専門家へ相談する
- 書類・規定・賃金台帳の内容を常に最新・正確に保つ
- 従業員とのコミュニケーションを丁寧に行い、不満や誤解を防ぐ
この章を参考に、現場での“あるあるトラブル”を未然に防ぎ、スムーズな申請と運用につなげてください。
第5章 現場体験談:実際に「賃金規定等共通化コース」を活用した企業の声

この章では、実際に賃金規定等共通化コースを活用した企業担当者の声・現場のリアルな体験談を紹介します。導入を検討している方がイメージしやすいよう、成功例・苦労した点・感じた効果など、実際の現場目線にこだわってまとめました。
もともと昇給はバラバラで人によって差があり、不満の声も上がっていました。制度を利用して“全員に毎年一律20円昇給”というルールを作成し、就業規則に記載・全員に説明。導入後、昇給額や評価の透明性が高まり、従業員の定着率アップにつながりました。
・工夫したこと:昇給時期を4月と決めてカレンダー管理し、台帳もデジタル化した
正社員と非正規の格差是正に取り組みたかったものの、「正社員のモチベーションが下がるのでは」という声や「パート・アルバイトの評価基準を作るのが難しい」といった課題も発生。社労士に相談しながら、丁寧な説明や個別面談を重ねた結果、導入後は社員同士の連携が強化されました。
・苦労したこと:規定変更の説明会で、具体的なシミュレーションやQ&Aを用意
書類作成や申請手続きは想像以上に手間がかかったが、最も大切なのは“現場で実際に昇給・賞与・手当が適用されているか”という実態の証明。現場リーダーと連携して、給与明細や賃金台帳を定期的にチェック・全員で制度の理解を深める工夫をしました。
・ポイント:実際の昇給や手当支給を、全従業員に毎回“見える化”した
忙しさのあまり、就業規則の変更届けや賃金台帳の一部添付漏れが発生。労働局からの照会や再提出指示で余計な手間と時間がかかりました。事前に専門家にチェックしてもらえばよかったと反省。
・学んだこと:申請期限・添付書類のダブルチェック体制が必須
これらの現場体験は、制度の導入・運用に悩む経営者や人事担当者にとって、実践的なヒントになるはずです。自社の状況に照らし合わせて、ぜひご活用ください。
第6章 賃金規定等共通化コースまとめ

賃金規定等共通化コースは、「非正規雇用」と「正社員」の格差是正に本気で取り組みたい企業・事業主にとって、大きなチャンスとなる助成金制度です。
単なる“ルール作り”や“書類対応”で終わらせず、現場の働き方・昇給制度の実態がしっかりと変わることが求められます。
申請時は、昇給ルールや賞与・手当の内容を就業規則・賃金規定に明記し、全従業員に公平に適用されているかを証拠書類で示す必要があります。
現場での運用実態がともなわなければ、申請しても支給が認められない場合もあるため注意が必要です。
実際の現場では、導入によって「定着率が上がった」「社内コミュニケーションが活性化した」といった前向きな声が聞かれる一方で、説明不足や申請ミスなどで苦労する例も少なくありません。
だからこそ、計画段階から専門家や労働局への相談を重ね、従業員への周知・フォロー体制までしっかり整備することが成功のポイントとなります。
会社全体の働き方改革や、長く安心して働ける職場づくりを目指す企業にとって、賃金規定等共通化コースの活用は大きな後押しになるはずです。
自社に最適な制度設計・申請を目指して、実際の現場目線での運用・改善に取り組みましょう。
参考リンク・公式情報
- 厚生労働省|キャリアアップ助成金 各コース一覧(公式ページ)
- 助成金ポータル|賃金規定等共通化コースの概要と対象要件
- 社会保険労務士田中浩ブログ|賃金規定等共通化コースのポイント(2024年度最新版)
- 島根労働局|賃金規定等共通化コース用 申請チェックリスト(PDF)
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する