
中小企業や小規模事業者にとって、人手不足や残業の増加、人件費の上昇は避けられない経営課題です。加えて最低賃金アップや働き方改革対応など、業務の効率化とコスト抑制を両立する必要に迫られています。しかし予算の制約から、設備導入やIT化、現場の見直しが進まないケースも少なくありません。
こうした経営課題の解決に役立つのが「業務改善助成金」です。この制度を活用すれば、設備導入・プロセス改善・従業員教育など幅広い生産性向上施策を実施しやすくなります。本記事では、業務改善助成金の最新制度や変更点、申請方法、活用事例まで詳しく解説。自社に合った支援策を活用し、効率的な業務運営と持続的な成長を目指しましょう。
業務改善助成金の基本:制度の概要と目的

業務改善助成金は、国が中小企業・小規模事業者の賃上げと生産性向上を強力に後押しするために設けた代表的な公的支援制度です。とくに、年々上昇する最低賃金への対応や従業員の処遇改善といった社会的課題に直面する事業者にとって、経営の安定と働き方改革の両立を実現する重要な支援策となっています。
この助成金の主な目的は、企業が事業場内最低賃金を引き上げる際、その実現を可能にするための設備投資や業務プロセスの改善、人材育成などにかかる費用を国が一部補助することにあります。たとえば、POSレジや自動釣銭機、ITシステム、業務効率化のためのDXツール、従業員のスキルアップを目的とした研修費用など、幅広い投資が対象です。
最低賃金の上昇は労働者の生活の質を高める一方で、経営者にとっては大きな負担となりがちです。そこで業務改善助成金を活用すれば、現場改善や設備投資を通じて生産性を高め、無理のない賃上げや従業員の定着率向上につなげることができます。さらに、2025年度は「物価高騰によるコスト増」への対応として特例措置も拡大されており、経済環境の変化にも柔軟に対応できる制度となっています。
なお、助成対象となる中小企業・小規模事業者の定義は業種や規模で異なります。たとえば、製造業であれば従業員300人以下かつ資本金3億円以下、卸売業は従業員100人以下かつ資本金1億円以下、小売業は従業員50人以下かつ資本金5,000万円以下など、業種ごとに詳細な基準が設定されています。自社が対象となるかは、必ず最新の厚生労働省公式サイトや手引きを確認しましょう。
令和7年度(2025年度)の変更点を確認:最新情報をチェック!
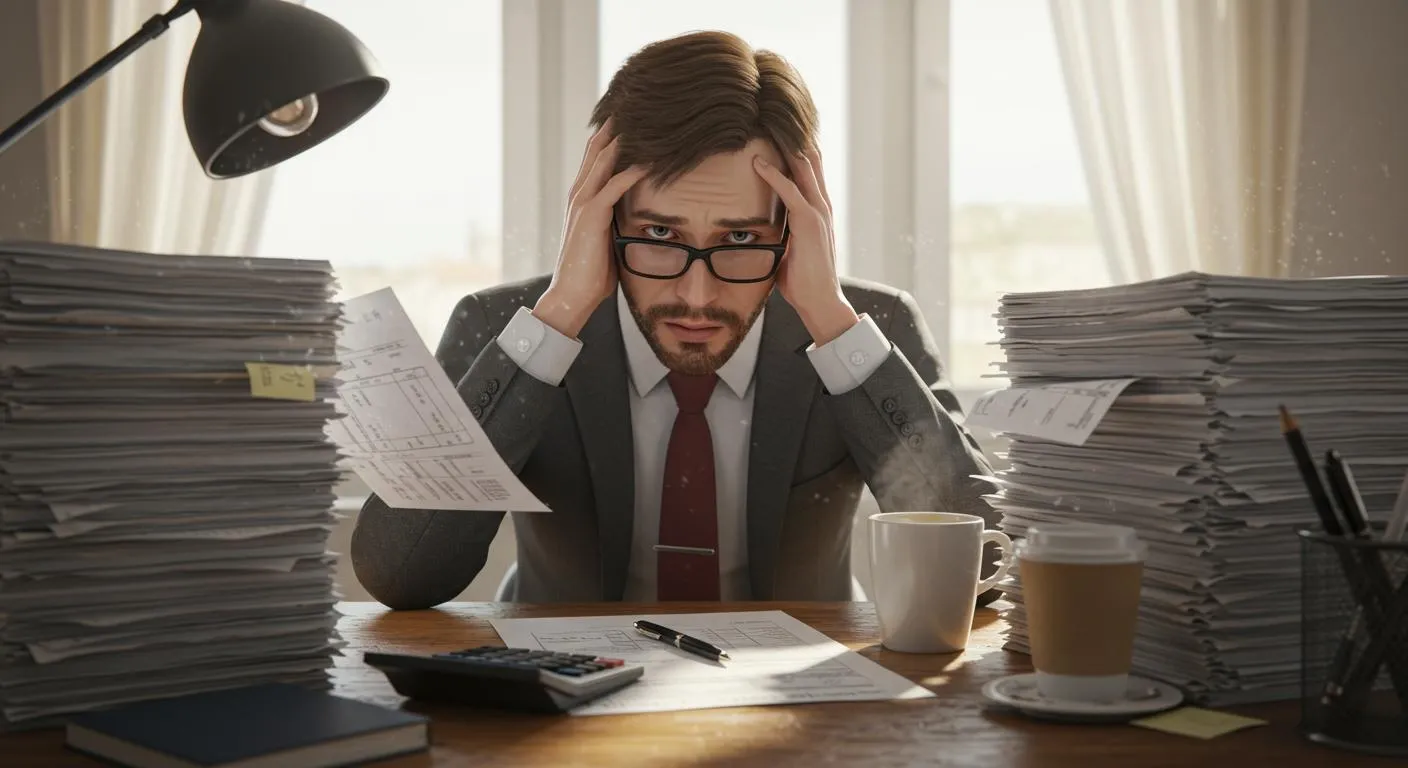
業務改善助成金は毎年度ごとに制度内容や申請ルールが見直されており、2025年度(令和7年度)も複数の重要な変更点があります。申請や導入計画の際は、必ず厚生労働省の公式情報をチェックしてください。
- 申請期間が2期制に
第1期:申請期間は4月14日~6月13日(賃上げ期間は5月1日~6月30日)
第2期:6月14日~地域別最低賃金改定日前日(賃上げ期間は7月1日~同日前日) - 事業完了・賃上げの実施完了期限
原則:令和8年1月31日まで(やむを得ない場合は理由書提出で令和8年3月31日まで延長可能) - 対象労働者の雇用期間要件が「6か月以上」に厳格化
昨年度(令和6年度)は3か月だったが、令和7年度は6か月以上の雇用実績が必要 - 助成額の上限は「事業主単位で600万円」
事業場ごとの上限ではなく、事業主全体での上限に統一 - みなし大企業は対象外
- 助成率の特例が再編
地域別最低賃金が1,000円未満の事業場のみ助成率4/5が適用 - 交付決定後の設備導入・支払い・賃上げが必須
交付決定前に発注や支払いを行った場合は助成対象外となる - 賃上げは一括実施のみが認められ、分割での賃上げは不可
- 事業実績報告書は、事業完了日から1ヶ月以内または翌年度4月10日までの早い方が提出期限
各都道府県や自治体の独自条件、加算措置、スケジュール変更などがある場合は、その都度最新の公募要領・公式発表をご確認ください。2025年度も物価高騰や人手不足など経済情勢に応じて特例措置が出る場合があります。
助成対象となる業務改善の取り組み:何が対象?

業務改善助成金の対象となる取り組みは、「賃金引き上げを無理なく実現し、事業場全体の生産性向上を図ること」を目的としています。単なる機器の導入や業務見直しにとどまらず、現場の働きやすさや効率化、人材育成まで幅広くサポートされます。近年は人手不足対策やDX推進、従業員満足度の向上など、経営課題に直結するテーマにも重点が置かれています。
- 設備投資:POSレジや自動釣銭機の導入は、会計業務を効率化し、レジ締めや現金管理のミス・時間ロスを大幅に削減します。また、ITシステムによる業務自動化は、受発注・在庫管理・売上集計などの手作業を省力化し、少人数でも高いパフォーマンスを発揮できる体制づくりに有効です。リフト付き車両の購入は、物流・福祉現場などで重労働や怪我のリスクを軽減し、高齢スタッフや女性の活躍推進にもつながります。省エネ機器や作業用機械の導入は、光熱費の削減だけでなく、最新設備による品質向上や生産効率UPも期待できます。
- 業務フロー改善:DXツール導入やペーパーレス化は、書類作成や伝票処理の手間を減らし、情報共有のスピード化・ヒューマンエラーの防止につながります。クラウド勤怠管理の活用により、従業員の打刻や残業集計、休暇管理を自動化でき、働き方改革の推進にも直結します。人手不足に悩む事業者が少人数でも回る体制を作るため、業務の標準化や無駄の排除にもこうしたツール活用は不可欠です。
- 専門家によるコンサルティング:外部の経営コンサルタントや中小企業診断士によるアドバイスは、現状分析から課題抽出、最適な業務改善策の提案・定着支援までを幅広くカバーします。たとえば、作業工程の見直しによるコストダウン、補助金活用の最適化、従業員の意識改革など、第三者の視点が加わることで、現場の“気づき”や抜本的な改革が進む事例も多く見られます。コンサル費用も助成対象になるため、専門知見を積極的に活用できます。
- 従業員の教育・訓練:現場スタッフへのスキルアップ研修や資格取得支援は、生産性向上やサービス品質の底上げに直結します。OJT(現場教育)の体系化や、外部セミナー・eラーニングの受講も幅広く対象です。特に中小企業の場合、一人ひとりの成長が組織全体の生産性に直結するため、人材投資は賃上げの原資確保や定着率アップにも大きな効果を発揮します。近年はデジタルスキル研修やリーダー育成プログラム、外国人労働者向け日本語研修など、多様な研修内容が活用されています。
助成対象経費は、機械装置やITシステム等の購入費、外部講師への謝金、専門家依頼費用、研修受講料など多岐にわたります。2025年度は「DX推進」「人材育成」も重要なキーワードとなっており、こうした分野の投資も積極的に認められています。最新の対象範囲や経費については、厚生労働省の公式資料で必ず確認しましょう。
助成額と助成率:いくらもらえるの?

業務改善助成金でもらえる金額や助成率は、「賃金引き上げ幅」と「対象となる労働者数」によって決まります。助成の上限額は、引き上げる金額が大きいほど、また対象となる従業員数が多いほど高くなります。さらに、事業場内の最低賃金水準や、物価高騰等の影響を受けた特例事業者かどうかによっても、助成率や上限額が変わります。
- 30円以上引き上げ(対象1~3人):上限50万円(助成率80%)
- 60円以上引き上げ(4~6人):上限100万円(助成率80%)
- 90円以上引き上げ(7人以上):上限150万円(助成率80%)
- ※賃金引上げ幅が大きい場合や、より多くの従業員を対象にした場合は、さらに高い上限額が設定されることもあります。
また、物価高騰の影響を受けている事業者や、特に地域経済を支える小規模事業者の場合、特例として助成率が最大90%に拡大する場合や、助成上限額が引き上げられるケースもあります。業種や事業規模、対象となる従業員の人数や賃金水準によっても細かく条件が分かれているため、申請前には必ず公式サイトの助成額シミュレーションや手引きで確認しましょう。
注意点
・助成金は、計画通りに賃上げを実施し、かつ認められた設備投資・取組が実績報告で確認された場合のみ支給されます。
・計画に記載していない設備の購入や、交付決定前に発注・支払いをした場合は対象外になるので注意が必要です。
・助成率や上限額は毎年変更される場合があります。特に令和6年度は物価高騰対応や賃上げ推進の強化で、例年より条件が優遇されています。
例:飲食業での活用イメージ
従業員3人の小規模飲食店が、時給を30円引き上げる計画を立て、POSレジ・自動釣銭機を導入した場合、導入費用の最大80%、上限50万円まで助成が受けられます。もし「物価高騰特例」の対象であれば、より高い助成率や上限額が適用される可能性もあります。
賢くシミュレーションを活用し、無理のない賃上げと設備投資を計画しましょう。最新情報や詳細な計算式は厚生労働省の公式ページや申請マニュアルでご確認ください。
申請から受給までの期間は、申請状況や審査状況によって異なりますが、数ヶ月程度かかる場合があります。早めの情報収集と計画的な準備が重要です。
申請条件:満たすべき要件とは?

業務改善助成金を申請するためには、複数の要件をクリアする必要があります。まず大前提として、中小企業または小規模事業者であることが求められます。業種ごとに定義が異なり、たとえば製造業なら「資本金3億円以下かつ従業員300人以下」、小売業なら「資本金5,000万円以下かつ従業員50人以下」など、具体的な基準が設けられています。
次に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金と同額以上であることも必須条件です。最低賃金を上回ることが前提となるため、まず自社の賃金水準が基準を満たしているか、必ず最新の地域別最低賃金一覧で確認してください。
さらに、過去1年間において労働関係法令違反がないことも重要です。不当な解雇や賃金の不払い、残業代の未払いなどがある場合は、不交付事由となり申請できません。また、助成金申請の直前に従業員を減らしたり賃金を引き下げたりした場合も、支給の対象外となるため注意が必要です。
そのほか、助成金を申請する全事業場で労働保険や社会保険に適正に加入していること、定められた提出書類がすべて揃っていることも要件となります。事業計画の内容が現実的かつ実行可能であるかも審査で重視されるため、申請前に十分な準備とチェックが欠かせません。要件の最新情報や詳細は、厚生労働省の公式ガイドや管轄労働局にて必ず確認しましょう。
| 業種 | 資本金の上限 | 従業員数の上限 |
|---|---|---|
| 製造業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車・航空機タイヤ・チューブ以外) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※業種分類や基準の詳細は公式ガイドで最新情報をご確認ください。
申請の流れ:ステップごとの詳細解説

業務改善助成金の申請から受給までは、いくつかの明確なステップがあります。初めての方でも迷わず進めるために、各段階ごとのポイントや注意事項もあわせて解説します。
- 交付申請
必要書類(事業計画書、経費見積書、労働者名簿など)を揃え、所轄の都道府県労働局またはオンライン窓口へ申請します。申請内容は審査のポイントとなるため、記載漏れや誤記には十分注意が必要です。 - 交付決定
申請後、内容審査が行われ、問題なければ交付決定通知書が発行されます。交付決定前に設備等の発注・購入をしてしまうと助成対象外になるため、必ず「決定通知到着後」に実施してください。 - 事業実施
交付決定された内容・計画に沿って業務改善の取組(設備投資や研修、コンサル活用など)を進めます。進行中に計画変更が生じた場合は、事前に労働局へ相談しましょう。 - 実績報告
すべての事業が完了したら、実績報告書・領収書・支払証明などの提出が必要です。証拠書類の紛失や内容不備は助成金の不支給リスクにつながります。 - 助成金支給
提出書類の内容確認・審査を経て、問題なければ助成金が指定口座に振り込まれます。通常、申請から受給までは数ヶ月を要しますが、混雑期や不備発生時はさらに遅れる場合もあります。余裕をもって計画し、早め早めの準備を心がけましょう。
申請時の注意点:失敗しないために
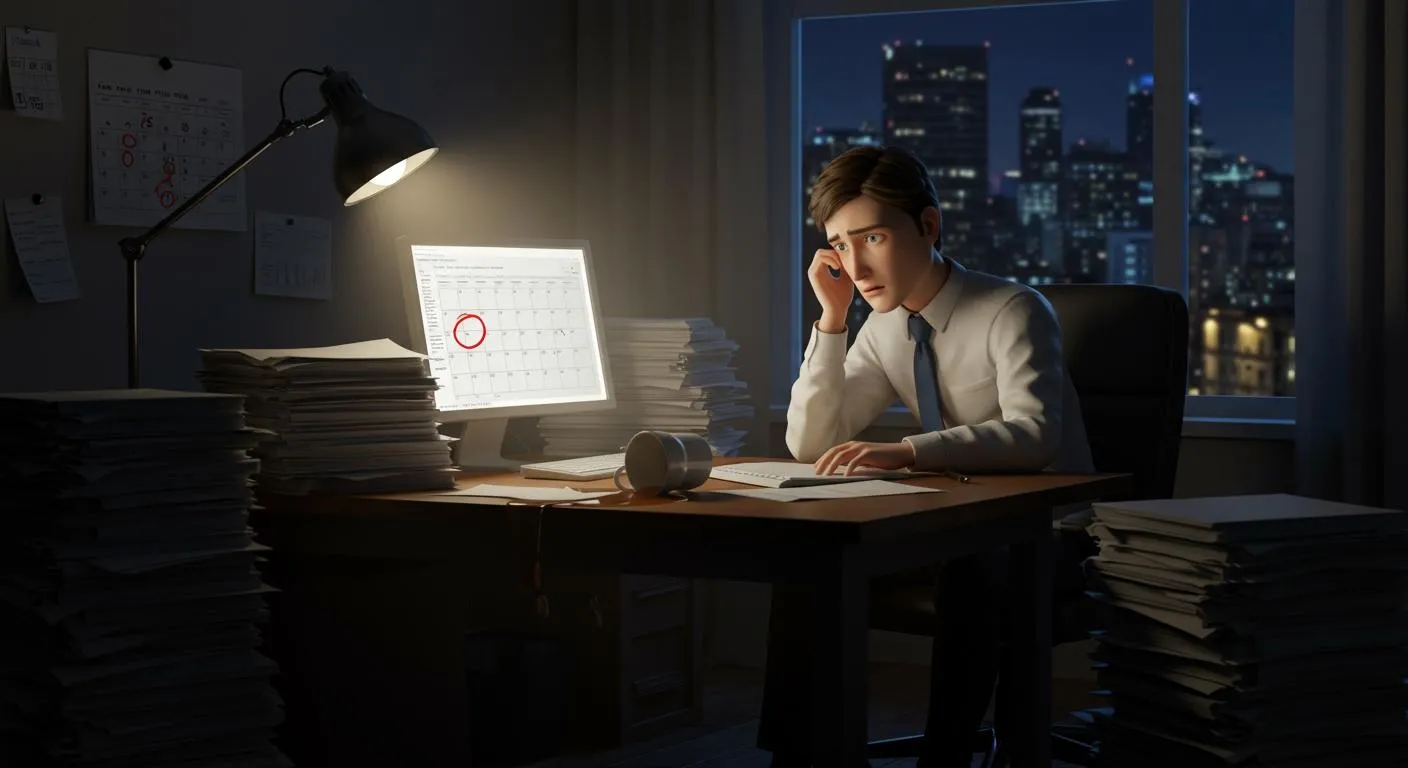
業務改善助成金は申請ルールが多く、思い込みや準備不足による不支給や減額も少なくありません。ここでは実際に現場で起きたトラブルの例と、必ず守るべきポイントを紹介します。
東京都内の製造業A社は、人手不足と業務効率化のために新型自動包装機を導入し、業務改善助成金も申請していました。しかし納期を急ぐあまり、交付決定通知の到着前に発注・設置を進めてしまい、交付決定日より前の発注・納品はすべて助成対象外となってしまいました。約120万円分の投資が全額自己負担となり、「事前に窓口に納期相談をしていれば避けられた」と大きく後悔する結果に。
教訓:必ず交付決定通知書が届いてから発注・納品・支払いを開始し、納期に不安がある場合は事前に労働局へ相談しましょう。
- 申請締切直前の提出で不備発覚、間に合わず申請自体が無効に
書類チェックや問い合わせが混雑し、修正が間に合わないケースが多数。
対策:提出は締切の1週間前には終えるのが鉄則です。 - 事業計画と違う内容(例:機種変更や対象者追加)を勝手に実施し減額・不支給に
計画変更は必ず事前相談と承認が必要です。
対策:迷ったら自己判断せず、すぐ相談を徹底しましょう。
申請前・実施前のチェックリスト
- 助成対象となる設備・研修内容・スケジュールが「事業計画書通り」になっているか
- 交付決定通知書の日付より前に発注・購入していないか
- 最新の申請期限・様式を厚生労働省や労働局のサイトで確認済みか
- 必要書類(領収書、見積書、賃金台帳、労働者名簿など)が全て揃っているか
- 進行中の計画変更・トラブルはすべて窓口に事前相談しているか
FAQ(よくある質問)
- Q. 見積は申請前に取ってもいいの?
- A. OKですが、発注・納品・支払いは必ず交付決定後に。
- Q. 締切当日の電子申請は間に合う?
- A. 混雑やエラーで受付不能になるリスクが高いので、余裕を持って提出しましょう。
- Q. 計画を途中で変えたくなった
- A. 必ず事前相談し、承認後に変更を実施してください。
業務改善助成金の活用事例:成功事例から学ぶ

業務改善助成金は、実際に多くの中小企業が生産性向上や賃上げを実現するために活用しています。ここでは主な業種ごとの成功事例と、助成金を有効活用するポイントを紹介します。
- 飲食業
従業員4名の個人経営の飲食店では、配膳ロボットの導入とPOSレジの最新機種への入れ替えを行い、注文や会計業務の自動化を実現しました。人手不足でもピーク時のオペレーションが安定し、従業員の負担が減少。さらに、賃金も時給50円アップを実施でき、スタッフの定着率も向上しました。 - 介護業
小規模デイサービス事業者が、リフト付き福祉車両を導入。高齢利用者の送迎が安全に行えるようになっただけでなく、従業員の腰痛や負担も軽減。設備導入費の大半を助成金でまかない、残った資金を従業員の資格取得支援や賃上げに充てることができました。 - 小売業
売上管理や在庫管理を手作業で行っていた地方スーパーが、クラウド型在庫管理システムを導入。商品の欠品や在庫過多が大幅に減少し、廃棄ロスも削減。生産性向上分を原資にパート従業員の時給を30円引き上げ、従業員満足度と顧客満足度の両立に成功しました。 - 製造業
金属加工工場で、従業員のスキルアップを目的に外部講師によるDX研修とITツール導入を実施。これまで手作業だった工程が自動化され、作業ミスやロスが減少。生産効率アップで残業が削減され、その分のコストを賃上げ原資に回せたという声もあります。
これらの事例に共通するのは、「助成金を単なる設備投資だけでなく、従業員の賃金や成長支援、働きやすさ向上にも役立てている」点です。自社の課題解決に向けて、実際の事例を参考に活用プランを考えてみてください。
業務改善助成金と他の助成金との併用:可能?不可能?

業務改善助成金は、原則として他の国・自治体の助成金や補助金と併用できる仕組みになっています。しかし、実際に併用する場合は「何に使うのか」「どの費用に適用するか」によって細かなルールや制限があります。
まず重要なのは、同一の設備投資・研修費用・賃上げ費用に対して二重で助成を受けることはできません。例えばPOSレジの導入に対して業務改善助成金を申請した場合、そのPOSレジ費用で他の補助金(省エネ補助金、IT導入補助金など)を重ねて申請・受給することはできません。同様に、同一の賃上げに対して二つの助成金を重複して適用することも不可です。
一方で、異なる対象経費であれば併用が可能です。たとえば、業務改善助成金でレジ導入、自治体独自の補助金でエアコン更新、別の国の補助金で防災設備を導入といったように、対象とする設備や取り組みが異なれば併用できるケースもあります。
また、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など、雇用関係の助成金との併用については制度の目的や時期が重複しないか慎重なチェックが必要です。制度趣旨が重なる部分では不可となる場合もあるため、注意が必要です。
最近は国の補助金と自治体補助金の併用に関する問合せやトラブルも増えています。申請前に必ず各助成金の公募要領や担当窓口で「併用可否」や制限条件を確認しましょう。複雑なケースや迷いがある場合は、社会保険労務士や補助金コンサルタントなど専門家のサポートを受けることをおすすめします。
実際、助成金の組み合わせ次第で数十万円から数百万円の資金差が出ることも。自社の事業計画や資金調達戦略を明確にし、最も有利な形で助成金を活用しましょう。
| 制度名 | 概要 | 併用例・注意点 |
|---|---|---|
| IT導入補助金 | 業務効率化・ITツール導入を支援 | 業務改善助成金で設備投資、IT導入補助金でソフトウェア・クラウド費用など用途を分けて申請可能。 同一費用の重複申請は不可。 |
| 省エネ補助金(省エネ設備導入支援事業等) | 省エネ機器・設備への入替支援 | エアコン更新やLED照明設置を省エネ補助金、レジや自動釣銭機を業務改善助成金など、設備ごとに分けて活用可能。 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規→正規転換・人材育成等の雇用施策 | 業務改善助成金で設備や賃上げ、キャリアアップ助成金で人材育成・正規化など対象・目的が異なれば併用可。 |
| 地方自治体独自補助金 | 各都道府県・市区町村が実施する中小企業支援 | 国の助成金と重複しない経費区分や別設備を対象にして併用可能な場合が多い。自治体によってルールが異なるため事前確認が必須。 |
| ものづくり補助金 | 生産設備や試作品開発、業務プロセス改革への投資支援 | 業務改善助成金と対象経費を分けることで併用実績あり。ただし同一設備・同一目的への重複申請は不可。 |
※あくまで併用例です。各制度の公式サイトや公募要領で最新の併用可否を必ずご確認ください。
申請代行サービスの活用:プロのサポートで安心

業務改善助成金の申請は書類が多く、ミスや不備があれば再提出や審査遅延、最悪の場合は不支給にもなりかねません。そのため、「本業が忙しい」「自社だけで申請に不安がある」という事業者の間では、申請書類の作成や手続きを専門家に依頼する申請代行サービスの利用が増えています。
申請代行サービスを使うメリットは、面倒な書類作成や証拠資料の整備、行政とのやりとりなど一連の手間を大幅に削減できる点です。特に初めての申請や時間的余裕のない企業では、本業に専念できるという安心感があります。
代行サービスを選ぶ際は、過去の実績(助成金採択件数や業種対応実績)、料金体系の明確さ(着手金の有無・成功報酬型かどうか)、サポート体制(申請後のフォローや書類修正への対応)を必ず比較検討しましょう。ウェブサイトの口コミや、初回相談での説明の分かりやすさも参考になります。
費用相場は、助成金受給額の10〜20%程度が多いですが、着手金・追加報酬・書類作成費など細かい費用がかかる場合もあるため、契約前に必ず詳細を確認しましょう。また、万が一不採択の場合の返金規定や、追加費用発生条件も要チェックです。
注意点として、助成金申請代行は行政書士や社会保険労務士など、国家資格を持つ専門家しか正式に行えません。無資格のコンサルや高額な前払い請求などには十分ご注意ください。助成金の受給額や代行費用は税務処理にも影響するため、経理・税理士とも相談しておくと安心です。
よくある質問:疑問を解消!

- Q. 何から始めればいいですか?
- A. まずは厚生労働省の公式サイトで最新の公募要領・手引きを確認し、自社が対象となるか、どのような設備投資や取り組みが助成対象となるかを確認しましょう。準備段階で専門家や支援機関に相談すると安心です。
- Q. 申請の難易度は?事業者だけでできる?
- A. 申請書類や事業計画書の作成には一定の手間がかかりますが、事業規模や内容によっては自社で完結することも可能です。初めての場合や複雑な申請内容の場合は、社会保険労務士や専門コンサルへの相談をおすすめします。
- Q. 助成金の支給タイミングは?
- A. 事業実施後に実績報告書などを提出し、内容審査を経て振込となります。交付決定前や事業完了前に助成金が支給されることはありません。
- Q. 交付決定通知前に設備発注した場合はどうなりますか?
- A. 交付決定日より前に発注・契約・納品した費用は全額助成対象外となります。必ず交付決定通知書が届いてから行動してください。
- Q. 事業計画を途中で変更したい場合は?
- A. 事前に労働局窓口に相談し、変更申請・承認を得た上で進める必要があります。無断変更は不支給や減額のリスクがあります。
- Q. 不採択や申請不備の場合の対策は?
- A. 書類の記載漏れや誤り、要件未達が原因です。申請前に公募要領のチェックリストや支援機関による事前確認を必ず行いましょう。改善後の再チャレンジも可能です。
- Q. 専門家への相談は有料ですか?
- A. 社会保険労務士や行政書士への申請代行は有料(報酬制)ですが、商工会議所や自治体窓口の無料相談も活用できます。
- Q. 他の助成金や補助金と併用できますか?
- A. 同一の設備・賃上げに対する重複受給はできませんが、異なる経費区分や異なる制度であれば併用可能な場合があります。申請前に各制度の条件を必ず確認してください。
業務改善助成金を最大限に活用するために
業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者が「生産性向上」と「賃上げ」の両立を目指すための強力な制度です。本記事では、制度の基礎から、申請条件、活用事例、注意点、併用可能な他の補助金・助成金、そして申請サポートまで徹底解説しました。
- 生産性向上・働きやすさアップに役立つ設備投資や研修、IT化が幅広く対象
- 必ず「交付決定通知後」に発注・契約・納品をスタートすること
- 申請は早め早めの準備・情報収集・計画的な進行が重要
- 同一費用への他助成金との“重複申請”には要注意
- 迷ったら厚生労働省・労働局や専門家への相談を活用
2025年度も物価高・人手不足・デジタル化など、経営環境は大きく変化しています。最新情報や公募要領は必ず公式サイトや自治体窓口でご確認ください。助成金を賢く活用し、業務の効率化・従業員の待遇改善を両立させることで、持続的な企業成長の実現を目指しましょう。
一歩踏み出すことで、補助金や助成金は“手の届く現実的な選択肢”となります。この記事が皆様の事業発展・働く環境の改善に役立つことを願っています。
外部参考リンク
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




