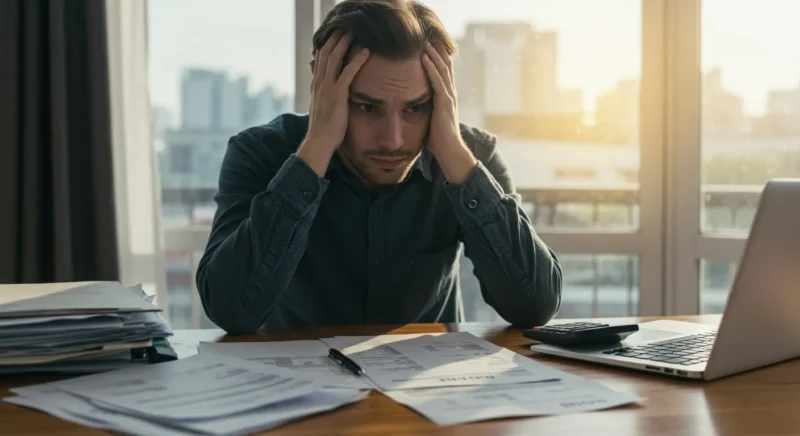企業経営において「資金繰り」は常に大きな課題です。特に中小企業やスタートアップでは、売掛金や手形の回収遅延によるキャッシュフローの悪化が事業の存続を左右する場面も少なくありません。本記事では、現代の資金調達手段として注目される「ファクタリング」と「手形割引」について、仕組み・メリット・デメリット・最新トレンド・業界実例を徹底解説します。2025年の法改正やデジタル化の流れ、現場でのリアルな成功・失敗体験も交え、経営判断に役立つ知識を網羅的にお届けします。
関連記事
ファクタリングと手形割引の基本概念

ファクタリングの定義と仕組み
ファクタリングとは、企業が自社の売掛金を第三者であるファクタリング会社へ譲渡することで、未回収の売掛金を早期に現金化し、即時の資金調達を実現する方法です。
一般的なファクタリングの流れは、以下の通りです。
- 企業が商品・サービスを提供し、売掛金(未回収債権)が発生
- 企業はファクタリング会社に売掛金を譲渡
- ファクタリング会社が一定の手数料を差し引いた現金を企業に支払う
- 売掛先(取引先)から売掛金が回収された際、ファクタリング会社が最終的に回収を受ける
この一連の仕組みにより、売掛金の回収までのタイムラグを解消し、企業は手元資金の即時確保とキャッシュフロー改善を実現できます。
近年は株式会社だけでなく、フリーランスや個人事業主向けのファクタリングサービスも登場し、資金調達の選択肢が広がっています。
【体験談1】ファクタリングで資金繰りの危機を回避!(中小製造業・経理担当Aさん)
取引先の入金遅延が相次ぎ、一時は従業員の給与支払いも危ぶまれた中、ファクタリングを活用することで即日数百万円の資金を確保できました。銀行融資では間に合わなかったため、本当に助かりました。
手形割引の定義と仕組み
手形割引は、企業が保有する約束手形を満期前に金融機関へ持ち込み、手数料(割引料)を差し引いた上で即時現金化できる資金調達方法です。
- 企業は取引先から受け取った手形を、金融機関や信用金庫などに提出
- 金融機関が手形額面から割引料(手数料)を引いた現金を支払う
- 満期時、手形の発行者(取引先)が金融機関に額面通りの資金を支払う
このプロセスにより、企業は手形の信用力を活用し、予定より早く資金を手にできるメリットがあります。
日本では「でんさい(電子記録債権)」など手形文化が根強く、資金繰りに悩む法人や商取引において多用されてきました。
ただし、手形割引の利用には「信用」や「発行企業の財務状況」などが大きく影響します。
【体験談2】創業直後の不安を救った手形割引(建設業・代表Bさん)
新規の大口取引で約束手形を受け取ったが、資材購入の現金が足りず、即時現金化が必要に。銀行の担当者に手形割引を相談し、手数料はかかったが無事に納期を守ることができた。
ファクタリングと手形割引の共通点

資金調達の迅速性
ファクタリングも手形割引も、共通してスピーディな資金調達が最大の魅力です。
通常の銀行融資では、審査・契約・実行まで数週間~1カ月かかることも多いですが、ファクタリングや手形割引なら最短即日・数日で現金化が可能です。
両者とも、手続きは比較的簡単で、企業側が必要な書類(売掛債権明細や手形原本など)を用意すれば、迅速に審査・入金まで進みます。
資金繰りの安定化・キャッシュフロー改善にも直結し、経営の柔軟性が増します。
【実務アドバイス】
- ファクタリング:オンライン申込で完結するサービスも登場、煩雑な手続きを大幅に削減可能
- 手形割引:地方銀行や信用金庫は、地場企業への支援・融資とセットで柔軟に対応するケースも
売掛金の流動化
両者に共通するのが「売掛金や手形を流動化=現金化」できる点です。
- ファクタリングは、売掛債権(未回収金)を売却して現金を得る
- 手形割引は、手形という証券を割引して資金化する
売掛金・手形が即現金化されることで、資金繰りに悩む中小企業や起業直後の法人でも、負債を膨らませずに資金を調達できるメリットがあります。
【体験談3】売掛金の流動化で新規投資を実現(IT業・経営者Cさん)
受注が拡大し資金が一時的に逼迫した際、ファクタリングで資金を調達。タイミングよく新規案件への投資ができ、結果的に売上増につながった。売掛金が“眠っている資産”から“使える資産”へ変わるインパクトは大きい。
ファクタリングと手形割引の主な違い

現金化の対象の違い
ファクタリングは「売掛金(請求済み・未回収金)」が現金化の対象ですが、手形割引は「受取手形(証券化された約束手形)」が対象です。
- ファクタリング…売掛債権の現金化。売掛金は幅広い商取引で発生しやすく、柔軟に対応可能。
- 手形割引…手形(証券)の現金化。発行や受け取りが一般的な業種・企業で利用。
この対象資産の違いにより、流動性や調達スピードも変化します。特に最近は、手形発行自体が減少傾向にあり、売掛金ファクタリングの利用が拡大しています。
【体験談4】売掛金型ファクタリングへの転換で資金繰り安定(物流業・経理担当Dさん)
以前は手形割引ばかり利用していたが、電子化・ペーパーレス化の流れで取引先が手形を発行しなくなり、ファクタリングへ切り替え。現金化までのスピードが上がり、資金繰り管理がしやすくなった。
審査基準の違い
ファクタリングは売掛先(取引先)の信用力が審査の中心。一方、手形割引は手形発行元の信用力が最も重視されます。
- ファクタリング…自社の与信より、取引先(売掛先)がしっかり支払いをするかが重視される
- 手形割引…手形を振り出した側(発行元)の信用調査がメイン。場合によっては自社の財務内容も審査
また、ファクタリングはオンライン審査やAI与信など「スピード重視型」のサービスも多く、手形割引より審査が簡素なケースが増えています。
手数料と金利の違い
ファクタリングは手数料(サービス料)が比較的高めに設定される傾向があり、手形割引は金利(割引料)が適用され、ファクタリングより低コストな場合が多いです。
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 主なコスト | 手数料 | 割引金利 |
| 相場感 | 2~10% | 1~5% |
| 入金までの速さ | 最短即日~数日 | 最短即日~数日 |
償還請求権の有無
ファクタリングはノンリコース型が主流で、売掛先が倒産・支払い不能になっても、請求権は基本的に買い取ったファクタリング会社に移転します(償還請求権なし)。
一方、手形割引は償還請求権あり(リコース型)が多く、不渡り時には企業側が責任を負うことに。
この違いが、企業側のリスク選好や資金調達戦略に影響を与えます。
ファクタリングのメリットとデメリット

ファクタリングのメリット
ファクタリングには、主に次のようなメリットがあります。
- 資金繰りの改善:売掛金を早期に現金化でき、運転資金を安定的に確保できる
- 迅速な資金調達:銀行融資よりも圧倒的にスピーディーに資金が手に入る
- 信用調査の負担軽減:審査の対象が自社ではなく取引先のため、自社の信用力が低い場合も活用可能
【体験談5】運転資金の悩みを一掃(飲食店経営・Eさん)
新規出店に伴う設備投資で一時的に資金が枯渇。銀行融資は書類が多く時間もかかり断念。知人に勧められたファクタリングを初利用し、書類提出から2日で数百万円を調達できて驚きました。
【実務アドバイス】
- 会計処理の際は「売掛金の譲渡」として帳簿に記載し、手数料分は費用計上するのが一般的です。
- 信用調査の負担が軽減される一方、売掛先との関係性や支払期日に注意が必要です。
ファクタリングのデメリット
一方、ファクタリングには以下のようなデメリットも存在します。
- 手数料の発生:売掛金額の数%~10%ほどの手数料がかかるため、資金調達コストが上昇する
- 顧客との関係への影響:売掛先がファクタリング会社への直接支払いとなる場合、取引先に資金繰り難が伝わることも
- 資金調達の限界:売上が減少すれば売掛金自体が減り、調達できる金額も減る
【実務アドバイス】
- ファクタリング利用時は取引先との信頼関係に配慮し、事前に説明・了承を得ておくことが大切です。
- 過度な利用は経営基盤を脆弱にするため、資金繰り表やキャッシュフロー管理も徹底しましょう。
【失敗談】手数料負担で経営悪化(小売業・F社)
売掛金回収遅延が常態化していたため、短期間に繰り返しファクタリングを利用。結果、手数料負担が積み重なり資金繰りがさらに悪化。資金繰り表の作成と経営改善の必要性を痛感しました。
手形割引のメリットとデメリット

手形割引のメリット
手形割引の主なメリットは次の通りです。
- 資金調達が迅速:受取手形を銀行や信用金庫に持ち込むだけで短期間に現金化できる
- 信用リスクの軽減:手形自体に信用が付与されているため、資金調達のハードルが下がる
- 柔軟な資金管理:手形の枚数や金額に応じて必要な時だけ現金化できる
【実務アドバイス】
- 長期的な取引関係がある場合、手形割引を活用することで資金管理がしやすくなります。
- 手形の信用度が高ければ、金利も比較的低く抑えられる場合があります。
【体験談6】老舗企業の資金計画と手形割引(老舗メーカー・経理Gさん)
長年付き合いのある取引先との商慣行で手形決済が中心。手形割引を計画的に使うことで、決算前の資金調整や急な設備投資にも柔軟に対応できました。
手形割引のデメリット
手形割引には以下のような注意点もあります。
- 手数料が発生する:割引料(実質的な金利)が発生し、資金調達コストとなる
- 手形の不渡りリスク:手形発行者が倒産や資金難に陥ると、最終的な支払い責任が割引利用企業に及ぶ可能性がある
- 資金繰りの不安定さ:商習慣や景気により手形発行自体が減ると、資金調達の選択肢が狭まる
【実務アドバイス】
- 手形割引を多用する場合、不渡りリスク管理と信用調査を徹底することが不可欠です。
- 不渡りリスクに備えて、与信限度や取引先選定基準も見直しましょう。
【失敗談】手形不渡りで連鎖倒産(部品製造業・H社)
主要取引先の資金悪化で受取手形が不渡りに。割引利用分の返済を求められ、一時は資金ショート寸前に。今では常に取引先の信用調査を欠かしません。
ファクタリングと手形割引の選び方

ファクタリングが適しているケース
ファクタリングは、次のような状況で特に有効です。
- 短期間でまとまった資金調達が必要な場合
- 取引先の信用リスクが高く、回収遅延が懸念される場合
- 売掛金の回収が遅れて資金ショートのリスクが高まっている場合
【体験談7】ITスタートアップの事業拡大(ITベンチャー経営・Iさん)
新規プロジェクトの受注は増えたものの、売掛金の回収が3カ月先。ファクタリングで迅速に資金調達し、人件費や開発投資に充てることができ、成長スピードを維持できました。
【専門家アドバイス】
- 「黒字倒産」を防ぐためにも、資金繰りの早期警戒シグナルを見逃さず、必要時はファクタリングも検討しましょう。
手形割引が適しているケース
手形割引は、以下のようなケースで有効です。
- 長期的な資金計画を立てている場合
- 安定した取引先があり、手形の発行が商慣行となっている場合
- 手形決済が一般的な業種や地域である場合
【体験談8】製造業の安定成長と手形割引(製造業・経理Jさん)
主要顧客が全て手形決済。割引を活用することで期末資金を計画的に準備でき、資金繰り不安が一切なくなりました。景気変動が大きい業界ほど、計画的な資金管理が重要です。
【専門家アドバイス】
- 手形割引は安定性が高い一方で、手形発行が減少する傾向にも注意。資金調達手段を複数持つことがリスクヘッジになります。
ケース別選択基準 ― どんな時にどちらを選ぶべきか?
- 急な運転資金不足や、売掛金の回収が大幅に遅れている場合:
ファクタリングなら請求書発行から最短即日~数日で現金化できるため、短期のつなぎ資金に有効です。 - 伝統的な業種で取引先が大企業・信用力が高い場合:
手形割引を活用すれば安定した条件で資金調達しやすく、割引料も抑えられる場合が多いです。 - 取引先に知られずに資金調達したい場合:
2社間ファクタリングを選択することで、取引先への通知を回避できます。 - 手形文化が縮小した場合の代替手段:
2025年以降、手形割引の利用が制限される場面が増えるため、電子記録債権やファクタリングの検討が必要です。
ポイント:どちらの方法も「債権を現金化する」という根本は同じですが、審査の内容・スピード・コスト・リスクの所在が異なるため、自社の業態や資金繰りの緊急度に応じて慎重に選びましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. ファクタリングと手形割引、どちらが中小企業におすすめですか?
どちらも資金繰り改善に役立ちますが、短期的な資金調達や取引先の信用リスクが高い場合はファクタリング、長期的な取引や手形文化が残る業界なら手形割引が適しています。自社の状況やコストなどを比較して選びましょう。
Q2. ファクタリング利用時、取引先には知られるのでしょうか?
2社間ファクタリングなら取引先に知られず資金調達ができます。3社間ファクタリングの場合は取引先の同意が必要で、売掛金の支払い先がファクタリング会社に変わります。利用目的に応じて選びましょう。
Q3. 手形割引で不渡りが発生した場合、どうなりますか?
一般的に償還請求権付きのため、手形発行元が不渡りとなった場合は割引利用者が最終的な支払い責任を負います。事前の信用調査やリスク管理が大切です。
Q4. ファクタリングや手形割引の手数料・金利相場は?
ファクタリングは2〜10%、手形割引は1〜5%が一般的な目安です。取引内容や信用力、サービスによって異なるため、必ず複数社を比較してください。
Q5. ファクタリングと手形割引の税務処理や経理上の注意点は?
ファクタリングは売掛債権譲渡、手形割引は受取手形の売却として処理し、手数料や割引料は費用扱いです。決算や申告時の科目や証憑管理にも注意が必要なので、専門家に相談するのもおすすめです。
Q6. 2025年以降、約束手形が使えなくなるとどうなる?
約束手形は今後廃止の流れにあり、電子記録債権やファクタリングなどデジタル資金調達が主流になります。オンライン型サービスへの移行も進んでいます。
Q7. 不正なファクタリング業者や詐欺に注意すべきポイントは?
高額な手数料や契約内容の不明瞭さなどは注意が必要です。複数社の比較や実績、監督官庁への登録、口コミのチェックも忘れずに。不安な場合は公的機関や弁護士に相談してください。
約束手形の廃止とファクタリングの未来

約束手形廃止の背景
約束手形は長年日本の商取引で大きな役割を果たしてきましたが、2025年をもって商習慣上も法制度上も廃止・縮小の流れが強まっています。
- 歴史的役割:戦後から現在まで、取引の信用を担保する決済手段として活用されてきた
- 廃止の背景:下請け企業への支払い遅延問題や手形不渡りによる連鎖倒産など経済的な課題、働き方改革・キャッシュレス化の進展
- デジタル化の進展:電子記録債権(でんさい)やオンライン資金調達の普及でペーパーレス・即時決済が主流に
でんさい(電子記録債権)の台頭とファクタリングとの関係
約束手形の廃止に伴い、電子記録債権(でんさい)の利用が急速に拡大しています。でんさいは、インターネット上で債権の発生・譲渡・消滅を記録できる電子的な決済手段で、ペーパーレス・リアルタイム・安全性の高さが特長です。
ファクタリング会社も、でんさいに対応したサービスを続々と提供しており、電子記録債権を売掛金として即時にファクタリングする仕組みが一般化しつつあります。これにより、資金調達のスピードと利便性がさらに向上し、今後は「紙の手形・請求書」から「電子債権」へのシフトが加速するでしょう。
現場からのアドバイス: でんさいの導入は、取引先やファクタリング会社・金融機関との連携が不可欠です。今後の資金調達戦略には、電子債権を活用した「スマート資金調達」の視点が重要です。
【実務アドバイス】
- 2025年以降、手形文化の縮小による影響を受ける業界は資金調達の多様化・新しい手法への対応が必須となります。
- 「手形決済」→「売掛金の電子化」「ファクタリング・オンライン融資」へシフトする動きが加速しています。
ファクタリングの重要性の高まり
約束手形の廃止により、ファクタリングをはじめとした新しい資金調達手法の重要性がこれまで以上に高まっています。
- テクノロジー活用:AI審査・電子契約・オンライン完結型ファクタリングなどが普及し、スピードと透明性が格段に向上
- フィンテック企業の参入:中小企業でも利用しやすい新サービスが急増
- 経営管理の高度化:リアルタイムでキャッシュフローを可視化し、資金ショートを未然に防ぐ仕組みが広がっている
【現場の声】デジタルファクタリングの衝撃(中小企業経営・Kさん)
「でんさい」とクラウド会計の連携、AIによる与信判定で、申請から24時間以内に資金が振り込まれました。書類の郵送も不要で、資金調達の常識が大きく変わったと実感しています。
【今後の展望】
- ファクタリングの会計・税務処理、法改正情報、サービス比較、成功・失敗事例を学ぶことが資金調達戦略のカギ
- 複数手法の併用や、専門家相談による資金繰りの最適化が今後ますます重要になります
ファクタリングを活用するうえで重要なのが、正確な会計処理と税務申告です。売掛債権を譲渡した場合、受け取った資金と売掛金との差額(ファクタリング手数料)は「支払手数料」や「雑費」などの勘定科目で経費計上します。手続きが煩雑な場合や迷うケースも多いため、会計ソフトや顧問税理士と連携し、証憑類の管理も徹底しましょう。ファクタリングの税務処理は「売掛金譲渡益」に該当せず、手数料相当額は損金算入が認められる一方で、消費税の課税区分や印紙税の取扱いなど細かな論点も存在します。法改正によっても実務運用が変化するため、最新の制度動向を常に確認し、必要に応じて専門家へ相談する姿勢が欠かせません。
また、2025年以降は電子記録債権(でんさい)やオンライン型ファクタリングの普及、約束手形廃止など制度改正も急速に進んでおり、従来型の資金調達スキームからの転換を求められる場面が増えています。会計・税務だけでなく、電子契約やオンライン審査への対応も含め、社内フローや社外との連携体制を見直しましょう。
さらに、資金繰りの安定やリスク分散を図るには、ファクタリング単体だけでなく、銀行融資やビジネスローン、でんさいなど複数の資金調達手法を組み合わせて活用することが有効です。各手法のメリット・デメリットやコスト、審査基準などを比較検討し、自社の業態や成長戦略に合わせた最適な資金調達ポートフォリオを構築することが今後の企業経営の大きなポイントとなります。