
障害のある方が働きやすい環境を整備することは、企業の社会的責任を果たす上で不可欠です。国や地方自治体は、障害者雇用を積極的に推進する事業主を支援するため、様々な助成金制度を用意しています。本記事では、これらの助成金制度をわかりやすく解説し、職場環境の向上と企業の成長をサポートする情報を提供します。
助成金制度の目的と概要

障害者雇用を促進する助成金制度は、障害のある方の雇用機会を増やし、職場への定着を支援することを目的としています。障害者が能力を最大限に発揮できる環境を整備することで、企業全体の生産性向上にも繋がります。
障害者福祉施設設置等助成金とは?
「障害者福祉施設設置等助成金」は、障害のある従業員の福祉を増進するための施設設置や整備にかかる費用の一部を助成する制度です。例えば、保健室、休憩室、食堂などの設置や、これらの施設を利用しやすくするための玄関、廊下、トイレなどのバリアフリー改修が対象となります。
助成対象となる施設の種類:「福祉施設等」の定義
助成の対象となる施設は、障害のある従業員の福祉を増進するための施設です。具体的には、保健室や休憩室などの保健施設、食堂などの給食施設が挙げられます。また、これらの施設を利用しやすくするための玄関、廊下、階段、トイレなどの付帯施設も対象となります。これらの施設はまとめて「福祉施設等」と呼ばれることがあります。例えば、車椅子利用者のためのスロープ設置や、休憩室の畳をタイルカーペットに変更するなどの事例が挙げられます。
助成対象となる事業主と障害者の条件

助成金を受け取るには、対象となる事業主と障害者の条件を満たす必要があります。
助成対象となる事業主の条件:雇用保険適用事業所であること
助成金を受けられる事業主は、原則として雇用保険に加入している事業所であることが条件です。これは、雇用保険制度を通じて労働者の雇用を安定させるという助成金の趣旨に沿ったものです。
対象となる障害者の種類:身体障害者、知的障害者、精神障害者
助成金の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者です。これらの障害のある方が、事業主によって雇用され、その福祉が増進される場合に助成の対象となります。
福祉増進が図られるとは?具体的な事例で解説
福祉増進とは、障害のある従業員が働きやすい環境を整備することで、その生活の質(QOL)を向上させることを指します。例えば、車椅子利用者のためにスロープを設置したり、視覚障害者のために音声案内を導入したりすることが挙げられます。また、精神障害のある方が安心して休憩できるスペースを設けることも、福祉増進に繋がります。これらの取り組みを通じて、障害のある従業員が能力を最大限に発揮し、活躍できる環境を整えることが重要です。
助成率と支給上限額

助成金制度を活用する上で重要なのが、助成率と支給上限額です。
助成率:対象費用の3分の1
助成率は、対象となる費用の3分の1です。例えば、休憩室の改修費用が300万円の場合、100万円が助成されることになります。
支給上限額:通常の場合と短時間労働者の場合
支給上限額は、通常の場合と短時間労働者の場合で異なります。通常の場合(短時間労働者を除く)は、1人あたり最大で一定額までとなっています。短時間労働者の場合は、さらに上限額が設定されています。ただし、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者は、この制限を受けません。具体的な金額は、年度や制度改正によって変動するため、必ず最新の情報を確認してください。
同一事業所・事業主団体における上限額
同一事業所または同一事業主の団体につき、同一年度あたりにも上限額が設定されています。複数の施設を整備する場合や、グループ企業全体で申請する場合などは、特に注意が必要です。事前に担当窓口に相談し、上限額を確認することをおすすめします。
申請手続きの流れと必要書類

助成金を受け取るためには、定められた手続きに従って申請を行う必要があります。
受給資格認定申請:申請時期と必要書類
障害者福祉施設設置等助成金を受け取るには、まず受給資格の認定を受ける必要があります。申請時期は、工事等の発注契約日の前日、または売買契約締結予定日の前日までです。必要書類は、事業計画書、施設の図面、見積書などです。詳細は管轄の窓口に確認しましょう。
支給請求:申請時期と必要書類
受給資格認定後、実際に施設設置・整備が完了したら、支給請求を行います。申請時期は、認定日から1年以内です。必要書類は、工事完了報告書、支払いを証明する書類、写真などです。
事前着手申出書:認定前に着手する場合の注意点
原則として、受給資格認定後に工事等に着手する必要があります。しかし、やむを得ない事情で認定前に着手する場合は、「事前着手申出書」を提出する必要があります。ただし、事前着手を認められた場合でも、助成金が必ず支給されるとは限りません。
既存建物の改修:建築基準法適合証明の必要性
既存の建物を改修して福祉施設等とする場合、建物が建築基準法に適合していることを証明する書類が必要となる場合があります。建築士に依頼して、事前に確認しておきましょう。
認定事例:助成金活用で実現した職場改善

障害者福祉施設設置等助成金は、様々なケースで活用されています。具体的な認定事例を通して、どのようなケースで助成が受けられるのか理解を深めましょう。
車椅子利用者のためのスロープ設置
車椅子を利用する従業員のために、建物の入り口にスロープを設置する工事は、バリアフリー化を推進する上で重要な取り組みです。このような工事は、移動の円滑化を図り、職場の安全性を高めるため、助成の対象となります。
休憩室の畳をタイルカーペットに変更
休憩室の畳をタイルカーペットに変更する工事は、清掃の容易さやアレルギー対策として有効です。特に、アレルギーを持つ従業員や清掃の負担を軽減したい場合に、助成の対象となることがあります。
食堂入り口のドアを引き戸に改修
食堂入り口のドアを引き戸に改修することは、車椅子利用者や高齢の従業員にとって、非常に有効な改善策です。開き戸に比べて、少ない力で開閉できるため、利用者の負担を軽減し、より快適な食事環境を提供できます。
てんかん発作後の休憩室整備
てんかん発作を起こした従業員が、発作後に安心して体を休めることができる休憩室を整備することは、安全な職場環境を整備する上で非常に重要です。このような休憩室には、緊急時の対応に必要な設備やプライバシーを保護する配慮が求められます。
助成の可否判断:障害者の特性と職場状況の考慮
助成金の支給は、対象となる障害者の特性や職場の状況などを考慮して判断されます。例えば、視覚障害のある従業員のために、音声案内システムを導入する場合や、聴覚障害のある従業員のために、情報伝達手段を工夫する場合などが考えられます。これらの取り組みは、障害者の能力を最大限に引き出し、職場での活躍を支援するために不可欠です。
助成金受給後の注意点

助成金を受給した後も、いくつかの注意点があります。
雇用継続義務期間と対象施設設備処分制限期間
助成金受給後は、雇用継続義務期間と対象施設設備処分制限期間を守る必要があります。雇用継続義務期間は、助成金によって雇用した障害者を一定期間雇用し続ける義務です。対象施設設備処分制限期間は、助成金で購入・整備した施設や設備を一定期間処分できない期間です。これらの期間内に義務違反があった場合、助成金の返還を求められることがあります。
助成金返還が必要となるケース:認定取消、不正受給、支給条件違反
助成金の返還が必要となる主なケースは、受給資格の認定が取り消された場合、不正な手段で助成金を受給した場合、支給条件に違反した場合です。例えば、対象障害者の雇用を継続できなかったり、施設・設備を目的外に使用したりした場合などが該当します。
離職時の対応:代替障害者の雇用義務
助成金受給後に、対象障害者が離職した場合、一定期間内に代替となる障害者を雇用する義務が生じることがあります。この義務を怠ると、助成金の返還を求められることがあります。
施設・事業計画変更時の事前相談の重要性
助成金を受けて設置・整備した施設や、事業計画に変更が生じる場合は、必ず事前に担当窓口に相談することが重要です。変更内容によっては、助成金の支給要件を満たさなくなる可能性があり、返還を求められることがあります。
その他の障害者雇用に関する助成金制度

障害者雇用を促進するための助成金制度は、障害者福祉施設設置等助成金だけではありません。
雇い入れに関する助成金
- 特定求職者雇用開発助成金: ハローワーク等の紹介により、障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し助成金が支給されます。発達障害者や難治性疾患患者を雇用する場合、雇用管理に関する事項を把握・報告することで助成金が支給されるコースもあります。
- トライアル雇用助成金: 障害者を試行的に雇い入れる事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対し助成金が支給されます。
職場定着に関する助成金
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース): 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置のいずれかを継続的に講じた事業主に対して助成金が支給されます。
障害者を雇用するために、情報通信技術(ICT)を活用した事例も支給対象となります。
障害福祉事業立ち上げに役立つ助成金・補助金

障害福祉事業、特に障がい者グループホームの立ち上げには、初期費用がかさみます。そこで、国や地方自治体、独立行政法人などが提供する各種助成金・補助金制度の活用を検討しましょう。これらの支援制度を利用することで、事業開始への経済的なハードルを下げることが可能です。
都道府県、独立行政法人、公益財団法人等の助成金・補助金
都道府県レベルでは、社会福祉法人やNPO法人等が施設の新設、改築、増築を行う際に利用できる助成金があります。独立行政法人では、障害者雇用を支援する施設や設備の設置・整備に対する助成金を提供しています。また、公益財団法人では、バリアフリー住宅の新築やリフォームを支援する助成金もあります。
障がい者グループホーム立ち上げ支援
障がい者グループホームの立ち上げに特化した支援制度も存在します。これらの制度は、物件の取得費用や改修費用、運営費の一部を補助するものが多く、事業の初期段階における経済的な負担を軽減するのに役立ちます。各自治体の制度内容を比較検討し、自社の状況に合ったものを選択しましょう。
中小企業庁の補助金:事業再構築補助金
中小企業庁の事業再構築補助金は、中小企業等が新たな事業分野への進出や事業転換を行う際に利用できる制度です。障がい者グループホームの立ち上げも、事業再構築の一環として認められる可能性があります。成長枠、グリーン成長枠など、複数の類型があるので、自社の事業計画に最も適した枠組みを選択しましょう。
助成金・補助金申請の注意点
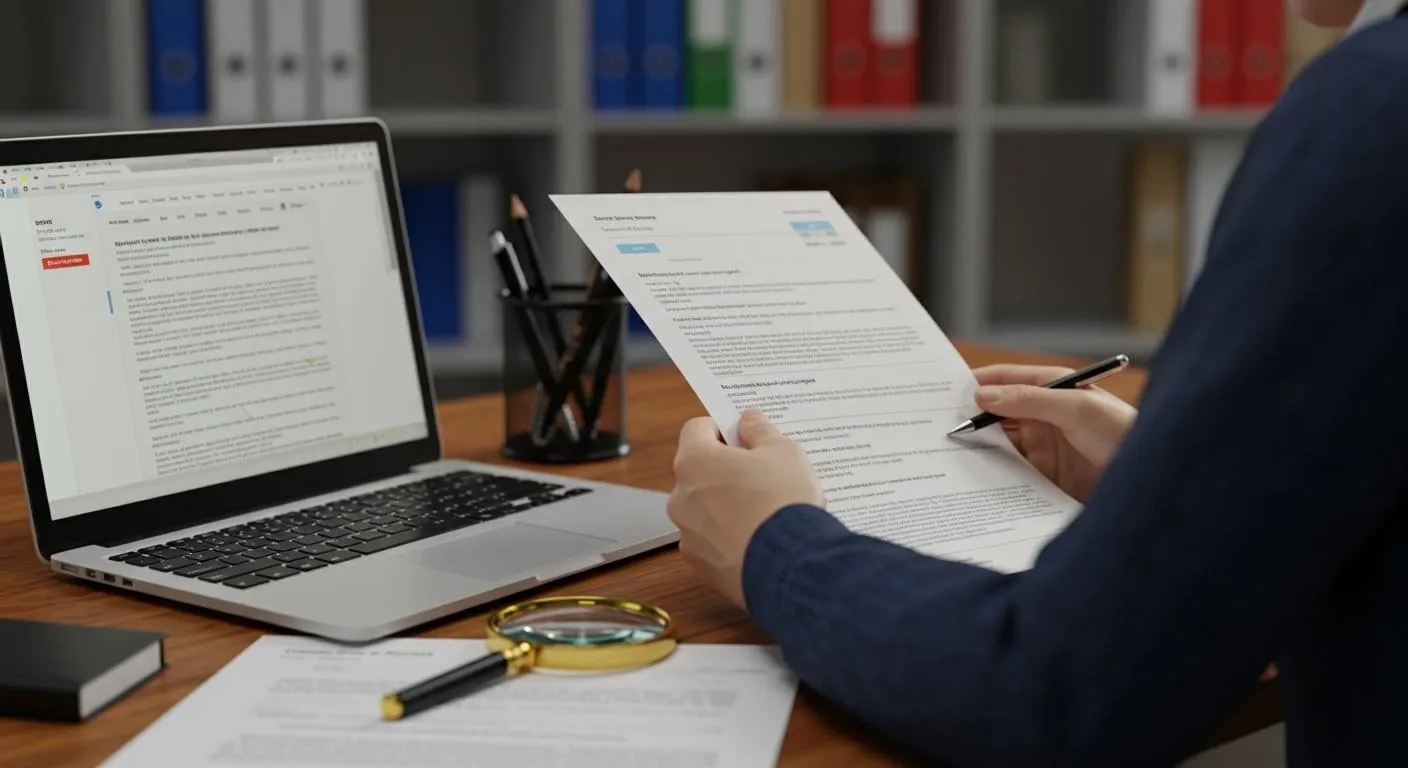
助成金や補助金を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
各制度の要件確認と担当窓口への相談
助成金や補助金の申請にあたっては、各制度の要件を事前にしっかりと確認することが不可欠です。対象となる事業主の条件、助成対象となる費用、助成額などは制度によって異なります。公式サイトやパンフレットを熟読し、不明な点があれば担当窓口に直接問い合わせることをおすすめします。個別の事情に応じて、最適な制度や申請方法についてアドバイスを受けることができるでしょう。
最新情報の確認:公式サイトの活用
助成金・補助金制度は、社会情勢や政策の変化に応じて内容が変更されることがあります。申請を検討する際には、必ず最新情報を確認するようにしましょう。各制度の公式サイトは、最新情報の発信源として最も信頼できます。実施要領や申請書類の変更、申請期間の締め切りなど、重要な情報を漏らさずチェックするように心がけましょう。
まとめ:助成金を活用して、誰もが働きやすい社会へ

障害者雇用に関する助成金制度は、障害のある方がいきいきと活躍できる職場環境づくりを支援する強力なツールです。これらの制度を積極的に活用し、企業の社会的責任を果たすとともに、多様な人材が活躍できる社会の実現に貢献しましょう。詳細については、厚生労働省や各都道府県の労働局にお問い合わせください。
外部関連記事
会社ランキング ファクタリングシークで
今すぐ確認する




